吐泥(へろど)19
2013/06/13 Thu 00:01
童貞青年を性玩具にする妻。実に魅力的な寝取られプレイだったが、しかしそんな私の企みは脆くも崩れた。妻はそんな私の企みを予感していたのか、アイスコーヒーとアイスティーを持った青年がこちらに向かって来るなり私のペニスから手を離し、それまでだらりと緩ませていた股を、いきなりギシッと閉じてしまったのだ。
実は私は、青年がテーブルの上にアイスコーヒーを置くのを狙っていた。その瞬間、わざとそのアイスコーヒーに肘をぶつけ、それを床にぶちまけようと企んでいたのだ。そうなれば当然、青年は慌てて床のコーヒーを拭き始めるだろう。真面目そうな青年は、きっとテーブルの下にまで頭を潜らせながらせっせと拭き始めるだろう。そこで青年は妻の性器を間近に見せつけられるのだ。グジョグジョと指が蠢き、いやらしい汁がダラダラと溢れるその卑猥な光景を間近に見せつけられた童貞は、激しく興奮するに違いなかった。
そして、更に追い討ちをかけるかのように、妻の顔を私の股間に押し付けてやるつもりだった。その時の妻は、見ず知らずの青年に陰部を見られているというこの異常な状況に、極度な興奮状態に陥っているはずであり、だから妻は、迷うことなく私の肉棒にしゃぶりつくに違いなかった。

そこまで青年に見せつけておき、青年の興奮状態を見計らった上で、私がソッと青年に誘いの手を差し伸べるのだ。「私たちの部屋に遊びに来ないか?」と……。
それが私の企みだった。だから私は妻の妖艶な手コキに必死に耐えながら、彼が来るのを待っていたのだが、しかし、またしてもドタキャンされた。あと一歩のところで全ての行為を強制終了され、無残にもドタキャンされてしまったのだった。
無念に顔を歪めていた私は、今の妻のこの状態ではまだまだ安心できないと思った。このままではサウナの入り口でドタキャンされる可能性も高く、何かもっと強烈な楔(くさび)を、今のうちに妻の精神に打ち込んでおかなければと改めて思い知らされた。
妙に冷め切った空気の中、私は無言でアイスコーヒーを啜った。香りもコクも全く感じられない黒い水だった。それでも喉が渇いていた私は、それを一気にズズズッと飲み干し、まだ半分以上アイスティーが残っている妻に、「行くぞ」とボソッと呟いた。
スタスタとレジに向かう途中、またしても妻が「何か怒ってる?」と聞いてきた。私はそう首を傾げている妻の顔を覗き込み、「あたりまえだ」とぶっきら棒に吐き捨てた。
「どうして怒ってるの?」
「キミがドタキャンするからだ」
「ドタキャン? 私が何をドタキャンしたの?」
「あの店員にオマンコを見せなかった」
「私、そんな事するなんて言ってないわよ」
「ああ、言ってないさ。言っていないとも。言ってはないが、しかしキミのアソコは濡れていた。それに私がそれを提案した時、キミは黙ったまま私のチンポもシコシコした。あれは明らかにそれに合意したという意思表示じゃないか!」
突然そう声を荒げると、妻は慌てて辺りを見回した。そして素早く私の袖をギュッと掴むと、「大きな声で変なこと言わないでよ」と、私の目をキッと睨んだのだった。
妻のその目に、私は素直に(マズい)と思った。ここで妻を怒らせてしまっては今後の計画が全て台無しになってしまう恐れがあるのだ。が、しかし、だからと言って、ここでいきなり態度を急変させるのも良くなかった。ここで私が妻に気を使い、下手に出るような事になれば、今後、この旅行においての主導権は妻が握ることになるだろう。そうなれば、それこそサウナの計画など夢のまた夢となり、インチキレビューだらけの食べログ人気店をぐるぐる回るだけのバカ旅行となってしまうのだ。
だからこそ引けなかった。たとえ妻が、怒ろうが、嫌がろうが、泣き喚こうが、ここは絶対に引いてはいけない場面だった。そう思いながら私は黙ってレジに進んだ。今の妻はSになりかけている。そんな妻を一気にドMのヘドロの中に沈めるような、そんな何か強烈なダメージはないものかと考えながら進んだ。
レジの前で足を止めると、奥の厨房からヌッと顔を出した童貞青年が、「ありがとうございますぅ」と語尾を伸ばしながら出てきた。全然忙しくないくせに忙しいふりをしているのが妙に痛々しく、こんなヤツにチンポやマンコを見せなくて良かったとつくづく思った。
童貞は私から伝票を受け取ると、「ご一緒でよろしかったですか?」と聞いた。当たり前だ見ればわかるだろいちいち聞くなゆとりバカ、と心の中で呟きながら「はい」と答えると、童貞は、アイスコーヒーとアイスティーで……と独り言のように呟きながらそれをレジに打ち込み、満面の笑顔で「千百五十円になりますぅ」と、また語尾を伸ばした。その笑顔と口調にイラっとしながらポケットに手を入れると、ふと妻のパンティーが指先に触れた。
途端に(これだ!)と思った。これなら妻にM的な羞恥ダメージを与えられると確信した。チラッと後ろを見ると、妻はまだ不機嫌な顔をして突っ立っていた。心の中で、(そんな不貞腐れた態度も今のうちだぞ……)と呟きながら、それをポケットの中からソッと摘み出した。そしてそれをレジカウンターの上にバサっと置くと、そのネトネトに濡れたクロッチを童貞の前で広げ、「あれ……財布はこっちだったかな……」と、わざとらしくもう片方のポケットを弄り始めたのだった。

童貞は瞬き一つせず、ぐっしょりと濡れた卑猥なクロッチを横目で見ていた。それは、誰が見ても使用済み下着だった。又、この状況から見て、その下着の持ち主がそこにいる女である事は一目瞭然だった。
私はそんな童貞の顔をチラチラと確認しながら背後の妻に振り向いた。そして「財布が見当たらないから、そっちで払っておいてくれ」と言いながら妻にその場所を譲った。「えっ? 財布がないの?」と驚いた妻は、取り敢えず支払いだけ済ませようとバッグから財布を取り出した。そして「おいくらですか?」と改めて聞きながら一歩前に出た瞬間、それを見つけた妻の目がギョッと見開いた。
「あ、はい、千百五十円になります」
そう慌てて答える童貞は、もはや語尾を伸ばしていなかった。妻は自分の汚れた下着を愕然と見つめたまま、財布の中から千円札を二枚取り出した。そんな妻の指は震えていた。重なった二枚の千円札が、震える妻の指でカサカサと乾いた音を鳴らしていた。
「二千円お預かりします」
そう童貞が金を受け取ると、妻のその指が恐る恐るパンティーに伸びた。どうやら妻は、童貞がお釣りを数えている間に、さりげなくそれを取り戻そうとしているらしい。
そんな妻の表情は羞恥で歪んでいた。そのネトネトに濡れているそれは、紛れもなく自分の陰部から滲み出た恥汁であり、そんな汚物を、こうして公然と赤の他人に見られるというのは、女の妻にとってはきっと凄まじい羞恥に違いなかった。
このダメージによって、この後、妻がどう出るかは、もはや賭けだった。怒り狂ってこのまま東京に帰ってしまう可能性もあれば、このままMのヘドロの中にどっぷりと沈む可能性もあった。だから私は、ドキドキしながら妻の表情を伺っていた。丁と出るか半と出るか、それによって今後の私たちの夫婦の関係も変わり、そしてこの小説のストーリーも大きく変わるのだ。
妻は顔を真っ赤に紅潮させながら、そこでベロリと広げられているパンティーに恐る恐る指を伸ばしていた。その表情は激怒しているようにも見え、不意に私は悪い予感を覚えた。が、しかし私は、ふと、妻のその指がパンティーに近づくにつれ、妻の表情がジワジワと変化し始めている事に気づいた。それはあの時に見た、羞恥が欲情へと変わっていく瞬間によく似ていた。
あの時とは、今から半年ほど前の出来事だった。妻が入浴中、何気に私が風呂場のドアを開けると、妻はタイルの上にしゃがみながら小便をしていたのだ。

妻は私に気付くと慌てて太ももにシャワーをあて、証拠隠滅を図ろうとした。しかし、しゃがんだ妻の足元には黄金色に染まった水が広がり、それを完全に隠し通すことはできなかった。
「小便してるのか?」と聞くと、妻は「してないよ」と平然と嘘をついた。そう嘘をつく妻に異様な欲情を覚えた私は、いきなりズカズカと浴室に入り込み、正面から妻の股間を覗いてやった。
案の定、しゃがんだ股からはシャーっと小便が吹き出していた。妻は真っ赤な顔をしながら「あっちに行ってよ」と怒っていたが、しかし女の小便はすぐには止まらないらしく、そのままそれを黙って見られるしか方法はなかった。
私はそんな妻に「股を開いて見せてみろ」と言った。そう言いながらズボンのボタンを外し、勃起したペニスをシコシコとシゴいて見せた。妻は「いやよ、出てってよ」と嫌悪を露わにしていたが、しかし、そんな妻の表情に、羞恥に駆られたマゾの欲望が浮かんでいるのを私は見逃さなかった。
だから私は、わざとシコシコとシゴくペニスを妻に向けながら、「ほら、早く股を開くんだ、小便しているそこに精液をぶっかけてやるから」と言った。すると妻は、今にも泣き出さんばかりに顔を顰め、「もう、出てってよ……」と声を震わせたが、しかし、そう言いながらも妻は股をジワジワと開き始め、その惨めな排尿シーンを私に見せつけた。

小便が吹き出る陰部からは、小便とは違う汁が垂れ、それがタイルの床に向かってニトーっと糸を引いていた。妻は排尿シーンを見られながら興奮していたのだ。
やはり妻はMだった。そう思った私は、まだ小便をしている最中の妻をその場に立ち上がらせようとした。すると妻は、抵抗することなく素直にそれを受け入れ、小便を垂れ流したままその場にゆっくりと立ち上がった。
壁に手をつかせ、尻を突き出させた。尻肉の片側を乱暴に押し開くと、股間の裏側から溢れる小便が太ももにダラダラと垂れているのが見えた。羞恥に駆られた妻が、「もうやめて……」と声を震わせた。それでも私は太ももの裏側に流れる温水を手で掬い、わざとジュルルルっと下品な音を立ててそれを飲んでやった。すると、更に羞恥に駆られた妻が、自らの意思で尻を動かし始めた。「お願いだからやめて……」と言いながらも、早く入れてとばかりに腰をコキコキと振り、その尻肉を私のペニスにグイグイと押し付けてきた。
私は、卑猥に揺れ動くその尻を見下ろしながら、(こいつは本物のマゾだ)と確信した。そして、(このメス豚めが)と心で呟きながら、その死んだ赤貝のようにだらしなく口を開いていた穴に向けて一気に腰を突き上げた。
何の障害もなくペニスがヌルっ滑り込むと、妻は背中を仰け反らせながら「あんっ」と天井を見上げた。そしてそのまま腰を振り、くちゅくちゅと湿った音と、ハァハァと切ない息を浴室に響かせた。
そんな妻の淫らな姿に目眩を感じるほどの興奮を覚えた私は、立ったまま腰を振る妻の腹を抱きかかえた。そしてそのまま機械のように高速で腰を振りまくり、更に妻をマゾのメス豚として狂わせてやったのだった。

あの時の、あの排尿を見られている時の妻の表情と、今の、この汚れた下着を見ず知らずの店員に晒されている時の妻の表情は同じだった。激しい羞恥が性的興奮へと変化した時の、マゾ女独特の歪んだ快楽がそこに滲み出ていた。
そんな妻の指が、カウンターに投げ捨てられたパンティーに触れようとしていた。妻の変化に気づいていた私は、素早く妻の体を押しのけ、カウンターの前に立った。そしてそのパンティーをサッと横取りすると、お釣りを出そうとしていた店員に「これ、凄いだろ」と笑いかけた。
隣にいた妻と、正面にいた店員の顔が、一瞬にして硬直するのがわかった。
私は背筋をゾクゾクさせながら指でパンティーを開いた。そしてそのネトネトに汚れたクロッチを店員に見せつけながら、「この女のパンツだよ」と下品に微笑み、それを目の当たりにしていた妻をヘドロの中に突き落としてやったのだった。

(つづく)
《←目次》《20話へ→》
実は私は、青年がテーブルの上にアイスコーヒーを置くのを狙っていた。その瞬間、わざとそのアイスコーヒーに肘をぶつけ、それを床にぶちまけようと企んでいたのだ。そうなれば当然、青年は慌てて床のコーヒーを拭き始めるだろう。真面目そうな青年は、きっとテーブルの下にまで頭を潜らせながらせっせと拭き始めるだろう。そこで青年は妻の性器を間近に見せつけられるのだ。グジョグジョと指が蠢き、いやらしい汁がダラダラと溢れるその卑猥な光景を間近に見せつけられた童貞は、激しく興奮するに違いなかった。
そして、更に追い討ちをかけるかのように、妻の顔を私の股間に押し付けてやるつもりだった。その時の妻は、見ず知らずの青年に陰部を見られているというこの異常な状況に、極度な興奮状態に陥っているはずであり、だから妻は、迷うことなく私の肉棒にしゃぶりつくに違いなかった。

そこまで青年に見せつけておき、青年の興奮状態を見計らった上で、私がソッと青年に誘いの手を差し伸べるのだ。「私たちの部屋に遊びに来ないか?」と……。
それが私の企みだった。だから私は妻の妖艶な手コキに必死に耐えながら、彼が来るのを待っていたのだが、しかし、またしてもドタキャンされた。あと一歩のところで全ての行為を強制終了され、無残にもドタキャンされてしまったのだった。
無念に顔を歪めていた私は、今の妻のこの状態ではまだまだ安心できないと思った。このままではサウナの入り口でドタキャンされる可能性も高く、何かもっと強烈な楔(くさび)を、今のうちに妻の精神に打ち込んでおかなければと改めて思い知らされた。
妙に冷め切った空気の中、私は無言でアイスコーヒーを啜った。香りもコクも全く感じられない黒い水だった。それでも喉が渇いていた私は、それを一気にズズズッと飲み干し、まだ半分以上アイスティーが残っている妻に、「行くぞ」とボソッと呟いた。
スタスタとレジに向かう途中、またしても妻が「何か怒ってる?」と聞いてきた。私はそう首を傾げている妻の顔を覗き込み、「あたりまえだ」とぶっきら棒に吐き捨てた。
「どうして怒ってるの?」
「キミがドタキャンするからだ」
「ドタキャン? 私が何をドタキャンしたの?」
「あの店員にオマンコを見せなかった」
「私、そんな事するなんて言ってないわよ」
「ああ、言ってないさ。言っていないとも。言ってはないが、しかしキミのアソコは濡れていた。それに私がそれを提案した時、キミは黙ったまま私のチンポもシコシコした。あれは明らかにそれに合意したという意思表示じゃないか!」
突然そう声を荒げると、妻は慌てて辺りを見回した。そして素早く私の袖をギュッと掴むと、「大きな声で変なこと言わないでよ」と、私の目をキッと睨んだのだった。
妻のその目に、私は素直に(マズい)と思った。ここで妻を怒らせてしまっては今後の計画が全て台無しになってしまう恐れがあるのだ。が、しかし、だからと言って、ここでいきなり態度を急変させるのも良くなかった。ここで私が妻に気を使い、下手に出るような事になれば、今後、この旅行においての主導権は妻が握ることになるだろう。そうなれば、それこそサウナの計画など夢のまた夢となり、インチキレビューだらけの食べログ人気店をぐるぐる回るだけのバカ旅行となってしまうのだ。
だからこそ引けなかった。たとえ妻が、怒ろうが、嫌がろうが、泣き喚こうが、ここは絶対に引いてはいけない場面だった。そう思いながら私は黙ってレジに進んだ。今の妻はSになりかけている。そんな妻を一気にドMのヘドロの中に沈めるような、そんな何か強烈なダメージはないものかと考えながら進んだ。
レジの前で足を止めると、奥の厨房からヌッと顔を出した童貞青年が、「ありがとうございますぅ」と語尾を伸ばしながら出てきた。全然忙しくないくせに忙しいふりをしているのが妙に痛々しく、こんなヤツにチンポやマンコを見せなくて良かったとつくづく思った。
童貞は私から伝票を受け取ると、「ご一緒でよろしかったですか?」と聞いた。当たり前だ見ればわかるだろいちいち聞くなゆとりバカ、と心の中で呟きながら「はい」と答えると、童貞は、アイスコーヒーとアイスティーで……と独り言のように呟きながらそれをレジに打ち込み、満面の笑顔で「千百五十円になりますぅ」と、また語尾を伸ばした。その笑顔と口調にイラっとしながらポケットに手を入れると、ふと妻のパンティーが指先に触れた。
途端に(これだ!)と思った。これなら妻にM的な羞恥ダメージを与えられると確信した。チラッと後ろを見ると、妻はまだ不機嫌な顔をして突っ立っていた。心の中で、(そんな不貞腐れた態度も今のうちだぞ……)と呟きながら、それをポケットの中からソッと摘み出した。そしてそれをレジカウンターの上にバサっと置くと、そのネトネトに濡れたクロッチを童貞の前で広げ、「あれ……財布はこっちだったかな……」と、わざとらしくもう片方のポケットを弄り始めたのだった。

童貞は瞬き一つせず、ぐっしょりと濡れた卑猥なクロッチを横目で見ていた。それは、誰が見ても使用済み下着だった。又、この状況から見て、その下着の持ち主がそこにいる女である事は一目瞭然だった。
私はそんな童貞の顔をチラチラと確認しながら背後の妻に振り向いた。そして「財布が見当たらないから、そっちで払っておいてくれ」と言いながら妻にその場所を譲った。「えっ? 財布がないの?」と驚いた妻は、取り敢えず支払いだけ済ませようとバッグから財布を取り出した。そして「おいくらですか?」と改めて聞きながら一歩前に出た瞬間、それを見つけた妻の目がギョッと見開いた。
「あ、はい、千百五十円になります」
そう慌てて答える童貞は、もはや語尾を伸ばしていなかった。妻は自分の汚れた下着を愕然と見つめたまま、財布の中から千円札を二枚取り出した。そんな妻の指は震えていた。重なった二枚の千円札が、震える妻の指でカサカサと乾いた音を鳴らしていた。
「二千円お預かりします」
そう童貞が金を受け取ると、妻のその指が恐る恐るパンティーに伸びた。どうやら妻は、童貞がお釣りを数えている間に、さりげなくそれを取り戻そうとしているらしい。
そんな妻の表情は羞恥で歪んでいた。そのネトネトに濡れているそれは、紛れもなく自分の陰部から滲み出た恥汁であり、そんな汚物を、こうして公然と赤の他人に見られるというのは、女の妻にとってはきっと凄まじい羞恥に違いなかった。
このダメージによって、この後、妻がどう出るかは、もはや賭けだった。怒り狂ってこのまま東京に帰ってしまう可能性もあれば、このままMのヘドロの中にどっぷりと沈む可能性もあった。だから私は、ドキドキしながら妻の表情を伺っていた。丁と出るか半と出るか、それによって今後の私たちの夫婦の関係も変わり、そしてこの小説のストーリーも大きく変わるのだ。
妻は顔を真っ赤に紅潮させながら、そこでベロリと広げられているパンティーに恐る恐る指を伸ばしていた。その表情は激怒しているようにも見え、不意に私は悪い予感を覚えた。が、しかし私は、ふと、妻のその指がパンティーに近づくにつれ、妻の表情がジワジワと変化し始めている事に気づいた。それはあの時に見た、羞恥が欲情へと変わっていく瞬間によく似ていた。
あの時とは、今から半年ほど前の出来事だった。妻が入浴中、何気に私が風呂場のドアを開けると、妻はタイルの上にしゃがみながら小便をしていたのだ。

妻は私に気付くと慌てて太ももにシャワーをあて、証拠隠滅を図ろうとした。しかし、しゃがんだ妻の足元には黄金色に染まった水が広がり、それを完全に隠し通すことはできなかった。
「小便してるのか?」と聞くと、妻は「してないよ」と平然と嘘をついた。そう嘘をつく妻に異様な欲情を覚えた私は、いきなりズカズカと浴室に入り込み、正面から妻の股間を覗いてやった。
案の定、しゃがんだ股からはシャーっと小便が吹き出していた。妻は真っ赤な顔をしながら「あっちに行ってよ」と怒っていたが、しかし女の小便はすぐには止まらないらしく、そのままそれを黙って見られるしか方法はなかった。
私はそんな妻に「股を開いて見せてみろ」と言った。そう言いながらズボンのボタンを外し、勃起したペニスをシコシコとシゴいて見せた。妻は「いやよ、出てってよ」と嫌悪を露わにしていたが、しかし、そんな妻の表情に、羞恥に駆られたマゾの欲望が浮かんでいるのを私は見逃さなかった。
だから私は、わざとシコシコとシゴくペニスを妻に向けながら、「ほら、早く股を開くんだ、小便しているそこに精液をぶっかけてやるから」と言った。すると妻は、今にも泣き出さんばかりに顔を顰め、「もう、出てってよ……」と声を震わせたが、しかし、そう言いながらも妻は股をジワジワと開き始め、その惨めな排尿シーンを私に見せつけた。

小便が吹き出る陰部からは、小便とは違う汁が垂れ、それがタイルの床に向かってニトーっと糸を引いていた。妻は排尿シーンを見られながら興奮していたのだ。
やはり妻はMだった。そう思った私は、まだ小便をしている最中の妻をその場に立ち上がらせようとした。すると妻は、抵抗することなく素直にそれを受け入れ、小便を垂れ流したままその場にゆっくりと立ち上がった。
壁に手をつかせ、尻を突き出させた。尻肉の片側を乱暴に押し開くと、股間の裏側から溢れる小便が太ももにダラダラと垂れているのが見えた。羞恥に駆られた妻が、「もうやめて……」と声を震わせた。それでも私は太ももの裏側に流れる温水を手で掬い、わざとジュルルルっと下品な音を立ててそれを飲んでやった。すると、更に羞恥に駆られた妻が、自らの意思で尻を動かし始めた。「お願いだからやめて……」と言いながらも、早く入れてとばかりに腰をコキコキと振り、その尻肉を私のペニスにグイグイと押し付けてきた。
私は、卑猥に揺れ動くその尻を見下ろしながら、(こいつは本物のマゾだ)と確信した。そして、(このメス豚めが)と心で呟きながら、その死んだ赤貝のようにだらしなく口を開いていた穴に向けて一気に腰を突き上げた。
何の障害もなくペニスがヌルっ滑り込むと、妻は背中を仰け反らせながら「あんっ」と天井を見上げた。そしてそのまま腰を振り、くちゅくちゅと湿った音と、ハァハァと切ない息を浴室に響かせた。
そんな妻の淫らな姿に目眩を感じるほどの興奮を覚えた私は、立ったまま腰を振る妻の腹を抱きかかえた。そしてそのまま機械のように高速で腰を振りまくり、更に妻をマゾのメス豚として狂わせてやったのだった。

あの時の、あの排尿を見られている時の妻の表情と、今の、この汚れた下着を見ず知らずの店員に晒されている時の妻の表情は同じだった。激しい羞恥が性的興奮へと変化した時の、マゾ女独特の歪んだ快楽がそこに滲み出ていた。
そんな妻の指が、カウンターに投げ捨てられたパンティーに触れようとしていた。妻の変化に気づいていた私は、素早く妻の体を押しのけ、カウンターの前に立った。そしてそのパンティーをサッと横取りすると、お釣りを出そうとしていた店員に「これ、凄いだろ」と笑いかけた。
隣にいた妻と、正面にいた店員の顔が、一瞬にして硬直するのがわかった。
私は背筋をゾクゾクさせながら指でパンティーを開いた。そしてそのネトネトに汚れたクロッチを店員に見せつけながら、「この女のパンツだよ」と下品に微笑み、それを目の当たりにしていた妻をヘドロの中に突き落としてやったのだった。

(つづく)
《←目次》《20話へ→》
吐泥(へろど)20
2013/06/13 Thu 00:01
妻が慌ててパンティーを奪い取る可能性はあった。
が、しかし、もはや妻はヘドロに足を取られていた。
横目でチラッと妻を見ると、妻は硬直したままジッと下を向き、羞恥で震える下唇をぎゅっと噛み締めたままだった。
こうなれば、あとはこっちのものだった。ヘドロから抜け出せなくなった妻は、そのままヘドロに飲み込まれて行くだけだ。そして自身もドロドロと蠢くヘドロと化していき、また違う誰かをヘドロの中に引きずり込むのだ。
その生贄がまさにこの店員だった。
本人を目前に、いきなり使用済み下着のシミを見せつけられた彼は、レジの前で身動きひとつせぬままそれをじっと見つめていた。衝撃、恐怖、高揚、戸惑い。この一瞬の間にそれらの表情を見せた彼は既に性的興奮しているに違いなく、恐らくレジカウンターの裏では、ズボンの股間に肉棒の形をくっきりと浮かばせているに違いなかった。
そんな彼の目を見ながら、私はクロッチに指を伸ばした。妻の汁がベッタリと付着しているクロッチに指をヌルヌルと滑らせた。そしてそれを彼に見せつけながら、「キミも触ってごらん」と怪しく微笑み、それを彼の前にそっと差し出した。
彼はそれをじっと見つめたまま、その細長い首にゴルフボール大の喉仏をゴクリと上下させた。そして私たちを一度も見ることなく恐る恐るそこに指を伸ばすと、まるで傷口に軟膏を塗りこむようにして、指をヌルヌルと回し始めたのだった。
さすが童貞青年だけあって堕ちるのが早かった。
ものの数分で彼はヘドロに足を取られてしまった。私は奇妙な高揚感を覚えながら、隣で項垂れている妻を見た。
妻は顔を伏せながらも、前髪の隙間からその光景をジッと見ていた。今にも泣き出しそうな表情をしていたが、しかしマゾが見せる絶望的な表情というのは、いわゆる快楽の表情であるという事を私は知っている。
私は妻の耳元にソッと顔を寄せると、レジ横にあったマガジンラックを指差しながら、「そこでしゃがんで股を開きなさい」と囁いた。
すかさず上目遣いの妻の視線がゆっくりと私に向けられた。妻は黙ったまま横目で私をジッと見つめ、恨めしそうな目で何かを必死に訴えていた。
さすがに、そこまで自分の意思ではできないようだった。欲望はあっても体が言う事を聞かないらしく、妻の足は竦んでいた。だから私は妻の腰にソッと手を回し、妻をその場所へと誘導する事にした。「ほら」と耳元で囁きながら妻の体をソッと押すと、妻は抵抗することなく歩き出した。項垂れながら歩く妻のその姿は、まるで処刑場に連行される死刑囚のようだった。
レジの横にあるマガジンラックの前は、展望台からも監視カメラからも死角になっていた。そこにしゃがめば、レジに立っている青年以外からは、誰からも見られることはなかった。
そこに項垂れたまま突っ立っている妻に、私はまるで犬に躾をしているかのように「しゃがみなさい」と命令した。
私のその声に合わせ、店員の目玉がギロリと横に向くのがわかった。
妻は下唇を噛み締めながらゆっくりと腰を下ろすと、目の前に並んだ二つの膝っ小僧を見つめたまま固まってしまった。そんな妻に、「おっぱいを出しなさい」と言うと、それまで目玉だけを横に向けていた店員が顔ごとこちらにサッと向けた。
いきなり店員と目が合った私は、「ここだったら出しても構わないでしょ?」と聞いた。
店員は黙ったまま唇を震わせ、何かと必死に葛藤していた。
「見たいでしょ?」と、更に私は店員を追い込むと、店員は黒縁メガネの中の目玉をそわそわと動かし始めた。そして意を決したようにコクンっと小さく頷くと、その血走った目玉を妻に向けたのだった。
「よし」と私が唇を歪めると、それを合図に妻が上着をスルスルと捲り始めた。
ヘソ、脇腹の順番でブラジャーに包まれた乳肉が現れた。そしてそのブラジャーを捲り上げると、そこから豊満な乳肉がポロンっと溢れ、まるで巨大な水風船のようにタプンっと跳ねた。
「どうだ……大きいだろ……あれは猫の腹みたいに柔らかくて温かいんだぞ……」
そう店員に振り返りながら笑いかけると、店員は呆然と見ていたその目をいきなりギョッと見開き、再びゴルフボール大の喉仏をゴクリと上下させた。
そんな店員の視線の先には、今にも泣きそうな顔をした妻が股を大きく開いていた。まだ私は何も命令していないというのに、妻は自らの意思で股を開き、その卑猥な陰部を見ず知らずの青年に露出していたのだった。

そんな妻の勝手な行動に、私は金属バットで後頭部を殴られたような衝撃を受けた。そのショックが次第に嫉妬へと変わり、妻に対する疑念へと変わった。
しかしそんな感情はすぐに性的興奮へと移行され、私は激しい欲情の念を抱いた。この異常なる感情の変化は、まさに寝取られ願望者の悲しき性だった。
妻の陰部からは透明の汁が糸を引き、それが床に垂れては小さな水溜りを作っていた。それを店員は、半開きの唇からハァハァと荒い息を吐きながら凝視していた。
(見るな……見ないでくれ……)私はそう店員の横顔に必死に呟いていた。しかし、そう呟きながらも、私はそっとパンティーを摘み上げるとそれを店員の目前に突きつけた。
「あの変態女のマンコの匂い……嗅いでみろよ……」
そう囁くと、店員は一瞬私の目をギロッと睨みながらも、恐る恐るそれを受け取った。そして震える指でそれを広げると、その一番汚れた部分を見つめながら大きく息を吐き、そこにゆっくりと鼻を近づけようとした。
しかし、それを見ていた妻が、「やめて」と悲痛な声で言うと、店員は「はっ」と我に帰った。そしていきなり「すみません」と謝りながら慌ててパンティーをカウンターの上に置いた。
すかさず私は店員の耳元に顔を近づけた。「キミはバカだな……」と囁きながら再びパンティーを摘んだ。そして、「あの女はマゾなんだ。羞恥心を与えられて喜ぶ変態なんだ。だから『やめて』と言いながらも実はそれを望んでいるんだよ……」と笑い、摘んだパンティーを彼の目の前にぶら下げた。
すると店員は、「そ、そうなんですか……」と呟き、ブラブラとぶら下がる目の前のパンティーをジッと見つめた。「ほら」と私がそれを突き出すと、店員はまるで催眠術にかかったかのように恐る恐るそれを摘み返し、酷く戸惑いながらもその一番汚れた部分をクンクンと嗅ぎ始めたのだった。

「どうだい……いやらしい匂いが脳をジンジンと痺れさせるだろ……」
「……はい……」
「変態女の汁はどんな匂いがする?」
「……汗の匂いがします……」
店員は、荒い息を震わせながらそう答えた。
そんな店員の耳元に、私は再び顔を寄せた。そして、熱い息をその耳元に吹きかけながら、「あの女とヤらせてあげようか?」と囁いた。
すかさず店員が、「で、でも……」と慌てて私に振り返った。私は鼻で笑いながら、「どうせキミは童貞だろ……彼女いないんだろ……あんないい女とデキる何て、こんなチャンスは二度とないぜ……」と囁いた。すると店員は愕然としながら再び顔を妻に向けた。そして妻のその淫らな姿を怯えた目で見つめながら、再び「でも……」と呟いたのだった。
私は素早く辺りを見回した。この優柔不断な童貞青年をホテルの部屋に連れ込むには、かなりの時間を要するだろうと思った私は、手っ取り早くそこら辺でデキないものかと、急いでその場所を探した。
レジカウンターの裏に狭い厨房があった。その厨房の奥に、いかにも裏口っぽいガラスのドアが見えた。「あのドアの向こうは?」とそこを指差しながら聞くと、店員は「バルコニーですけど……」と答えた。
確かここは三十一階だった。パンフレットにも地上百二十五メートルの展望台と書いてあった。そんなバルコニーなら、外から誰かに見られる心配はない。
そう思うなり、私は店員に「あのバルコニーで待ってろ」と告げた。店員は「えっ!」と戸惑っていたが、しかし私に強引に背中を押され、三十一階のバルコニーへと突き出された。
すぐさま妻のところへ戻ると、しゃがんだまま項垂れていた妻を強引に立たせ、無言でバルコニーへと連行した。
バルコニーのドアを開けるなり、生温い潮風の突風が襲いかかってきた。三畳ほどの狭いスペースに巨大なダストボックスが置かれ、正面のフェンスは花壇で仕切られていた。そんなバルコニーの隅で、店員は呆然と立ち尽くしていた。
もはや言葉はいらなかった。私は店員のズボンに手を伸ばすと、無言でベルトを外し始めた。「いや、ちょっと、それは……」と焦ってはいたが、しかし彼は、私のその手を止めようとはしなかった。
既にペニスは勃起していた。さすが童貞だと頷けるほどに劣悪な代物だった。仮性包茎の皮はベロリと捲れ、テラテラに濡れ輝いた亀頭がヌッと突き出ていた。その痛々しいほどにピンク色をした亀頭には白濁の恥垢がドロドロと付着し、まるで犬のペニスのようだった。
この汚いペニスを妻に……と思うと、たちまち私は強烈な興奮に襲われた。
彼は名前も知らない見ず知らずの男だ。不細工で不潔で貧乏くさい童貞男で、しかもそのペニスはこれだけ汚れているのだ。
寝取られという特殊な性癖を持つマゾヒストな私にとって、彼は申し分のない相手だった。妻の相手となるべく男というのは、キラキラと輝くジャニーズ系の美少年よりも、ドロドロとした蛭子能収系のキモ男の方が良く、そんな男に大切な妻を汚されるシチュエーションの方が、マゾヒストな私は興奮するのである。
私は、ドアの前で項垂れている妻の前に立つと、いきなりスカートの中に手を入れ、乱暴に陰毛の中を弄った。ヌルヌルの割れ目に指を滑らせ、グチュグチュと卑猥な音を立てると、「うっ」と顔を顰める妻の顔を覗き込みながら、「あの汚いちんぽをしゃぶりなさい」と囁いた。
妻は今にも泣き出しそうな表情で、「いや……」と呟いたが、それでも私は妻の手を強引に引っ張り、店員の足元に妻をしゃがませた。
店員のズボンを足首までスルッと下ろし、妻の目の前に強烈にイカ臭い肉棒を突き立ててやると、妻はゆっくりと私の顔を見上げながら、もう一度「いや……」と首を振ったが、しかし、そう首を振りながらも妻の手はペニスへと伸びていた。
妻の指がその根元をがっしりと握りしめた。途端に店員は「あっ」と小さく叫びながら腰をスッと引いた。
妻はその臭汁がテラテラと濡れ輝く肉棒を上下に動かし始めた。そして恨めしそうな目で私を見つめながらそこに顔を近づけると、まるで大型犬が水を飲むように大きく舌を動かしながら、ペニスの裏を舐め始めたのだった。

店員はハァハァと荒い息を吐きながら、ベロベロと舌を動かす妻を見下ろしていた。時折私を見つめては何かを必死に訴えていたが、私はそんな店員の視線を無視し、しゃがんだ妻の背後に腰を下ろした。
妻の背中をそっと抱きしめると、甘い香水が漂ううなじに顔を埋めた。白く柔らかいうなじに唇を滑らせ、そのまま耳元に、「童貞のチンポはおいしいか……」と囁き、心の中で(変態女……)と付け加えた。
そんな卑猥な言葉をコソコソと耳元に囁きながら、私は妻のワンピースのボタンを外した。巨大な乳肉がポタンっと溢れ、店員の視線が一気にそこに注がれた。私は店員にサービスするかのように、その乳肉を両手の平で持ち上げると、それをタプタプと揺らしてやった。すると私のその手の平に妻の乳首がコリコリと擦れた。それに刺激されたのか、今まで舌をベロベロと動かしていた妻は「ああああ」と息を吐き、そしてそのまま丸く開いたその口でペニスをパクッと咥えたのだった。

私のすぐ目の前で、妻が見知らぬ男の肉棒を咥えていた。「んぐ、んぐ、んぐ」と喉を鳴らし、その唇に、プチャ、プチャ、プチャ、という湿った音を立てていた。
嫉妬と興奮が入り乱れ、クラクラと目眩を感じた。しゃがんだ妻のスカートを捲し上げると、ポチャポチャとした大きな尻が堰を切ったかのようにプルンっと飛び出した。それはまるで、皿に落とされたプッチンプリンのようにフルルンっと揺れていた。
その谷間に指を滑り込ませると、大量の汁がネバネバと指に絡みついてきた。そうしながら、もう片方の手でズボンのチャックを開け、勃起したペニスを妻の尻肉にグイグイと押し付けた。そうしながら、店員の肉棒を行ったり来たりしている妻の唇を見ていると、このまま尻から入れてしまいたいという衝動に駆られた。
他人のペニスを咥える妻を背後から犯す。それは恐らく、今までにない快楽に違いなかった。そのヌルヌルの穴にペニスをヌポヌポさせ、尻をユッサユッサと激しく揺らし、そして店員が射精すると同時に、そこに大量の精液を中出しする。
今までに、幾度も夢見たシーンだった。それを妄想をするだけで、凄まじい快楽を得ることができるほどだった。

が、しかし、私は耐えた。いつもの私なら見境なく欲望を遂げようとするが、しかし今日の私は違った。
それは、あと数時間もすれば、もっと凄い快楽を現実に得られることができるからである。だから私は必死に我慢した。まるで素股ヘルスの尻コキのように、尻肉の谷間にペニスをヌルヌルと滑らせるだけに留めていた。
そうやって必死に耐えていると、頭上から聞こえてくる店員の鼻息が次第に乱れてきた。その鼻息に合わせ、妻の顔の動きも激しくなってきた。(そろそろだな)と思いながら、私もその瞬間に便乗しようと、尻肉に擦り付けるペニスの動きを早めた。
その直後、店員が「あっ」と小さく叫んだ。(イッたな……)と思いながら、私は肉棒を咥える妻の横顔を見つめた。
妻の顔の動きは止まっていた。迸る精液を受け止めている最中らしく、まるで炭酸飲料水を一気飲みしているかのように苦しそうな表情をしていた。
そんな妻の耳元にソッと唇を這わせた。「全部飲み干すんだよ……」と囁くなり、自分で言ったその言葉に脳を刺激されてしまった私は、たちまち妻の尻に大量の精液を飛び散らせた。
店員が、「ああああ……」と唸りながら空を見上げた。妻は「んん……んん……」と唸りながら顔をゆっくりと動かした。そんな妻の両頬が凹んでいた。そんな妻の喉がゴクリと動いた。

(つづく)
《←目次》《21話へ→》
が、しかし、もはや妻はヘドロに足を取られていた。
横目でチラッと妻を見ると、妻は硬直したままジッと下を向き、羞恥で震える下唇をぎゅっと噛み締めたままだった。
こうなれば、あとはこっちのものだった。ヘドロから抜け出せなくなった妻は、そのままヘドロに飲み込まれて行くだけだ。そして自身もドロドロと蠢くヘドロと化していき、また違う誰かをヘドロの中に引きずり込むのだ。
その生贄がまさにこの店員だった。
本人を目前に、いきなり使用済み下着のシミを見せつけられた彼は、レジの前で身動きひとつせぬままそれをじっと見つめていた。衝撃、恐怖、高揚、戸惑い。この一瞬の間にそれらの表情を見せた彼は既に性的興奮しているに違いなく、恐らくレジカウンターの裏では、ズボンの股間に肉棒の形をくっきりと浮かばせているに違いなかった。
そんな彼の目を見ながら、私はクロッチに指を伸ばした。妻の汁がベッタリと付着しているクロッチに指をヌルヌルと滑らせた。そしてそれを彼に見せつけながら、「キミも触ってごらん」と怪しく微笑み、それを彼の前にそっと差し出した。
彼はそれをじっと見つめたまま、その細長い首にゴルフボール大の喉仏をゴクリと上下させた。そして私たちを一度も見ることなく恐る恐るそこに指を伸ばすと、まるで傷口に軟膏を塗りこむようにして、指をヌルヌルと回し始めたのだった。
さすが童貞青年だけあって堕ちるのが早かった。
ものの数分で彼はヘドロに足を取られてしまった。私は奇妙な高揚感を覚えながら、隣で項垂れている妻を見た。
妻は顔を伏せながらも、前髪の隙間からその光景をジッと見ていた。今にも泣き出しそうな表情をしていたが、しかしマゾが見せる絶望的な表情というのは、いわゆる快楽の表情であるという事を私は知っている。
私は妻の耳元にソッと顔を寄せると、レジ横にあったマガジンラックを指差しながら、「そこでしゃがんで股を開きなさい」と囁いた。
すかさず上目遣いの妻の視線がゆっくりと私に向けられた。妻は黙ったまま横目で私をジッと見つめ、恨めしそうな目で何かを必死に訴えていた。
さすがに、そこまで自分の意思ではできないようだった。欲望はあっても体が言う事を聞かないらしく、妻の足は竦んでいた。だから私は妻の腰にソッと手を回し、妻をその場所へと誘導する事にした。「ほら」と耳元で囁きながら妻の体をソッと押すと、妻は抵抗することなく歩き出した。項垂れながら歩く妻のその姿は、まるで処刑場に連行される死刑囚のようだった。
レジの横にあるマガジンラックの前は、展望台からも監視カメラからも死角になっていた。そこにしゃがめば、レジに立っている青年以外からは、誰からも見られることはなかった。
そこに項垂れたまま突っ立っている妻に、私はまるで犬に躾をしているかのように「しゃがみなさい」と命令した。
私のその声に合わせ、店員の目玉がギロリと横に向くのがわかった。
妻は下唇を噛み締めながらゆっくりと腰を下ろすと、目の前に並んだ二つの膝っ小僧を見つめたまま固まってしまった。そんな妻に、「おっぱいを出しなさい」と言うと、それまで目玉だけを横に向けていた店員が顔ごとこちらにサッと向けた。
いきなり店員と目が合った私は、「ここだったら出しても構わないでしょ?」と聞いた。
店員は黙ったまま唇を震わせ、何かと必死に葛藤していた。
「見たいでしょ?」と、更に私は店員を追い込むと、店員は黒縁メガネの中の目玉をそわそわと動かし始めた。そして意を決したようにコクンっと小さく頷くと、その血走った目玉を妻に向けたのだった。
「よし」と私が唇を歪めると、それを合図に妻が上着をスルスルと捲り始めた。
ヘソ、脇腹の順番でブラジャーに包まれた乳肉が現れた。そしてそのブラジャーを捲り上げると、そこから豊満な乳肉がポロンっと溢れ、まるで巨大な水風船のようにタプンっと跳ねた。
「どうだ……大きいだろ……あれは猫の腹みたいに柔らかくて温かいんだぞ……」
そう店員に振り返りながら笑いかけると、店員は呆然と見ていたその目をいきなりギョッと見開き、再びゴルフボール大の喉仏をゴクリと上下させた。
そんな店員の視線の先には、今にも泣きそうな顔をした妻が股を大きく開いていた。まだ私は何も命令していないというのに、妻は自らの意思で股を開き、その卑猥な陰部を見ず知らずの青年に露出していたのだった。

そんな妻の勝手な行動に、私は金属バットで後頭部を殴られたような衝撃を受けた。そのショックが次第に嫉妬へと変わり、妻に対する疑念へと変わった。
しかしそんな感情はすぐに性的興奮へと移行され、私は激しい欲情の念を抱いた。この異常なる感情の変化は、まさに寝取られ願望者の悲しき性だった。
妻の陰部からは透明の汁が糸を引き、それが床に垂れては小さな水溜りを作っていた。それを店員は、半開きの唇からハァハァと荒い息を吐きながら凝視していた。
(見るな……見ないでくれ……)私はそう店員の横顔に必死に呟いていた。しかし、そう呟きながらも、私はそっとパンティーを摘み上げるとそれを店員の目前に突きつけた。
「あの変態女のマンコの匂い……嗅いでみろよ……」
そう囁くと、店員は一瞬私の目をギロッと睨みながらも、恐る恐るそれを受け取った。そして震える指でそれを広げると、その一番汚れた部分を見つめながら大きく息を吐き、そこにゆっくりと鼻を近づけようとした。
しかし、それを見ていた妻が、「やめて」と悲痛な声で言うと、店員は「はっ」と我に帰った。そしていきなり「すみません」と謝りながら慌ててパンティーをカウンターの上に置いた。
すかさず私は店員の耳元に顔を近づけた。「キミはバカだな……」と囁きながら再びパンティーを摘んだ。そして、「あの女はマゾなんだ。羞恥心を与えられて喜ぶ変態なんだ。だから『やめて』と言いながらも実はそれを望んでいるんだよ……」と笑い、摘んだパンティーを彼の目の前にぶら下げた。
すると店員は、「そ、そうなんですか……」と呟き、ブラブラとぶら下がる目の前のパンティーをジッと見つめた。「ほら」と私がそれを突き出すと、店員はまるで催眠術にかかったかのように恐る恐るそれを摘み返し、酷く戸惑いながらもその一番汚れた部分をクンクンと嗅ぎ始めたのだった。

「どうだい……いやらしい匂いが脳をジンジンと痺れさせるだろ……」
「……はい……」
「変態女の汁はどんな匂いがする?」
「……汗の匂いがします……」
店員は、荒い息を震わせながらそう答えた。
そんな店員の耳元に、私は再び顔を寄せた。そして、熱い息をその耳元に吹きかけながら、「あの女とヤらせてあげようか?」と囁いた。
すかさず店員が、「で、でも……」と慌てて私に振り返った。私は鼻で笑いながら、「どうせキミは童貞だろ……彼女いないんだろ……あんないい女とデキる何て、こんなチャンスは二度とないぜ……」と囁いた。すると店員は愕然としながら再び顔を妻に向けた。そして妻のその淫らな姿を怯えた目で見つめながら、再び「でも……」と呟いたのだった。
私は素早く辺りを見回した。この優柔不断な童貞青年をホテルの部屋に連れ込むには、かなりの時間を要するだろうと思った私は、手っ取り早くそこら辺でデキないものかと、急いでその場所を探した。
レジカウンターの裏に狭い厨房があった。その厨房の奥に、いかにも裏口っぽいガラスのドアが見えた。「あのドアの向こうは?」とそこを指差しながら聞くと、店員は「バルコニーですけど……」と答えた。
確かここは三十一階だった。パンフレットにも地上百二十五メートルの展望台と書いてあった。そんなバルコニーなら、外から誰かに見られる心配はない。
そう思うなり、私は店員に「あのバルコニーで待ってろ」と告げた。店員は「えっ!」と戸惑っていたが、しかし私に強引に背中を押され、三十一階のバルコニーへと突き出された。
すぐさま妻のところへ戻ると、しゃがんだまま項垂れていた妻を強引に立たせ、無言でバルコニーへと連行した。
バルコニーのドアを開けるなり、生温い潮風の突風が襲いかかってきた。三畳ほどの狭いスペースに巨大なダストボックスが置かれ、正面のフェンスは花壇で仕切られていた。そんなバルコニーの隅で、店員は呆然と立ち尽くしていた。
もはや言葉はいらなかった。私は店員のズボンに手を伸ばすと、無言でベルトを外し始めた。「いや、ちょっと、それは……」と焦ってはいたが、しかし彼は、私のその手を止めようとはしなかった。
既にペニスは勃起していた。さすが童貞だと頷けるほどに劣悪な代物だった。仮性包茎の皮はベロリと捲れ、テラテラに濡れ輝いた亀頭がヌッと突き出ていた。その痛々しいほどにピンク色をした亀頭には白濁の恥垢がドロドロと付着し、まるで犬のペニスのようだった。
この汚いペニスを妻に……と思うと、たちまち私は強烈な興奮に襲われた。
彼は名前も知らない見ず知らずの男だ。不細工で不潔で貧乏くさい童貞男で、しかもそのペニスはこれだけ汚れているのだ。
寝取られという特殊な性癖を持つマゾヒストな私にとって、彼は申し分のない相手だった。妻の相手となるべく男というのは、キラキラと輝くジャニーズ系の美少年よりも、ドロドロとした蛭子能収系のキモ男の方が良く、そんな男に大切な妻を汚されるシチュエーションの方が、マゾヒストな私は興奮するのである。
私は、ドアの前で項垂れている妻の前に立つと、いきなりスカートの中に手を入れ、乱暴に陰毛の中を弄った。ヌルヌルの割れ目に指を滑らせ、グチュグチュと卑猥な音を立てると、「うっ」と顔を顰める妻の顔を覗き込みながら、「あの汚いちんぽをしゃぶりなさい」と囁いた。
妻は今にも泣き出しそうな表情で、「いや……」と呟いたが、それでも私は妻の手を強引に引っ張り、店員の足元に妻をしゃがませた。
店員のズボンを足首までスルッと下ろし、妻の目の前に強烈にイカ臭い肉棒を突き立ててやると、妻はゆっくりと私の顔を見上げながら、もう一度「いや……」と首を振ったが、しかし、そう首を振りながらも妻の手はペニスへと伸びていた。
妻の指がその根元をがっしりと握りしめた。途端に店員は「あっ」と小さく叫びながら腰をスッと引いた。
妻はその臭汁がテラテラと濡れ輝く肉棒を上下に動かし始めた。そして恨めしそうな目で私を見つめながらそこに顔を近づけると、まるで大型犬が水を飲むように大きく舌を動かしながら、ペニスの裏を舐め始めたのだった。

店員はハァハァと荒い息を吐きながら、ベロベロと舌を動かす妻を見下ろしていた。時折私を見つめては何かを必死に訴えていたが、私はそんな店員の視線を無視し、しゃがんだ妻の背後に腰を下ろした。
妻の背中をそっと抱きしめると、甘い香水が漂ううなじに顔を埋めた。白く柔らかいうなじに唇を滑らせ、そのまま耳元に、「童貞のチンポはおいしいか……」と囁き、心の中で(変態女……)と付け加えた。
そんな卑猥な言葉をコソコソと耳元に囁きながら、私は妻のワンピースのボタンを外した。巨大な乳肉がポタンっと溢れ、店員の視線が一気にそこに注がれた。私は店員にサービスするかのように、その乳肉を両手の平で持ち上げると、それをタプタプと揺らしてやった。すると私のその手の平に妻の乳首がコリコリと擦れた。それに刺激されたのか、今まで舌をベロベロと動かしていた妻は「ああああ」と息を吐き、そしてそのまま丸く開いたその口でペニスをパクッと咥えたのだった。

私のすぐ目の前で、妻が見知らぬ男の肉棒を咥えていた。「んぐ、んぐ、んぐ」と喉を鳴らし、その唇に、プチャ、プチャ、プチャ、という湿った音を立てていた。
嫉妬と興奮が入り乱れ、クラクラと目眩を感じた。しゃがんだ妻のスカートを捲し上げると、ポチャポチャとした大きな尻が堰を切ったかのようにプルンっと飛び出した。それはまるで、皿に落とされたプッチンプリンのようにフルルンっと揺れていた。
その谷間に指を滑り込ませると、大量の汁がネバネバと指に絡みついてきた。そうしながら、もう片方の手でズボンのチャックを開け、勃起したペニスを妻の尻肉にグイグイと押し付けた。そうしながら、店員の肉棒を行ったり来たりしている妻の唇を見ていると、このまま尻から入れてしまいたいという衝動に駆られた。
他人のペニスを咥える妻を背後から犯す。それは恐らく、今までにない快楽に違いなかった。そのヌルヌルの穴にペニスをヌポヌポさせ、尻をユッサユッサと激しく揺らし、そして店員が射精すると同時に、そこに大量の精液を中出しする。
今までに、幾度も夢見たシーンだった。それを妄想をするだけで、凄まじい快楽を得ることができるほどだった。

が、しかし、私は耐えた。いつもの私なら見境なく欲望を遂げようとするが、しかし今日の私は違った。
それは、あと数時間もすれば、もっと凄い快楽を現実に得られることができるからである。だから私は必死に我慢した。まるで素股ヘルスの尻コキのように、尻肉の谷間にペニスをヌルヌルと滑らせるだけに留めていた。
そうやって必死に耐えていると、頭上から聞こえてくる店員の鼻息が次第に乱れてきた。その鼻息に合わせ、妻の顔の動きも激しくなってきた。(そろそろだな)と思いながら、私もその瞬間に便乗しようと、尻肉に擦り付けるペニスの動きを早めた。
その直後、店員が「あっ」と小さく叫んだ。(イッたな……)と思いながら、私は肉棒を咥える妻の横顔を見つめた。
妻の顔の動きは止まっていた。迸る精液を受け止めている最中らしく、まるで炭酸飲料水を一気飲みしているかのように苦しそうな表情をしていた。
そんな妻の耳元にソッと唇を這わせた。「全部飲み干すんだよ……」と囁くなり、自分で言ったその言葉に脳を刺激されてしまった私は、たちまち妻の尻に大量の精液を飛び散らせた。
店員が、「ああああ……」と唸りながら空を見上げた。妻は「んん……んん……」と唸りながら顔をゆっくりと動かした。そんな妻の両頬が凹んでいた。そんな妻の喉がゴクリと動いた。

(つづく)
《←目次》《21話へ→》
吐泥(へろど)21
2013/06/13 Thu 00:01
時刻は既に四時を過ぎていた。ホテルの三階にある図書館のようなカフェに寄り、どうでもいいサンドイッチを食べていた。
つい数時間前の新幹線の中では、『食べログ』を見ながらあれが食べたいこれが食べたいとはしゃいでいた妻も、今は黙ってそれを食べていた。会話もせず、目を合わせることもなく、二人はこのどこにでもあるサンドイッチを黙々と食べていた。しかもそれは異様にパサパサしており、やたらと喉に詰まるサンドイッチだった。
向かい合って座る妻と私の間には、まるでコールタールのようなドロドロとした重たい空気が漂っていた。それは、単独男とプレイしたラブホから帰る途中の車中の空気によく似ていた。
他人にヤられた妻と、他人にヤらせた夫。他人棒に乱れながら痴態を晒していた妻と、その妻の痴態を見ながら自慰に狂っていた夫。そんな二人が乗り込む車中は、無人のように静まり返り、互いに合わせる顔もなければ、交わす言葉もなかった。
あの時と同じ重たい空気が、今の二人にも漂っていた。
はっきり言って気まずかった。店員のペニスをしゃぶらせている最中は、互いにあれだけ燃え上がっていたのに、その行為後はバケツの水をぶっかけられたように冷め、嫌な気まずさだけがブスブスと燻っていた。
そんな空気の中、アイスティーを一口飲んだ妻が、「パンツ……」とポツリと呟いた。それは、行為後の妻が初めて口にした言葉であり、その時初めて、行為後の妻の顔をまともに見た気がした。
「ああ、そうだったね……」と、慌ててポケットからピンクのパンティーを取り出すと、まるで不正な金を政治家の秘書に渡すかのように、それを机の下からソッと渡した。
てっきりトイレに行くものと思っていたが、しかし妻は、それを受け取るなりその場で素早くそれを履いた。
そのパンティーは他人に嗅がれたものだった。濡れたクロッチを指で弄られたものだった。普段の妻なら、そんなパンツを履く事に抵抗を感じるはずだったが、しかし今の妻はすんなりそれを履いた。
そんな妻を見つめながら、ふと思った。
この女は、ついさっきまで見ず知らずの男の性器を舐めていたのだ。恥垢にまみれ、強烈にイカ臭いペニスを何の抵抗もなくしゃぶり、挙句の果てには、どんな性病が含まれているかもわからないような精液を飲み干したのだ。この女は異常者なのだ。だからそんなパンツでも、この女は何の抵抗もなく履けるのだ……と。
そう思っていると、未だドロドロに濡れている妻の膣に、それがピタリと張り付くシーンが頭に浮かんだ。そのカピカピに乾いていたクロッチに、残り汁がジワジワと染み込み、そこに新たなる卑猥なシミが浮かぶのを想像した。

(恐らく今の妻は、ヤリたくてヤリたくて堪らないはずだ……)
そう思うなり再びムラッと欲情した。私はこの短時間で既に三回も射精していた。しかし異常性欲者の私は、このままここで、妖艶な妻の顔を見ながらペニスをシゴきたいと思うほどに興奮していた。
「あの店員とヤリたかったか?」
そう声を震わせながら妻に聞くと、妻はストローに口をつけながら上目遣いで私を見た。そして白いストローに茶色いアイスティーをスッと走らせると、私の目をジッと見たまま「クスッ」と小さく笑った。
それは、ついさっきまでMだった妻からは想像できないSの微笑みだった。そんな挑発的な微笑みに私は心の臓を抉られた。怒り、悲しみ、絶望、嫉妬。それらが頭の中でドロドロと渦巻き、それと同時に身震いするような性的興奮を覚えた私は、拳が震えるほどに激しく動揺した。
そもそも寝取られ願望者というのは、限りなくSでありながら、果てしなくMだった。最愛の妻を見ず知らずの男に抱かせるというサディズムな凶暴性は、妻のメスの部分を見てみたいというマゾヒズムな被虐性が起源であり、寝取られ願望のある夫というのは、表裏一体化したサドマゾヒズムなのである。
もちろん、それに従う妻も同じだった。他人棒に悶えている時の妻は、その姿を最愛の夫に『見られている』というM的な快楽と、『見せている』というS的な快楽に溺れていた。その二つの快楽を交互に受けながら、それによって異常な性欲を湧き上がらせているのだった。

妻のその小悪魔的な微笑みを見た瞬間、私は凄まじい恐怖に襲われた。店員の肉棒に唇を滑らせていたシーンや、恍惚とした表情で精液を飲んでいたシーンが頭の中を駆け巡り、思わず私は、泣き出したくなるほどの絶望感に襲われた。
もうやめよう、と思った。こんなことを続けていると、今に取り返しのつかないことになってしまうと心底思った。最愛の妻を壊したくない。最愛の妻を失くしたくない。そう焦りながら私は、今すぐ東京に帰ろうと思い、無言でスクっと立ち上がった。
すると、ストローを唇に挟んだままの妻が「ん?」と首を傾げながら私を見上げた。
「もう行くの? まだサンドイッチがこんなに残ってるよ?」
私の絶望感を逆撫でするかのように妻は優しく微笑んだ。妻のその愛らしい顔を見ていると、突然胸底から異様な興奮がムラムラと湧き上がってきた。
(お前はその唇であの薄汚いチンポをしゃぶっていた……チンカスも精液も、そのアイスティーのように飲み込んでしまった……)
膝がガクガクと震えた。目は血走り、奥歯が鳴り、全身の毛穴が開いた。
(もしあの時、私があの場にいなければ、きっとお前はあの店員にヤらせていたはずだ……例えあの店員がそれを拒否したとしても、お前はあいつを床に押し倒し、強引にあいつの上に跨っては、チンポを自分のマンコに入れていただろう……)

その光景を想像すると、半開きの唇からハァハァと荒い息が漏れた。その激しい酸素により、それまで絶望で固まっていた脳が活性化し始め、みるみると感情が蘇ってきた。
「行くぞ」と呟く私は、痛いほどに勃起していた。そのままスタスタと歩き出すと、妻は「もう」と唇を尖らせながら立ち上がり、慌てて伝票を持ってレジに走った。
出口で立ち止まっていた私は、レジでお金を払っている妻を見ていた。レジを打つ男性店員のすぐ目の前で、妻の大きな乳肉がタプタプしていた。それを見ながらズボンのポケットの中に手を入れた。そしてポケットの中から勃起したペニスをギュッと握りしめながら、(あの女を……滅茶苦茶にしてやる……)と呟いた。そんな私の脳は、再びヘドロと化していた。
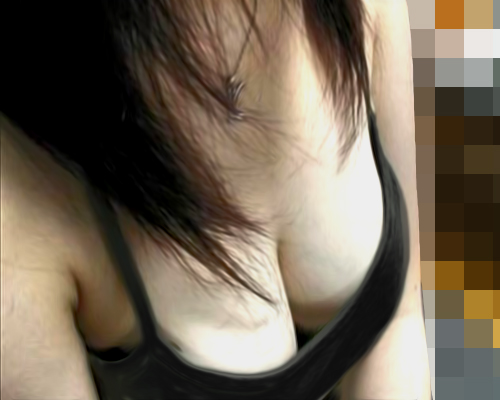
ホテルを出ると、正面玄関の通路で待機していたタクシーに乗り込んだ。例のビジネスホテルの名を告げると、運転手は、「今からだと一時間ぐらいかかりますよ」と言いながらバックミラーで私を見つめ、「電車だったら十五分で着きますけど……」と言った。
いかにも善良そうな運転手だった。五十代半ばだろうか、制帽からはみ出した鬢はほとんど白髪だった。
そんな運転手の、パリッと糊付けされた几帳面なワイシャツの襟を見つめながら、「結構ですよ」と答えると、運転手は「ありがとうございます」と嬉しそうに微笑み、その笑顔のままタクシーを発進させたのだった。
今から一時間かかったとしても、ホテルに到着するのは六時だった。それでも作戦決行までにはまだ六時間もあり、その間、いかにして今の妻の性欲を保っておこうかと考えていた。
とりあえずチェックインし、部屋で有料のアダルトビデオを見せながら、ローターでオナニーでもさせておくか……。
ふとそう思ったが、しかし、それでイキ過ぎて満足されてしまっては元も子もなかった。かといって、何の刺激も与えないまま六時間放置しておくというのは、せっかく苦労して沸かした熱湯をわざわざ冷ましてしまうようなものだった。
(この六時間は、私にとって最も長い六時間になりそうだ……)
その難解さに覚悟しながらぼんやり窓の外を眺めていると、ふと道路の右手に海が見えてきた。
左の座席に座っていた妻に「ほら」と指を差した。妻はゆっくりと身を乗り出しながら窓の外を眺め、「海だね」と呟いた。
私の太ももの上では、前屈みで窓の外を見つめる妻のおっぱいが、まるで水を入れすぎた水風船のようにタプタプと揺れていた。私はそこにソッと手を這わせた。ボテッと垂れる柔肉を手の平で支え、その柔肉のグラムを量るかのように持ち上げたりして弄んだ。
妻は私のその手を振り払おうともせず無言で海を眺めていた。しかし、私の左手が妻の背中へと回り、ワンピースの上からブラのフックを外そうとすると、急に妻は眉を八の字に下げながら、無言でイヤイヤと首を横に振った。
それでも私はブラのフックを外した。そしてワンピースの上からブラの肩紐を下ろそうとすると、慌てて妻が元の位置に戻ろうとしたため、私は妻の腰に腕を回してそれを制止した。
そのまま妻の上半身を膝の上に押さえ込んだ。運転手に聞こえないくらいの小声で「このままジッとしてろ……」と囁くと、妻は小さな溜息と共に力を抜いた。
素早くブラの肩紐を両肩ずらした。腕の関節で止まったブラを強引に抜こうとすると、妻はそんな私の手をソッと振り払い、自分でそれを片方の袖から抜き取った。
素早く上着を捲ると、二つの巨大な柔肉の塊がボテンっと垂れた。ポテンポテンと波打つそれは、中年女独特の柔らかさがあった。まるでスライムのようであり、揉んでいるだけでアドレナリンが放出された。

それを揉みながら、もうすぐこれを見ず知らずの男たちが弄ぶのかと思うと、たちまち激しい嫉妬と興奮に襲われ、途端に目の前がクラクラした。
ポテンっと垂れる生乳を五本の指でムニュっと握った。妻は抵抗することもなく下唇をキュッと噛んだ。
そのまま人差し指を伸ばし乳首をコロコロと転がすと、窓の外を見ていた妻が、途端に「はっ」と息を飲みながら項垂れた。「感じる?」と耳元に囁くと、妻は無言で私の股間に手を伸ばし、既に固くなっている肉棒をギュッと握ったのだった。
すぐ目の前の運転席には、見知らぬ中年男がいた。気がつけば、この狭い空間の中には、私たち夫婦以外に他人男がもう一人いたのだ。
改めてそれに気付いた瞬間、最も長いと思っていたこの六時間が急に短く感じ、これからの一分一秒が大切に思えた。
(今度はこの運転手を、ヘドロに引きずり込むか……)
そう思いながら私は、この中年タクシードライバーのペニスを強引に咥えさせられている妻の悲惨な姿を思い浮かべた。そしてギラギラとした強烈な興奮に胸を締め付けられながら、なぜか無性に可笑しくて堪らなくなったのだった。

(つづく)
《←目次》《22話へ→》
つい数時間前の新幹線の中では、『食べログ』を見ながらあれが食べたいこれが食べたいとはしゃいでいた妻も、今は黙ってそれを食べていた。会話もせず、目を合わせることもなく、二人はこのどこにでもあるサンドイッチを黙々と食べていた。しかもそれは異様にパサパサしており、やたらと喉に詰まるサンドイッチだった。
向かい合って座る妻と私の間には、まるでコールタールのようなドロドロとした重たい空気が漂っていた。それは、単独男とプレイしたラブホから帰る途中の車中の空気によく似ていた。
他人にヤられた妻と、他人にヤらせた夫。他人棒に乱れながら痴態を晒していた妻と、その妻の痴態を見ながら自慰に狂っていた夫。そんな二人が乗り込む車中は、無人のように静まり返り、互いに合わせる顔もなければ、交わす言葉もなかった。
あの時と同じ重たい空気が、今の二人にも漂っていた。
はっきり言って気まずかった。店員のペニスをしゃぶらせている最中は、互いにあれだけ燃え上がっていたのに、その行為後はバケツの水をぶっかけられたように冷め、嫌な気まずさだけがブスブスと燻っていた。
そんな空気の中、アイスティーを一口飲んだ妻が、「パンツ……」とポツリと呟いた。それは、行為後の妻が初めて口にした言葉であり、その時初めて、行為後の妻の顔をまともに見た気がした。
「ああ、そうだったね……」と、慌ててポケットからピンクのパンティーを取り出すと、まるで不正な金を政治家の秘書に渡すかのように、それを机の下からソッと渡した。
てっきりトイレに行くものと思っていたが、しかし妻は、それを受け取るなりその場で素早くそれを履いた。
そのパンティーは他人に嗅がれたものだった。濡れたクロッチを指で弄られたものだった。普段の妻なら、そんなパンツを履く事に抵抗を感じるはずだったが、しかし今の妻はすんなりそれを履いた。
そんな妻を見つめながら、ふと思った。
この女は、ついさっきまで見ず知らずの男の性器を舐めていたのだ。恥垢にまみれ、強烈にイカ臭いペニスを何の抵抗もなくしゃぶり、挙句の果てには、どんな性病が含まれているかもわからないような精液を飲み干したのだ。この女は異常者なのだ。だからそんなパンツでも、この女は何の抵抗もなく履けるのだ……と。
そう思っていると、未だドロドロに濡れている妻の膣に、それがピタリと張り付くシーンが頭に浮かんだ。そのカピカピに乾いていたクロッチに、残り汁がジワジワと染み込み、そこに新たなる卑猥なシミが浮かぶのを想像した。

(恐らく今の妻は、ヤリたくてヤリたくて堪らないはずだ……)
そう思うなり再びムラッと欲情した。私はこの短時間で既に三回も射精していた。しかし異常性欲者の私は、このままここで、妖艶な妻の顔を見ながらペニスをシゴきたいと思うほどに興奮していた。
「あの店員とヤリたかったか?」
そう声を震わせながら妻に聞くと、妻はストローに口をつけながら上目遣いで私を見た。そして白いストローに茶色いアイスティーをスッと走らせると、私の目をジッと見たまま「クスッ」と小さく笑った。
それは、ついさっきまでMだった妻からは想像できないSの微笑みだった。そんな挑発的な微笑みに私は心の臓を抉られた。怒り、悲しみ、絶望、嫉妬。それらが頭の中でドロドロと渦巻き、それと同時に身震いするような性的興奮を覚えた私は、拳が震えるほどに激しく動揺した。
そもそも寝取られ願望者というのは、限りなくSでありながら、果てしなくMだった。最愛の妻を見ず知らずの男に抱かせるというサディズムな凶暴性は、妻のメスの部分を見てみたいというマゾヒズムな被虐性が起源であり、寝取られ願望のある夫というのは、表裏一体化したサドマゾヒズムなのである。
もちろん、それに従う妻も同じだった。他人棒に悶えている時の妻は、その姿を最愛の夫に『見られている』というM的な快楽と、『見せている』というS的な快楽に溺れていた。その二つの快楽を交互に受けながら、それによって異常な性欲を湧き上がらせているのだった。

妻のその小悪魔的な微笑みを見た瞬間、私は凄まじい恐怖に襲われた。店員の肉棒に唇を滑らせていたシーンや、恍惚とした表情で精液を飲んでいたシーンが頭の中を駆け巡り、思わず私は、泣き出したくなるほどの絶望感に襲われた。
もうやめよう、と思った。こんなことを続けていると、今に取り返しのつかないことになってしまうと心底思った。最愛の妻を壊したくない。最愛の妻を失くしたくない。そう焦りながら私は、今すぐ東京に帰ろうと思い、無言でスクっと立ち上がった。
すると、ストローを唇に挟んだままの妻が「ん?」と首を傾げながら私を見上げた。
「もう行くの? まだサンドイッチがこんなに残ってるよ?」
私の絶望感を逆撫でするかのように妻は優しく微笑んだ。妻のその愛らしい顔を見ていると、突然胸底から異様な興奮がムラムラと湧き上がってきた。
(お前はその唇であの薄汚いチンポをしゃぶっていた……チンカスも精液も、そのアイスティーのように飲み込んでしまった……)
膝がガクガクと震えた。目は血走り、奥歯が鳴り、全身の毛穴が開いた。
(もしあの時、私があの場にいなければ、きっとお前はあの店員にヤらせていたはずだ……例えあの店員がそれを拒否したとしても、お前はあいつを床に押し倒し、強引にあいつの上に跨っては、チンポを自分のマンコに入れていただろう……)

その光景を想像すると、半開きの唇からハァハァと荒い息が漏れた。その激しい酸素により、それまで絶望で固まっていた脳が活性化し始め、みるみると感情が蘇ってきた。
「行くぞ」と呟く私は、痛いほどに勃起していた。そのままスタスタと歩き出すと、妻は「もう」と唇を尖らせながら立ち上がり、慌てて伝票を持ってレジに走った。
出口で立ち止まっていた私は、レジでお金を払っている妻を見ていた。レジを打つ男性店員のすぐ目の前で、妻の大きな乳肉がタプタプしていた。それを見ながらズボンのポケットの中に手を入れた。そしてポケットの中から勃起したペニスをギュッと握りしめながら、(あの女を……滅茶苦茶にしてやる……)と呟いた。そんな私の脳は、再びヘドロと化していた。
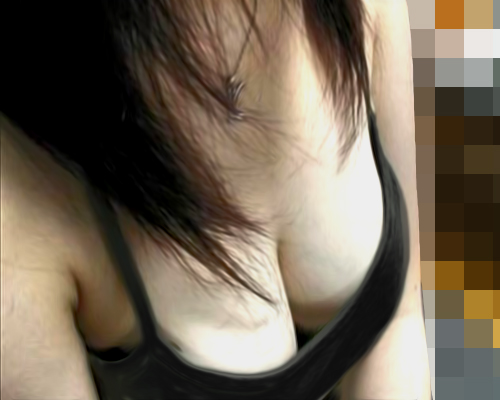
ホテルを出ると、正面玄関の通路で待機していたタクシーに乗り込んだ。例のビジネスホテルの名を告げると、運転手は、「今からだと一時間ぐらいかかりますよ」と言いながらバックミラーで私を見つめ、「電車だったら十五分で着きますけど……」と言った。
いかにも善良そうな運転手だった。五十代半ばだろうか、制帽からはみ出した鬢はほとんど白髪だった。
そんな運転手の、パリッと糊付けされた几帳面なワイシャツの襟を見つめながら、「結構ですよ」と答えると、運転手は「ありがとうございます」と嬉しそうに微笑み、その笑顔のままタクシーを発進させたのだった。
今から一時間かかったとしても、ホテルに到着するのは六時だった。それでも作戦決行までにはまだ六時間もあり、その間、いかにして今の妻の性欲を保っておこうかと考えていた。
とりあえずチェックインし、部屋で有料のアダルトビデオを見せながら、ローターでオナニーでもさせておくか……。
ふとそう思ったが、しかし、それでイキ過ぎて満足されてしまっては元も子もなかった。かといって、何の刺激も与えないまま六時間放置しておくというのは、せっかく苦労して沸かした熱湯をわざわざ冷ましてしまうようなものだった。
(この六時間は、私にとって最も長い六時間になりそうだ……)
その難解さに覚悟しながらぼんやり窓の外を眺めていると、ふと道路の右手に海が見えてきた。
左の座席に座っていた妻に「ほら」と指を差した。妻はゆっくりと身を乗り出しながら窓の外を眺め、「海だね」と呟いた。
私の太ももの上では、前屈みで窓の外を見つめる妻のおっぱいが、まるで水を入れすぎた水風船のようにタプタプと揺れていた。私はそこにソッと手を這わせた。ボテッと垂れる柔肉を手の平で支え、その柔肉のグラムを量るかのように持ち上げたりして弄んだ。
妻は私のその手を振り払おうともせず無言で海を眺めていた。しかし、私の左手が妻の背中へと回り、ワンピースの上からブラのフックを外そうとすると、急に妻は眉を八の字に下げながら、無言でイヤイヤと首を横に振った。
それでも私はブラのフックを外した。そしてワンピースの上からブラの肩紐を下ろそうとすると、慌てて妻が元の位置に戻ろうとしたため、私は妻の腰に腕を回してそれを制止した。
そのまま妻の上半身を膝の上に押さえ込んだ。運転手に聞こえないくらいの小声で「このままジッとしてろ……」と囁くと、妻は小さな溜息と共に力を抜いた。
素早くブラの肩紐を両肩ずらした。腕の関節で止まったブラを強引に抜こうとすると、妻はそんな私の手をソッと振り払い、自分でそれを片方の袖から抜き取った。
素早く上着を捲ると、二つの巨大な柔肉の塊がボテンっと垂れた。ポテンポテンと波打つそれは、中年女独特の柔らかさがあった。まるでスライムのようであり、揉んでいるだけでアドレナリンが放出された。

それを揉みながら、もうすぐこれを見ず知らずの男たちが弄ぶのかと思うと、たちまち激しい嫉妬と興奮に襲われ、途端に目の前がクラクラした。
ポテンっと垂れる生乳を五本の指でムニュっと握った。妻は抵抗することもなく下唇をキュッと噛んだ。
そのまま人差し指を伸ばし乳首をコロコロと転がすと、窓の外を見ていた妻が、途端に「はっ」と息を飲みながら項垂れた。「感じる?」と耳元に囁くと、妻は無言で私の股間に手を伸ばし、既に固くなっている肉棒をギュッと握ったのだった。
すぐ目の前の運転席には、見知らぬ中年男がいた。気がつけば、この狭い空間の中には、私たち夫婦以外に他人男がもう一人いたのだ。
改めてそれに気付いた瞬間、最も長いと思っていたこの六時間が急に短く感じ、これからの一分一秒が大切に思えた。
(今度はこの運転手を、ヘドロに引きずり込むか……)
そう思いながら私は、この中年タクシードライバーのペニスを強引に咥えさせられている妻の悲惨な姿を思い浮かべた。そしてギラギラとした強烈な興奮に胸を締め付けられながら、なぜか無性に可笑しくて堪らなくなったのだった。

(つづく)
《←目次》《22話へ→》
吐泥(へろど)22
2013/06/13 Thu 00:01
さっそく私は、窓一面に映る海を覗き込みながら、「ここは泳げるんですか?」と運転手に話しかけてみた。そう聞きながらもズボンのボタンをソッと外すした。
運転手はバックミラーでチラッと私を見ながら「ここら一帯は海水浴場になってますよ」と、なぜか妙に嬉しそうに答えた。その口ぶりから、なかなかノリの良さそうな親父だと察した。
私は「へぇ〜」と頷きながらトランクスのゴムを剝いだ。それまで押し付けられていたペニスがビンっと跳ね上がり、陰毛の生い茂る下腹部にピタンッと当たった。それは、先日NHKの特集で見た、ユーラシアプレートに沈み込んだフィリピンプレートが跳ね上がって起きる『南海トラフのメカニズム』によく似ていた。
そんなペニスを妻の唇に突きつけてやると、妻は素早くそれを握りしめた。そして我慢汁がダラダラと溢れる尿道を愛おしそうに見つめながら、その弛んだ皮を上下にシコシコと動かし始めた。

太ももから快楽がジンジンと湧き上がってきた。フゥゥゥ……と静かに息を吐きながら妻の髪を優しく撫でていると、再び運転手が私に話しかけてきた。
「シーズンになりますとね、この通りは海水浴に来た客で凄い渋滞ですよ。もうピクリとも車が動かなくなりますからね。だから、私たちタクシードライバーの間ではね、シーズン中のこの通りの事を『天神様の細道』なんて呼んでるんですよ……」
とりあえず、「そうなんだ……」とだけ答えておいた。
正直どうでもよかった。この通りが彼らの間で何と呼ばれているなど全く興味はなく、今はただ妻の愛撫に集中していたかった。だからそのまま話を切ろうとしたのだが、しかし、案の定、運転手は話を続けてきた。バックミラーでチラチラと私を見ながら、まるで、自分しか知らないクイズの答えをコメンテーターに聞き出そうとしている自己欲の強いみのもんたのように、「なぜだと思います?」と聞いてきた。
「知るかボケ!」と怒鳴りたいところだったが、しかし、その瞬間、妻がいきなり亀頭をベロリと舐めた。その快感により私の表情がフッと一瞬緩んだのを運転手はバックミラーで見ていた。だから私は無視できなかった。反論もできなかった。いや、逆にこうやってこの男に話しを続けさせていた方が、妻にスリルを与えられるのではないかと咄嗟に思い、私は顔を緩ませたまま「なぜだろう……わかんないなぁ……教えて下さいよ……」なとど、そのくだらない話に乗ったふりをした。
「ふふふふ。お客さん、通りゃんせ、通りゃんせ、って童謡知ってるでしょ。アレですよアレ。あの歌に『天神様の細道』って出てくるじゃないっすか」
「はぁ……」と私が答える間にも、妻の舌はソフトクリームを舐めるように動き出し、ピチャピチャという湿った音まで鳴らし始めた。

「行きはヨイヨイ、帰りは怖い、っつうね、まさにアレですよ。客を海水浴場まで送ってくのには料金がバンバン跳ね上がるからいいんですけどね、その帰り道は渋滞で身動き取れなくなって時間を無駄にしちゃうでしょ、だからこの通りは、私たちの間では『天神様の細道』なんて呼ばれてるんですわ」
そう運転手がへらへらと笑うと同時に、ペニスは妻の口内にヌルッと滑り込んだ。
妻はそれを咥えたままゆっくりと舌を動かした。尿道やカリ首の裏といった細部にまでその生温い舌を滑らせながら、窄めた唇で竿を上下に摩擦した。

そんな妻の口技は、ペニスだけでなく私の脳までも愛撫していた。思わず顔を顰めて「んふっ……」と息を漏らすと、それをバックミラーで見ていた運転手が、「お客さん?……もしかして車酔いしました?」と心配そうに眉を顰めた。
「いえ……大丈夫です……」と答えながら腰をずらし、慌てて妻の口からペニスを抜いた。この状況でもう少ししゃぶらせていたかったが、しかし、今の私には、このシチュエーションはあまりにも刺激が強すぎたため、ここで果ててしまうのには勿体ないと思い、慌てて妻のそれをやめさせたのだった。
そのまま妻の上半身を起き上がらせると、妻は俯いたまま唇の唾液をそっと拭い、元の座席位置へと戻った。
妻の体が突然ムクリと起き上がったせいか、それをバックミラーで見ていた運転手は、「あれ? 気分が悪いのは奥さんの方でしたか?」と心配そうに聞いてきた。
「ええ。そうなんですよ……妻はすぐに車酔いするんですよ……」
私はそう嘘を吐くと、バックミラーには映らない妻の下半身に手を伸ばし、指を尺取虫のように動かしながらスカートを捲った。真っ白な太ももとピンクのパンティーが、海面に反射して炎のようにメラメラと輝く夕日に照らされた。
妻は一瞬ビクっとしたが、しかし、運転手が後ろに振り向かない限り、そこを彼に見られる事はないと知ると、大胆に股を広げたまま、そのスリリングなプチ露出にドキドキしていた。
そんな事がすぐ真後ろで行われているとは露知らず、運転手は「それじゃあ、もう少しゆっくり走りますね」などと言いながらスピードを緩めた。私はそんな運転手に「すみませんねぇ」と呟きながら、素早くそのピンクのパンティーの中に手を滑り込ませた。いきなり生温い汁が指にネトネトと絡みついてきた。まるで大量の『めかぶ』が流し込まれたかのように、そこは異様なほどに濡れていた。もはやどこがクリトリスで、どこに穴があるのかもわからないくらいヌルヌルしていた。

二本の指を滑り込ませ、熱い穴の中をぐちゃぐちゃと掻き回した。妻は「んん……」と小さく唸りながら私の肩に頬を摺り寄せた。髪から漂う甘いリンスの香りを感じながら妻の耳元にソッと唇を這わせ、「声を出すとバレちゃうよ……」と囁きながらも、声を出せよと言わんばかりにわざと指を激しく動かしてやった。
右手でそうしながら左手でバッグの中を漁った。今こそあれを使うべきだと思いながら必死にそれを探した。
すぐ目の前では、名前も知らない赤の他人がハンドルを握っていた。この男だったら、と思った。「もし気分が悪くなったらコンビニに寄りますので、遠慮なくお申し付けください」などと話しているこの真面目そうな男だったら、きっと従順な性玩具となってくれるはずだと期待しながら、私はバッグの中からピンクローターを摘み出した。
それを妻に見せると、妻は困惑した表情で「音が聞こえちゃうよ……」と慌てた。私は妻のうなじにそっと唇を這わせると、「いいじゃないか、見せてあげよう……」と囁き、拒む妻の手を払い除けながらそれをパンティーの中に入れた。
トロトロに濡れた割れ目にそれを這わした。ツルツルとした丸い表面は面白いようにヌルヌルと滑り、時折それが穴の中にツルンっと滑り込んだりした。その度に妻は太ももをヒクンっと跳ね上げ、必死に私の腕にしがみついていたが、しかし、いよいよその丸い先がクリトリスの上をヌルヌルと滑り始めると、妻は恐怖の表情を浮かべながら私の顔を見上げ、無言で「いや、いや」と首を横に振った。
そんな妻のマゾ顔に激しく欲情しながら、私はもう片方の手でコントローラーを握った。眉を顰めながら必死に懇願する妻を無視し、「運転手さん……」と声を掛けると、その声と同時に妻は股を閉じ、慌ててスカートを直し始めた。
「なんでしょう?」と運転手がバックミラーで私を見た。私は、再びスカートを捲り上げながら、「ほら、言うことを聞きなさい……」と、わざと運転手に聞こえるくらいの声で言いながら、妻の太ももを左足の膝でツンツンと突いた。
「どうかなさいましたか?」
運転手はそう言いながら後ろに振り返ると、ぐったりと項垂れている妻を見て、「大丈夫ですか?」と驚いた。私はそんな運転手の目をジッと見ながら、一気にローターのスイッチを入れた。
妻の股間から振動音が響いた。すかさず運転手の視線が妻の下半身へとサッと下りた。運転手の目が、ピンクのパンティーの中で蠢く私の手を捕らえた。たちまち運転手はその子羊のような目をギョッと見開き、慌てて前に向き直ったのだった。
一瞬にして車内は静まり返った。重たい沈黙の中、電気剃刀のようなヴィィィィィィィィィという振動音だけが不気味に響いていた。
項垂れている妻の耳元に、「見られちゃったよ」囁くと、妻は閉じていた目を更にぎゅっと瞑りながら、迫り来る羞恥と恐怖と快楽に必死に耐えていた。
そんな妻のマゾ心を更に昂ぶらせようと、閉じていた太ももを乱暴に引っ張り、股を逆Y字に開かせた。「パンツのシミが丸見えだよ」と耳元に囁きながら妻の手を握り、その妻の手をパンティーの中に潜らせた。「自分でヤリなさい」とパンティーの中でローターを渡そうとすると、妻は戸惑いながらもそれを受け取り、いつものようにそれを陰核に押し付けた。

「はぁん」という声と共に、妻は背骨を大きく反らした。そしてすぐに腰を引き、再びガクンっと項垂れた。その一瞬の激しい出来事に、慌てて運転手がバックミラーを覗いた。バックミラー越しに運転手と目があった。運転手の目は激しく動揺し、まるでタクシー強盗に後ろから包丁を突きつけられているような恐怖が浮かんでいた。
私はバックミラーに「フッ」と小さく微笑むと、「すみませんね、驚かせちゃって……」と言いながら、ノーブラの大きな胸をダイナミックに揉みしだいた。そして「この女、変態なんですよ」と笑ってやると、運転手は、「あぁ、はい……」と、しどろもどろになりながら、慌ててバックミラーから目を反らした。
私は運転席へと身を乗り出した。シート越しに運転手の耳元に顔を近づけ、「こーいう事したらダメですか?」と聞くと、運転手は人形のようにジッと前を向いたまま、「いえ……」と呟いた。
そんな運転手の顔は顔面神経痛のように引き攣っていた。ハンドルを握る手はブルブルと震えていた。助手席の前にあるネームプレートには『松本和樹』と達筆で書かれていた。そのプレートの上には、『優良運転者』と表示されたカードが刺さっており、そこには『十年間無事故無違反達成』という表彰マークが記されていた。
恐らく彼は、浮気をしたこともなければ、風俗にも行ったことのないような、仕事一筋の真面目な男だった。それは、運転席と助手席の隙間に刺さっている本のタイトルから見てもわかった。普通のタクシーなら、週刊大衆やアサヒ芸能といった下品な週刊誌や、ニッカンや東スポといったスポーツ新聞が刺さっているものだが、しかしそこに刺さっていたのは、『お客様を確実に気分良くさせるための接客術』というハウツー本と、『般若心経から読み取る真心のおもてなし』という単行本だった。
こんな本を読んでいる奴に悪人はいなかった。こんな本を読んでいる奴は風俗などには絶対に行かず、一貫して古女房の股座で性処理しているはずだった。がしかし、その一方で、こんな本を読んでいる奴に限って、一歩道を踏み外すと取り返しがつかないくらいに暴走するものだった。特に性的な問題は、免疫力がない為にブレーキが効かず、一度欲情すると獣の如く手がつけられなくなるものだった。
(こんな真面目な男が、出会い系で知り合った少女を殺しちゃったりするんだろうな……)
そんなことを勝手に想像しながら、私はこの真面目な男に、妻の不真面目な性器を見せてみたいと思った。それは、ウブな少女に卑猥なノーカット動画を見せてみたいという欲求によく似ていた。
ムラムラと興奮を覚えた私は、そのまま手を伸ばして、勝手にバックミラーの角度を変えた。途端に運転手が、「あっ、お客さん、それは——」と、慌ててバックミラーを元の角度に戻そうとしたが、しかし、そこに妻の下半身が映っていることを知ると、運転手は、何かに必死に戸惑いながらもソッと手を下ろした。
そんな運転手の下劣な本能に欲情した私は、黙々とオナニーに耽っている妻のパンティーを一気に膝まで下ろした。一瞬妻は「イヤ……」と呟いたが、しかし、この状況下でオナニーに耽っている妻の脳は、もはや完全にヘドロと化しており、口ではイヤと言いながらも抵抗する気配は微塵もなかった。
渦巻く陰毛の中で、赤く爛れたワレメがテラテラと濡れ輝いていた。それはまるで、腸を抉られた魚の腹のように残酷であり、グロテスクだった。その部分を運転手にも見せたいと思った私は、逆Y字に開いていた妻の足を片方ずつシートの上に持ち上げ、股をM字に開かせた。
その恥ずかしい部分を他人に見られていると意識した妻は、ハァハァと息を荒げ始めた。そしてクリトリスを集中的に攻めながら「見ないで、見ないで」と何度も呟き、自らの意思で更に股を大きく開いた。

そんな妻の乱心する姿を、運転手はバックミラーで見ていた。そこに映る運転手の目には狂気が浮かんでいた。あの羊のように優しかった目は獰猛な狼の目に変わり、今にも襲いかかってきそうな危険な光を帯びていた。
羊の皮を被った狼。こんな男に妻を犯させたいと思った。風俗にも行かなければ、浮気もしない。エロ雑誌も見なければエロ動画も一切見ない。古女房一筋の真面目で誠実なタクシードライバー。そんな男が、他人の妻の裸体に悶え狂っている姿を見てみたいと本気で思った。
私は、妻のワンピースの肩をずらした。大きな乳肉が溢れ、ポテンっと波を打った。妻の手をそこに誘導した。そして妻が自ら乳肉を揉み始めたのを確認すると、運転手の耳元に「私の妻は……露出狂なんです……」と呟いた。
「あぁ、はい……」
そう頷く運転手の耳の裏からは、強烈な加齢臭が漂ってきた。
「妻を……助手席に座らせてもいいですか?……」
そう聞くと、運転手は戸惑いながらも、「はぁ……」と頷いた。
「良かったね……前に座ってもいいってさ」
そう囁くと、妻はその言葉から、今から始まる卑猥な光景を想像したのか、ハァハァという呼吸を荒げた。そして半開きの目で運転席を見つめながら突然乳房を激しく揉み出すと、そのまま全身をヒクヒクさせながらイッてしまったのだった。

(つづく)
《←目次》《23話へ→》
運転手はバックミラーでチラッと私を見ながら「ここら一帯は海水浴場になってますよ」と、なぜか妙に嬉しそうに答えた。その口ぶりから、なかなかノリの良さそうな親父だと察した。
私は「へぇ〜」と頷きながらトランクスのゴムを剝いだ。それまで押し付けられていたペニスがビンっと跳ね上がり、陰毛の生い茂る下腹部にピタンッと当たった。それは、先日NHKの特集で見た、ユーラシアプレートに沈み込んだフィリピンプレートが跳ね上がって起きる『南海トラフのメカニズム』によく似ていた。
そんなペニスを妻の唇に突きつけてやると、妻は素早くそれを握りしめた。そして我慢汁がダラダラと溢れる尿道を愛おしそうに見つめながら、その弛んだ皮を上下にシコシコと動かし始めた。

太ももから快楽がジンジンと湧き上がってきた。フゥゥゥ……と静かに息を吐きながら妻の髪を優しく撫でていると、再び運転手が私に話しかけてきた。
「シーズンになりますとね、この通りは海水浴に来た客で凄い渋滞ですよ。もうピクリとも車が動かなくなりますからね。だから、私たちタクシードライバーの間ではね、シーズン中のこの通りの事を『天神様の細道』なんて呼んでるんですよ……」
とりあえず、「そうなんだ……」とだけ答えておいた。
正直どうでもよかった。この通りが彼らの間で何と呼ばれているなど全く興味はなく、今はただ妻の愛撫に集中していたかった。だからそのまま話を切ろうとしたのだが、しかし、案の定、運転手は話を続けてきた。バックミラーでチラチラと私を見ながら、まるで、自分しか知らないクイズの答えをコメンテーターに聞き出そうとしている自己欲の強いみのもんたのように、「なぜだと思います?」と聞いてきた。
「知るかボケ!」と怒鳴りたいところだったが、しかし、その瞬間、妻がいきなり亀頭をベロリと舐めた。その快感により私の表情がフッと一瞬緩んだのを運転手はバックミラーで見ていた。だから私は無視できなかった。反論もできなかった。いや、逆にこうやってこの男に話しを続けさせていた方が、妻にスリルを与えられるのではないかと咄嗟に思い、私は顔を緩ませたまま「なぜだろう……わかんないなぁ……教えて下さいよ……」なとど、そのくだらない話に乗ったふりをした。
「ふふふふ。お客さん、通りゃんせ、通りゃんせ、って童謡知ってるでしょ。アレですよアレ。あの歌に『天神様の細道』って出てくるじゃないっすか」
「はぁ……」と私が答える間にも、妻の舌はソフトクリームを舐めるように動き出し、ピチャピチャという湿った音まで鳴らし始めた。

「行きはヨイヨイ、帰りは怖い、っつうね、まさにアレですよ。客を海水浴場まで送ってくのには料金がバンバン跳ね上がるからいいんですけどね、その帰り道は渋滞で身動き取れなくなって時間を無駄にしちゃうでしょ、だからこの通りは、私たちの間では『天神様の細道』なんて呼ばれてるんですわ」
そう運転手がへらへらと笑うと同時に、ペニスは妻の口内にヌルッと滑り込んだ。
妻はそれを咥えたままゆっくりと舌を動かした。尿道やカリ首の裏といった細部にまでその生温い舌を滑らせながら、窄めた唇で竿を上下に摩擦した。

そんな妻の口技は、ペニスだけでなく私の脳までも愛撫していた。思わず顔を顰めて「んふっ……」と息を漏らすと、それをバックミラーで見ていた運転手が、「お客さん?……もしかして車酔いしました?」と心配そうに眉を顰めた。
「いえ……大丈夫です……」と答えながら腰をずらし、慌てて妻の口からペニスを抜いた。この状況でもう少ししゃぶらせていたかったが、しかし、今の私には、このシチュエーションはあまりにも刺激が強すぎたため、ここで果ててしまうのには勿体ないと思い、慌てて妻のそれをやめさせたのだった。
そのまま妻の上半身を起き上がらせると、妻は俯いたまま唇の唾液をそっと拭い、元の座席位置へと戻った。
妻の体が突然ムクリと起き上がったせいか、それをバックミラーで見ていた運転手は、「あれ? 気分が悪いのは奥さんの方でしたか?」と心配そうに聞いてきた。
「ええ。そうなんですよ……妻はすぐに車酔いするんですよ……」
私はそう嘘を吐くと、バックミラーには映らない妻の下半身に手を伸ばし、指を尺取虫のように動かしながらスカートを捲った。真っ白な太ももとピンクのパンティーが、海面に反射して炎のようにメラメラと輝く夕日に照らされた。
妻は一瞬ビクっとしたが、しかし、運転手が後ろに振り向かない限り、そこを彼に見られる事はないと知ると、大胆に股を広げたまま、そのスリリングなプチ露出にドキドキしていた。
そんな事がすぐ真後ろで行われているとは露知らず、運転手は「それじゃあ、もう少しゆっくり走りますね」などと言いながらスピードを緩めた。私はそんな運転手に「すみませんねぇ」と呟きながら、素早くそのピンクのパンティーの中に手を滑り込ませた。いきなり生温い汁が指にネトネトと絡みついてきた。まるで大量の『めかぶ』が流し込まれたかのように、そこは異様なほどに濡れていた。もはやどこがクリトリスで、どこに穴があるのかもわからないくらいヌルヌルしていた。

二本の指を滑り込ませ、熱い穴の中をぐちゃぐちゃと掻き回した。妻は「んん……」と小さく唸りながら私の肩に頬を摺り寄せた。髪から漂う甘いリンスの香りを感じながら妻の耳元にソッと唇を這わせ、「声を出すとバレちゃうよ……」と囁きながらも、声を出せよと言わんばかりにわざと指を激しく動かしてやった。
右手でそうしながら左手でバッグの中を漁った。今こそあれを使うべきだと思いながら必死にそれを探した。
すぐ目の前では、名前も知らない赤の他人がハンドルを握っていた。この男だったら、と思った。「もし気分が悪くなったらコンビニに寄りますので、遠慮なくお申し付けください」などと話しているこの真面目そうな男だったら、きっと従順な性玩具となってくれるはずだと期待しながら、私はバッグの中からピンクローターを摘み出した。
それを妻に見せると、妻は困惑した表情で「音が聞こえちゃうよ……」と慌てた。私は妻のうなじにそっと唇を這わせると、「いいじゃないか、見せてあげよう……」と囁き、拒む妻の手を払い除けながらそれをパンティーの中に入れた。
トロトロに濡れた割れ目にそれを這わした。ツルツルとした丸い表面は面白いようにヌルヌルと滑り、時折それが穴の中にツルンっと滑り込んだりした。その度に妻は太ももをヒクンっと跳ね上げ、必死に私の腕にしがみついていたが、しかし、いよいよその丸い先がクリトリスの上をヌルヌルと滑り始めると、妻は恐怖の表情を浮かべながら私の顔を見上げ、無言で「いや、いや」と首を横に振った。
そんな妻のマゾ顔に激しく欲情しながら、私はもう片方の手でコントローラーを握った。眉を顰めながら必死に懇願する妻を無視し、「運転手さん……」と声を掛けると、その声と同時に妻は股を閉じ、慌ててスカートを直し始めた。
「なんでしょう?」と運転手がバックミラーで私を見た。私は、再びスカートを捲り上げながら、「ほら、言うことを聞きなさい……」と、わざと運転手に聞こえるくらいの声で言いながら、妻の太ももを左足の膝でツンツンと突いた。
「どうかなさいましたか?」
運転手はそう言いながら後ろに振り返ると、ぐったりと項垂れている妻を見て、「大丈夫ですか?」と驚いた。私はそんな運転手の目をジッと見ながら、一気にローターのスイッチを入れた。
妻の股間から振動音が響いた。すかさず運転手の視線が妻の下半身へとサッと下りた。運転手の目が、ピンクのパンティーの中で蠢く私の手を捕らえた。たちまち運転手はその子羊のような目をギョッと見開き、慌てて前に向き直ったのだった。
一瞬にして車内は静まり返った。重たい沈黙の中、電気剃刀のようなヴィィィィィィィィィという振動音だけが不気味に響いていた。
項垂れている妻の耳元に、「見られちゃったよ」囁くと、妻は閉じていた目を更にぎゅっと瞑りながら、迫り来る羞恥と恐怖と快楽に必死に耐えていた。
そんな妻のマゾ心を更に昂ぶらせようと、閉じていた太ももを乱暴に引っ張り、股を逆Y字に開かせた。「パンツのシミが丸見えだよ」と耳元に囁きながら妻の手を握り、その妻の手をパンティーの中に潜らせた。「自分でヤリなさい」とパンティーの中でローターを渡そうとすると、妻は戸惑いながらもそれを受け取り、いつものようにそれを陰核に押し付けた。

「はぁん」という声と共に、妻は背骨を大きく反らした。そしてすぐに腰を引き、再びガクンっと項垂れた。その一瞬の激しい出来事に、慌てて運転手がバックミラーを覗いた。バックミラー越しに運転手と目があった。運転手の目は激しく動揺し、まるでタクシー強盗に後ろから包丁を突きつけられているような恐怖が浮かんでいた。
私はバックミラーに「フッ」と小さく微笑むと、「すみませんね、驚かせちゃって……」と言いながら、ノーブラの大きな胸をダイナミックに揉みしだいた。そして「この女、変態なんですよ」と笑ってやると、運転手は、「あぁ、はい……」と、しどろもどろになりながら、慌ててバックミラーから目を反らした。
私は運転席へと身を乗り出した。シート越しに運転手の耳元に顔を近づけ、「こーいう事したらダメですか?」と聞くと、運転手は人形のようにジッと前を向いたまま、「いえ……」と呟いた。
そんな運転手の顔は顔面神経痛のように引き攣っていた。ハンドルを握る手はブルブルと震えていた。助手席の前にあるネームプレートには『松本和樹』と達筆で書かれていた。そのプレートの上には、『優良運転者』と表示されたカードが刺さっており、そこには『十年間無事故無違反達成』という表彰マークが記されていた。
恐らく彼は、浮気をしたこともなければ、風俗にも行ったことのないような、仕事一筋の真面目な男だった。それは、運転席と助手席の隙間に刺さっている本のタイトルから見てもわかった。普通のタクシーなら、週刊大衆やアサヒ芸能といった下品な週刊誌や、ニッカンや東スポといったスポーツ新聞が刺さっているものだが、しかしそこに刺さっていたのは、『お客様を確実に気分良くさせるための接客術』というハウツー本と、『般若心経から読み取る真心のおもてなし』という単行本だった。
こんな本を読んでいる奴に悪人はいなかった。こんな本を読んでいる奴は風俗などには絶対に行かず、一貫して古女房の股座で性処理しているはずだった。がしかし、その一方で、こんな本を読んでいる奴に限って、一歩道を踏み外すと取り返しがつかないくらいに暴走するものだった。特に性的な問題は、免疫力がない為にブレーキが効かず、一度欲情すると獣の如く手がつけられなくなるものだった。
(こんな真面目な男が、出会い系で知り合った少女を殺しちゃったりするんだろうな……)
そんなことを勝手に想像しながら、私はこの真面目な男に、妻の不真面目な性器を見せてみたいと思った。それは、ウブな少女に卑猥なノーカット動画を見せてみたいという欲求によく似ていた。
ムラムラと興奮を覚えた私は、そのまま手を伸ばして、勝手にバックミラーの角度を変えた。途端に運転手が、「あっ、お客さん、それは——」と、慌ててバックミラーを元の角度に戻そうとしたが、しかし、そこに妻の下半身が映っていることを知ると、運転手は、何かに必死に戸惑いながらもソッと手を下ろした。
そんな運転手の下劣な本能に欲情した私は、黙々とオナニーに耽っている妻のパンティーを一気に膝まで下ろした。一瞬妻は「イヤ……」と呟いたが、しかし、この状況下でオナニーに耽っている妻の脳は、もはや完全にヘドロと化しており、口ではイヤと言いながらも抵抗する気配は微塵もなかった。
渦巻く陰毛の中で、赤く爛れたワレメがテラテラと濡れ輝いていた。それはまるで、腸を抉られた魚の腹のように残酷であり、グロテスクだった。その部分を運転手にも見せたいと思った私は、逆Y字に開いていた妻の足を片方ずつシートの上に持ち上げ、股をM字に開かせた。
その恥ずかしい部分を他人に見られていると意識した妻は、ハァハァと息を荒げ始めた。そしてクリトリスを集中的に攻めながら「見ないで、見ないで」と何度も呟き、自らの意思で更に股を大きく開いた。

そんな妻の乱心する姿を、運転手はバックミラーで見ていた。そこに映る運転手の目には狂気が浮かんでいた。あの羊のように優しかった目は獰猛な狼の目に変わり、今にも襲いかかってきそうな危険な光を帯びていた。
羊の皮を被った狼。こんな男に妻を犯させたいと思った。風俗にも行かなければ、浮気もしない。エロ雑誌も見なければエロ動画も一切見ない。古女房一筋の真面目で誠実なタクシードライバー。そんな男が、他人の妻の裸体に悶え狂っている姿を見てみたいと本気で思った。
私は、妻のワンピースの肩をずらした。大きな乳肉が溢れ、ポテンっと波を打った。妻の手をそこに誘導した。そして妻が自ら乳肉を揉み始めたのを確認すると、運転手の耳元に「私の妻は……露出狂なんです……」と呟いた。
「あぁ、はい……」
そう頷く運転手の耳の裏からは、強烈な加齢臭が漂ってきた。
「妻を……助手席に座らせてもいいですか?……」
そう聞くと、運転手は戸惑いながらも、「はぁ……」と頷いた。
「良かったね……前に座ってもいいってさ」
そう囁くと、妻はその言葉から、今から始まる卑猥な光景を想像したのか、ハァハァという呼吸を荒げた。そして半開きの目で運転席を見つめながら突然乳房を激しく揉み出すと、そのまま全身をヒクヒクさせながらイッてしまったのだった。

(つづく)
《←目次》《23話へ→》
吐泥(へろど)23
2013/06/13 Thu 00:01
シーサイドラインと呼ばれる国道を延々と進んでいた。窓の外にはひたすら海が続き、既に日が暮れた日本海は漆黒の闇と化していた。
妻は助手席に座っていた。まるで護送される囚人のようにぐったりと項垂れている。
私は後部座席から、「股を開きなさい……」と耳元に囁いた。しばらく黙ったまま項垂れていた妻だったが、しかし私が何度もそう囁きながらワンピースの肩をずらし、真っ白な乳肉をそこにタポンっと溢れさせると、やっと観念したのか、妻は股をゆっくりと開き始めた。
後部座席から手を伸ばし、曝け出された柔肉をタプタプと揺らした。妻は「いや……」と小さく呟きながら、私のその手の動きを止めようとした。すかさず私は、指先で乳首を転がした。そして、「ほら、いつもみたいに自分でコリコリとやってごらんよ……」と囁きながら妻の手を柔肉の上にソッと乗せた。
すると妻は、更に「いや……」と呟きながらも、その指を恐る恐る乳首に伸ばした。そしてその硬くなった乳首をコリコリと転がしながら、自らの意思でもう片方の手をパンティーの中に滑り込ませ、そこでも指をクネクネと動かし始めたのだった。

んふっ……んふっ……んふっ……。
そんな妻の鼻息が、静まり返った車内に響いていた。後部座席から運転手の横顔をソッと覗き込み、「どうです……凄い変態でしょ……」と笑うと、運転手は横目でチラッと妻を見ながら、「はぁ……」と小さく頷いた。
そんな運転手は、明らかに怯えていた。当然、こんな客は初めてだろうし、恐らく、今までに他人女のリアルなオナニーなど一度も見た事はないはずだった。だからこの男は怯え、そして狼狽えているのだろうが、しかし、精神的にそうであっても肉体的には違うようだった。それは、彼のその痛々しいほどに膨らんでいる股間を見れば一目瞭然だった。
「この女はね、見られることが嬉しいんですよ。自分の恥ずかしい姿を他人に見られることにね、喜びを感じる変態なんですよ。だから見てやって下さいよ……私の妻の気分を、確実に良くさせてやって下さいよ……」
私はそう言いながら、助手席と運転席の隙間に刺さっていた、『お客様を確実に気分良くさせるための接客術』を抜き取り、それを運転手にチラチラと見せながら笑った。
暫くすると長いトンネルに突入した。入り口の壁には、『出口まで約8分』という看板が表示されていた。今までも度々トンネルに出くわしたが、しかし、どれも一瞬で脱出してしまうほどの短いものばかりだった。
私は、この長い闇に乗じることにした。車内が薄暗ければ、妻もこの男ももっと大胆になれると思ったのだ。
さっそく助手席に両手を伸ばし、ワンピースの胸元を大きく開かせた。まるでダムの決壊のように巨大な乳肉が溢れ出し、解放された二つの柔肉がタプタプと交互に揺れた。
その乳肉を背後からムニムニと揉みしだきながら、妻の耳元に「パンツを脱ぎなさい」と囁いた。トンネルの闇がそうさせているのか、妻はまるで催眠術にかけられたかのように素直に従い、それを足首までスルスルと下ろした。
「シートに両足を乗せて、股をM字に開くんだ……」
私はそう囁きながら二つの乳首を両指でコリコリと転がした。すると妻がゆっくりと顔を上げ、そっと私の耳元に唇を近づけた。
「ローター……頂戴……」
妻の甘い囁き声と生暖かい息が私の脳をくすぐった。この状況でそれを求める妻の変態性に強烈な興奮を覚えた私は、脳をクラクラさせながら妻の唇の中に舌を押し込んだ。
激しく絡み合う互いの舌が、ベプ……ペプ……と音を立てた。そのまま乳首を思い切り摘むと、妻は私の口内で「ング……ング……」と唸り声をあげた。そうしながら横目で運転手を見ると、運転手はそっと前屈みになりながら妻の股を覗き込んでいた。ふと見ると、いつの間にか妻は股をM字に開いていた。
それを見た私は、バンジージャンプを跳んだ瞬間のような衝撃を受けた。こっそり陰部を男に見せつけていた妻に激しい嫉妬を感じ、そして、どさくさに紛れて、他人の妻の陰部を覗き込んでいるその男の卑しい根性に、激しい怒りを覚えた。
自ら『見てくれ』と頼みながらも、しかし、いざ本当に見られると激しい怒りを感じるというのが、寝取られ願望者特有の複雑な精神構造だった。そんな怒りは、次第に焦りへと変わり、それが、嫉妬、悲しみ、怯え、絶望、と変化しながら、最終的に快楽へと昇りつめていくというから、これは、一般人では到底理解できない精神構造だった。
そんな異常者である私は、嫉妬と怒りで脳をクラクラさせながら妻の唇から乱暴に舌を抜いた。ローターを頂戴とせがむ妻を無視し、いきなりハンドルを握っている運転手の左手首をガッと掴んだ。
「わっ、お客さん! 危ないです!」
そう慌てる運転手に、「あんた、今、私の妻のオマンコをこっそり見てたでしょ」と聞いた。運転手はそれに答えず、ただひたすらに「危ないですから離して下さい!」と焦っていた。
「こっそり見なくたっていいじゃないですか……こっちは最初から見てやってくれって頼んでるんですから、堂々と見てもらって構わないんですよ……」
「わかりましたから、危ないですからとにかく手を離して下さい!」
「いや、あなたこそ、その手をハンドルから離して下さいよ……」
「……えっ?」
「見るだけじゃなくて……触ってやってくださいよ……」
そう不敵に笑うと、運転手はそれ以上何も言わず、トンネルの闇をジッと見つめたままゴクリと唾を飲み込んだ。
一瞬の沈黙が流れた。沈黙の中、ハンドルを握る運転手の左手から力が抜けていくのがわかった。
私はその手を静かにハンドルから外した。運転手は、何の抵抗もする事なく、黙ってそれに従った。その手を妻の股間へと持って行くと、それまで半開きだった妻の股が大きくM字に開いた。それは、妻自らの意思だった。妻は、まさに早く触ってと言わんばかりに性器を突き出しており、途端に私は激しい嫉妬に襲われたのだった。

クチャ……クチャ……クチャ……。そんな卑猥な音が微かに響いていた。
運転手の指は、戸惑いながらも確実に穴を捕らえていた。トンネルの闇をジッと見つめながらも、そこから溢れる汁に指をヌルヌルと滑らせていた。
妻は完全無抵抗で陰部を剥き出しながら、まるで高熱で魘されているかのようにハァハァと荒い息を吐いていた。時折、蠢く運転手の指先がクリトリスに触れると、突然赤ちゃんの泣き声のような声を出しては、腰をヒクン、ヒクン、と痙攣させていた。
そんな二人を後部座席から見ていた私は、今までにない強烈な嫉妬に襲われていた。それは、この時の妻があまりにも積極的すぎたからだった。今までのように、嫌がりながらも行為に及ぶという感じではなく、今は、自らそうして下さいと言わんばかりに大胆なのだ。しかも妻は、異常なほどに感じていた。ローターも使わず、指だけでここまで感じている妻など今までに見たことがないのだ。
(こんな加齢臭漂う汚いオヤジに……どうしてこんなに感じているんだ……)
そうギリギリと歯軋りをしながら私は嫉妬に燃えていた。こんな状態なら、妻はすんなりこの男のペニスを受け入れるはずだ。路肩に車を止め、運転席に座る男の膝の上に乗れと命令すれば、きっと今の妻なら喜んでそうするはずだと思った。
そう思っていると、不意に、騎乗位で腰を振っている妻の姿が頭に浮かんだ。そして同時に、妻の尻をペシペシと叩きながら「うぅぅぅぅ」と唸っている運転手の表情までもが鮮明に浮かんできた。

ヘドロのような妄想の中では、運転手のペニスが妻の尻の谷間をズボズボとピストンしていた。目を閉じながら喘いでいる妻は、そのコリコリとした肉棒の感触を必死に味わっているようであり、その乱れ方はもはや淫乱そのものだった。
妄想の中の運転手は、上下に動く妻の大きな胸に顔を埋めながら、「お客さん……イキそうです!」と唸った。妻は、運転手の加齢臭漂う耳元にソッと唇を寄せると、「中で出して……」と囁き、そしてその耳たぶをペロッと舐めた。すかさず運転手が「うっ!」と呻きながら体を硬直させた。妻はその体にしがみつきながら狂ったように腰を振りまくった。そして妻は、射精中の男の唇の中に自ら舌を押し込みながら、自身も快楽の渦に巻かれていったのだった……。
そんな妄想を一人黙々と繰り広げ、息ができないくらいに嫉妬に胸を締め付けられていた。頭をクラクラさせながらも現実に戻り、ソッと助手席を覗いてみると、いつの間にか、運転手の指はクリトリスから穴へと移動していた。
ピンクの粘膜を剥き出しにされた穴の中を、テラテラと濡れ輝く二本の指が行ったり来たりと繰り返していた。年季の入った皺だらけの指に、どす黒い小陰唇がヌルヌルと絡みついていた。
その指の動きは貪欲だった。まるで場末のピンサロで、安サラリーマンが料金分触らなければ損だとばかりにピンサロ嬢の体を触りまくっているような、そんな必死さが感じられた。
(この男……相当溜まっているな……)
そう思った私は、もはやこの男は私の性奴隷と化したと確信した。さっそく背後から運転手の耳元に顔を寄せ、まるで暗示をかけるような口調で、「チンポを出してください……」と囁いた。「えっ」と一瞬振り向きかけた運転手は、顔を横に向けたまま横目で前を見つめ、「今……ですか?」と声を震わせた。
「今です……そのままズボンを下げて、そのビンビンに勃起しているチンポを妻に見せてやって下さい……」
運転手は絶句したまま困惑していたが、しかし、暫くすると陰部からヌルリと指を抜き、そのテラテラと輝く指でズボンのベルトを外し始めた。
ベルトの金具がカチャカチャと鳴るのを、妻はハァハァと胸を上下させながら横目でジッと見ていた。妻のその目は明らかに異常をきたしており、それは欲情している時の私の目と同じだった。
ベルトを外した運転手は、恐る恐るシートに腰を浮かせながらズボンとトランクスを同時に下ろし始めた。ズボンが太ももの上をスルッと通過すると、痛々しいまでに勃起した肉棒がビンっと跳ね上がった。

肉棒には無数の血管が絡まっていた。獰猛な爬虫類のような亀頭からはヘドロのような汁がダラダラと溢れ、それがゴツゴツとした肉棒に垂れてはテラテラと怪しく輝いていた。
特に巨大というわけではないが、その肉の棒は凄まじいパワーに満ち溢れていた。ちょっとでも触れれば、すぐにでも爆発しそうな一触即発の気を発していた。
ソッと妻の顔を見ると、妻はムラムラとした目でソレを見つめながら割れ目に指を滑らせていた。そんな妻の耳元に「シコシコしてあげなさい……」と囁いてやると、妻はそれをリアルに想像して欲情したのか、「はぁぁぁぁ……」と大きな息を吐きながら、自分の穴の中を指で掻き回し始めたのだった。

(つづく)
《←目次》《24話へ→》
妻は助手席に座っていた。まるで護送される囚人のようにぐったりと項垂れている。
私は後部座席から、「股を開きなさい……」と耳元に囁いた。しばらく黙ったまま項垂れていた妻だったが、しかし私が何度もそう囁きながらワンピースの肩をずらし、真っ白な乳肉をそこにタポンっと溢れさせると、やっと観念したのか、妻は股をゆっくりと開き始めた。
後部座席から手を伸ばし、曝け出された柔肉をタプタプと揺らした。妻は「いや……」と小さく呟きながら、私のその手の動きを止めようとした。すかさず私は、指先で乳首を転がした。そして、「ほら、いつもみたいに自分でコリコリとやってごらんよ……」と囁きながら妻の手を柔肉の上にソッと乗せた。
すると妻は、更に「いや……」と呟きながらも、その指を恐る恐る乳首に伸ばした。そしてその硬くなった乳首をコリコリと転がしながら、自らの意思でもう片方の手をパンティーの中に滑り込ませ、そこでも指をクネクネと動かし始めたのだった。

んふっ……んふっ……んふっ……。
そんな妻の鼻息が、静まり返った車内に響いていた。後部座席から運転手の横顔をソッと覗き込み、「どうです……凄い変態でしょ……」と笑うと、運転手は横目でチラッと妻を見ながら、「はぁ……」と小さく頷いた。
そんな運転手は、明らかに怯えていた。当然、こんな客は初めてだろうし、恐らく、今までに他人女のリアルなオナニーなど一度も見た事はないはずだった。だからこの男は怯え、そして狼狽えているのだろうが、しかし、精神的にそうであっても肉体的には違うようだった。それは、彼のその痛々しいほどに膨らんでいる股間を見れば一目瞭然だった。
「この女はね、見られることが嬉しいんですよ。自分の恥ずかしい姿を他人に見られることにね、喜びを感じる変態なんですよ。だから見てやって下さいよ……私の妻の気分を、確実に良くさせてやって下さいよ……」
私はそう言いながら、助手席と運転席の隙間に刺さっていた、『お客様を確実に気分良くさせるための接客術』を抜き取り、それを運転手にチラチラと見せながら笑った。
暫くすると長いトンネルに突入した。入り口の壁には、『出口まで約8分』という看板が表示されていた。今までも度々トンネルに出くわしたが、しかし、どれも一瞬で脱出してしまうほどの短いものばかりだった。
私は、この長い闇に乗じることにした。車内が薄暗ければ、妻もこの男ももっと大胆になれると思ったのだ。
さっそく助手席に両手を伸ばし、ワンピースの胸元を大きく開かせた。まるでダムの決壊のように巨大な乳肉が溢れ出し、解放された二つの柔肉がタプタプと交互に揺れた。
その乳肉を背後からムニムニと揉みしだきながら、妻の耳元に「パンツを脱ぎなさい」と囁いた。トンネルの闇がそうさせているのか、妻はまるで催眠術にかけられたかのように素直に従い、それを足首までスルスルと下ろした。
「シートに両足を乗せて、股をM字に開くんだ……」
私はそう囁きながら二つの乳首を両指でコリコリと転がした。すると妻がゆっくりと顔を上げ、そっと私の耳元に唇を近づけた。
「ローター……頂戴……」
妻の甘い囁き声と生暖かい息が私の脳をくすぐった。この状況でそれを求める妻の変態性に強烈な興奮を覚えた私は、脳をクラクラさせながら妻の唇の中に舌を押し込んだ。
激しく絡み合う互いの舌が、ベプ……ペプ……と音を立てた。そのまま乳首を思い切り摘むと、妻は私の口内で「ング……ング……」と唸り声をあげた。そうしながら横目で運転手を見ると、運転手はそっと前屈みになりながら妻の股を覗き込んでいた。ふと見ると、いつの間にか妻は股をM字に開いていた。
それを見た私は、バンジージャンプを跳んだ瞬間のような衝撃を受けた。こっそり陰部を男に見せつけていた妻に激しい嫉妬を感じ、そして、どさくさに紛れて、他人の妻の陰部を覗き込んでいるその男の卑しい根性に、激しい怒りを覚えた。
自ら『見てくれ』と頼みながらも、しかし、いざ本当に見られると激しい怒りを感じるというのが、寝取られ願望者特有の複雑な精神構造だった。そんな怒りは、次第に焦りへと変わり、それが、嫉妬、悲しみ、怯え、絶望、と変化しながら、最終的に快楽へと昇りつめていくというから、これは、一般人では到底理解できない精神構造だった。
そんな異常者である私は、嫉妬と怒りで脳をクラクラさせながら妻の唇から乱暴に舌を抜いた。ローターを頂戴とせがむ妻を無視し、いきなりハンドルを握っている運転手の左手首をガッと掴んだ。
「わっ、お客さん! 危ないです!」
そう慌てる運転手に、「あんた、今、私の妻のオマンコをこっそり見てたでしょ」と聞いた。運転手はそれに答えず、ただひたすらに「危ないですから離して下さい!」と焦っていた。
「こっそり見なくたっていいじゃないですか……こっちは最初から見てやってくれって頼んでるんですから、堂々と見てもらって構わないんですよ……」
「わかりましたから、危ないですからとにかく手を離して下さい!」
「いや、あなたこそ、その手をハンドルから離して下さいよ……」
「……えっ?」
「見るだけじゃなくて……触ってやってくださいよ……」
そう不敵に笑うと、運転手はそれ以上何も言わず、トンネルの闇をジッと見つめたままゴクリと唾を飲み込んだ。
一瞬の沈黙が流れた。沈黙の中、ハンドルを握る運転手の左手から力が抜けていくのがわかった。
私はその手を静かにハンドルから外した。運転手は、何の抵抗もする事なく、黙ってそれに従った。その手を妻の股間へと持って行くと、それまで半開きだった妻の股が大きくM字に開いた。それは、妻自らの意思だった。妻は、まさに早く触ってと言わんばかりに性器を突き出しており、途端に私は激しい嫉妬に襲われたのだった。

クチャ……クチャ……クチャ……。そんな卑猥な音が微かに響いていた。
運転手の指は、戸惑いながらも確実に穴を捕らえていた。トンネルの闇をジッと見つめながらも、そこから溢れる汁に指をヌルヌルと滑らせていた。
妻は完全無抵抗で陰部を剥き出しながら、まるで高熱で魘されているかのようにハァハァと荒い息を吐いていた。時折、蠢く運転手の指先がクリトリスに触れると、突然赤ちゃんの泣き声のような声を出しては、腰をヒクン、ヒクン、と痙攣させていた。
そんな二人を後部座席から見ていた私は、今までにない強烈な嫉妬に襲われていた。それは、この時の妻があまりにも積極的すぎたからだった。今までのように、嫌がりながらも行為に及ぶという感じではなく、今は、自らそうして下さいと言わんばかりに大胆なのだ。しかも妻は、異常なほどに感じていた。ローターも使わず、指だけでここまで感じている妻など今までに見たことがないのだ。
(こんな加齢臭漂う汚いオヤジに……どうしてこんなに感じているんだ……)
そうギリギリと歯軋りをしながら私は嫉妬に燃えていた。こんな状態なら、妻はすんなりこの男のペニスを受け入れるはずだ。路肩に車を止め、運転席に座る男の膝の上に乗れと命令すれば、きっと今の妻なら喜んでそうするはずだと思った。
そう思っていると、不意に、騎乗位で腰を振っている妻の姿が頭に浮かんだ。そして同時に、妻の尻をペシペシと叩きながら「うぅぅぅぅ」と唸っている運転手の表情までもが鮮明に浮かんできた。

ヘドロのような妄想の中では、運転手のペニスが妻の尻の谷間をズボズボとピストンしていた。目を閉じながら喘いでいる妻は、そのコリコリとした肉棒の感触を必死に味わっているようであり、その乱れ方はもはや淫乱そのものだった。
妄想の中の運転手は、上下に動く妻の大きな胸に顔を埋めながら、「お客さん……イキそうです!」と唸った。妻は、運転手の加齢臭漂う耳元にソッと唇を寄せると、「中で出して……」と囁き、そしてその耳たぶをペロッと舐めた。すかさず運転手が「うっ!」と呻きながら体を硬直させた。妻はその体にしがみつきながら狂ったように腰を振りまくった。そして妻は、射精中の男の唇の中に自ら舌を押し込みながら、自身も快楽の渦に巻かれていったのだった……。
そんな妄想を一人黙々と繰り広げ、息ができないくらいに嫉妬に胸を締め付けられていた。頭をクラクラさせながらも現実に戻り、ソッと助手席を覗いてみると、いつの間にか、運転手の指はクリトリスから穴へと移動していた。
ピンクの粘膜を剥き出しにされた穴の中を、テラテラと濡れ輝く二本の指が行ったり来たりと繰り返していた。年季の入った皺だらけの指に、どす黒い小陰唇がヌルヌルと絡みついていた。
その指の動きは貪欲だった。まるで場末のピンサロで、安サラリーマンが料金分触らなければ損だとばかりにピンサロ嬢の体を触りまくっているような、そんな必死さが感じられた。
(この男……相当溜まっているな……)
そう思った私は、もはやこの男は私の性奴隷と化したと確信した。さっそく背後から運転手の耳元に顔を寄せ、まるで暗示をかけるような口調で、「チンポを出してください……」と囁いた。「えっ」と一瞬振り向きかけた運転手は、顔を横に向けたまま横目で前を見つめ、「今……ですか?」と声を震わせた。
「今です……そのままズボンを下げて、そのビンビンに勃起しているチンポを妻に見せてやって下さい……」
運転手は絶句したまま困惑していたが、しかし、暫くすると陰部からヌルリと指を抜き、そのテラテラと輝く指でズボンのベルトを外し始めた。
ベルトの金具がカチャカチャと鳴るのを、妻はハァハァと胸を上下させながら横目でジッと見ていた。妻のその目は明らかに異常をきたしており、それは欲情している時の私の目と同じだった。
ベルトを外した運転手は、恐る恐るシートに腰を浮かせながらズボンとトランクスを同時に下ろし始めた。ズボンが太ももの上をスルッと通過すると、痛々しいまでに勃起した肉棒がビンっと跳ね上がった。

肉棒には無数の血管が絡まっていた。獰猛な爬虫類のような亀頭からはヘドロのような汁がダラダラと溢れ、それがゴツゴツとした肉棒に垂れてはテラテラと怪しく輝いていた。
特に巨大というわけではないが、その肉の棒は凄まじいパワーに満ち溢れていた。ちょっとでも触れれば、すぐにでも爆発しそうな一触即発の気を発していた。
ソッと妻の顔を見ると、妻はムラムラとした目でソレを見つめながら割れ目に指を滑らせていた。そんな妻の耳元に「シコシコしてあげなさい……」と囁いてやると、妻はそれをリアルに想像して欲情したのか、「はぁぁぁぁ……」と大きな息を吐きながら、自分の穴の中を指で掻き回し始めたのだった。

(つづく)
《←目次》《24話へ→》





