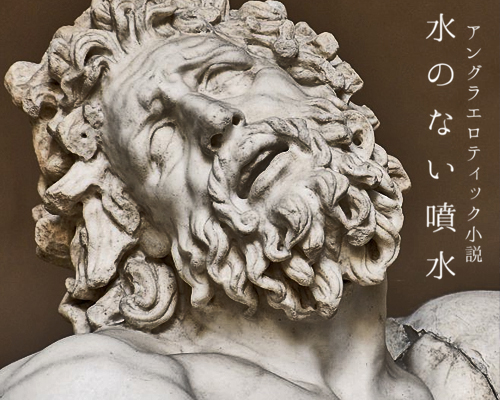水のない噴水2
2012/11/17 Sat 04:26
「はいもう一枚、はいもう一枚、はい、そのまま動かずに目線だけをカメラに……はいOKでぇす」
カメラマンのOKと共にボンっと照明が落とされた。
一斉にスタジオ内が動きだし、イージーホワイトのスクリーンに囲まれていた涼子は一人ポツンと取り残された。
カメラマンとADが小さなモニターを覗き込みながら、数百枚撮った画像を高速でプレビューしていた。
真夏のファーダウンジャケットはさすがに辛かった。スタジオ内は冷凍庫のようにクーラーが効いていたが、しかし、これだけの照明に照らされていては何の役にも立たなかった。
そんな涼子を見かねて、馴染みのADが扇風機を持って来てくれたが、しかし、涼子はそれを辞退した。ここで扇風機に吹かれるとヘアースタイルもジャケットのファーも乱れてしまう。もし、撮り直しという事になれば、また最初から全てセットし直さなくてはならなくなるのだ。
するとADは、扇風機の代わりに冷却スプレーを持って来てくれた。涼子は満面の笑みを浮かべながらそれを受け取ると、ジャケットの下から手を突っ込み、商品を汚さないようスプレーの先をTシャツの中に向けながら噴射したのだった。
しばらくすると、涼子が所属するモデル事務所の専務がニヤニヤと笑いながらやってきた。
「外は三十度超えてるってさ」
専務はそう言いながら、ミントの香りが充満しているステージに上がって来た。
「ここ暑いねぇ……」
専務は驚きながらステージを見回した。メインの照明は落とされていても、四方を囲むハロゲンは猛烈な熱気を発しながら爛々と輝いたままなのだ。
専務は、一気に噴き出した額の汗を手の甲で拭き取りながら、「いよいよRinちゃんにもいい仕事が回って来たようだよ」と自慢げに笑った。Rinというのは涼子の芸名だ。
「えっ、どんな仕事ですか?」
涼子が目を輝かせると、専務は更に自慢げに微笑んだのだった。
涼子はこのモデル事務所で、アパレルネットショップのモデルを専属としていた。楽天を開けば、着飾った涼子がそこらじゅうに写っている。
しかし涼子はネットモデルでは満足できなかった。大手アパレル企業の専属モデルとなれば、それなりに自慢もできたし、それなりのギャラも手に入ったが、しかし、それでは満足できなかった。
涼子の目指す所はネットではなく雑誌だった。それもカタログ販売の雑誌や、素人モデルが道端で撮られているような雑誌ではなく、名のあるブランドのファッションカタログだった。
それを涼子は事務所に強く要望していた。そんな涼子の願いが叶ったかのように専務は微笑んでいたため、涼子は専務の次の言葉に、目を輝かせながら期待していた。
「武田さんがね、来春のSSのジャケットにキミを指名して来たよ」
専務の言葉に、涼子は一瞬呼吸が止まった。
武田というのは、海外の大手ファッションブランドの日本版カタログを数多く手掛けているカメラマンだった。世界的にも名の売れている武田は、モデル達から神と呼ばれる存在だった。
息を詰まらせていた涼子の目がジワッと潤んだ。
あの武田から自分が指名されるなんて……ましてSSのジャケットに選ばれるなんて……
愕然とする涼子の背後から、馴染みのADがヌッと顔を出した。そして手慣れた手付きで、つけまつげに溜った涙を、綿の大きな綿棒で素早く吸い取ってくれた。
「おめでと」
馴染みのADは、次々に滲んで来る涙を吸い取りながら小さく呟いた。しかし、彼女のその一言で一気に涙が溢れてしまい、遂に涙は防波堤のつけまつげを欠壊してしまったのだった。
翌日、涼子と専務は、朝早くから南青山にある武田の事務所に向かった。
十七階建ての真っ白なビルは、宇宙ロケットのような形をしていた。最上階に着くなりハーフの秘書が現れ、奥の部屋へと案内してくれた。
髪をピンクに染めた秘書は、ダイヤが散りばめられたピアスを唇の端にぶら下げ、クロムハーツの最新モデルのブーツを履いていた。まるでドイツのファッション雑誌から飛び出して来たような可愛い女の子だった。
そんな彼女に大きなガラス窓が嵌め込まれた部屋に案内された。
窓からは表参道が一望できた。朝のラッシュで混み合う表参道には、真っ黒な排気ガスと人間が吐き出すエネルギーがムンムンと沸き上がり、まるで暴動が起きているかのように活気に溢れていた。
しばらくすると、難しい表情をした武田が、携帯電話を肩と耳に挟みながらやってきた。
表参道を背景にした白いソファーに横柄に腰掛けた武田は、「皇居での撮影は許可が必要なんてのは権力の横暴だろ」と、携帯に向かって誰かに怒鳴ると、正面に座っていた涼子達を見て「ハロー」っと笑った。
見上げるほどに大きな男だった。元々身長が高い上に、更にヒールの高い靴を履いているため、優に二メートルは超えていた。
骨格はアメフトの選手のようにがっしりとしていたが、スタイルは水泳選手のように品やかでスレンダーだった。
パンツとジャケットはヒョウ柄で決め、長い髪は金髪に染め、首から頬にかけて黒いトカゲのタトゥーを浮かべ、カミソリのように鋭い目にはシベリアンハスキーのようなカラーコンタクトを付けていた。
まるで気が狂ったロックスターのように派手だった。ピンク色の煙草を吸う度に、前歯に埋め込んだ大粒のダイヤをキラリと光らせていた。
「おまえらがどうしても撮影許可を出さないっつーのならもういいよ、山本太郎に直訴させるからもうおまえらには頼まないよ。二度とおまえらみたいな日の丸センズリ野郎とは喋ってやらない。後でロケット弾打ち込まれて吠え面かいてんじゃねぇぞバーカ」
武田はそう言って慌てて電話を切ると、子供のようにケラケラと笑いながら、ふと、起立したままの専務と涼子に気付いた。
「あんたらなにやってんの? 座れば?」
不思議そうに首を傾げる武田に、緊張した専務が「本日はお忙しい中を……」と畏まった挨拶をしようとすると、武田はそれを無視して「皇宮警察本部に圧力をかけてやった」と、涼子に向かって不敵にニヤリと笑った。その目はまるで小学生が悪戯した時のような可愛い目をしていた。
ハーフの秘書が、何やら緑色した不気味なホットドリンクを持ってやって来た。秘書は、それを「エスプレッソだよ」と、涼子と専務と武田の前に置いた。
秘書はそのまま武田の隣りに腰を下ろすと、ピンクのエナメルのバッグの中から書類を取り出した。
「これはウチとあんたの会社との契約書で、こっちはモデルさん自身に書いてもらう同意書。文句がなければさっさと判を押しちゃいな」
そう言いながらテーブルの上に書類を並べる秘書のTシャツには、蛇イチゴのような赤い乳首がくっきりと浮かんでいたのだった。
専務はさっそく老眼鏡をかけると、書類の隅から隅まで真剣に読み始めた。それを見ていた秘書は、武田に出した緑色のエスプレッソをチビリチビリと飲みながら、「ん? なんか文句あるかジジイ、ん? ん?」と、専務を急かせるように何度も呟いていた。
その横で、口をへの字に曲げながらジッと涼子を見ていた武田は、
いきなり右手で金髪の髪をかきあげると、「キミはエルビス・プレスリーが便秘で死んだ件についてどう思う」と涼子の顔を覗き込んだ。
涼子は突然の質問に驚きながらも、その変な質問に思わず「え?」っと首を傾げてしまった。
武田は質問を繰り返さぬまま、秘書からエスプレッソを奪い取り、ズズズッと啜った。そしてそのままエスプレッソでぐちゅぐちゅとウガイをすると、ゴクリと喉を鳴らして飲み込み、涼子の目を見つめながら「キミは何かを隠している」と、意味ありげに呟いた。
何が何だかわからない涼子は、秘書に助けを求めようと彼女に視線を送った。が、しかしハーフの秘書は、蟹スプーンのような長い爪で拳のカサブタを黙々と掻きながら知らん顔していた。そんな秘書の拳にはカサブタになった無数の傷跡が所々に走っていた。
「ズバリ言おう。日頃のキミは、いつもそうしてスマした顔しているんだろうが、実はキミの本性はとっても大変なのだ」
「大変?」と涼子が首を傾げると、拳のカサブタをピリリッと毟ったハーフの秘書が「変態の逆さ言葉です」と呟いた。
「そう変態。キミはきっととんでもない変態だ。自分では気付いていないだろうが、キミは大変な変態なのだ。俺にはわかる。世界各国の美女を何百人と撮って来た俺にはわかる。キミみたいな女は、テレビ見てる時でも、飯食ってる時でも、掃除や洗濯してるだけでエロスなんだ」
そう熱く語る武田の横で、秘書が毟ったカサブタをガラス製の灰皿の中に捨てようとした。
すると武田はそのカサブタを奪い取った。ペロッと口の中に入れ、リスのように前歯でカツカツと噛みだすと、突然、「今朝、私は黒い痰を吐いたよ……」と呟いた。
武田はそのままソファーを立ち上がった。巨大な窓ガラスから朝の表参道を見下ろしながら、「実際ビビったよ……」と呟いた。
「昔ね、カンヌ映画祭に行った時、イタリアの映画監督が教えてくれたんだ。肺病の痰というのは病気の進行と共に色が変わっていくらしくてね、透明から黄色、グレーから紫、そして赤から黒……」
武田はそこで言葉を止めると、くるりと振り向きながら涼子を見つめた。そして、細く揃えた眉を八の字に下げると、ゆっくりと首を振った。
「黒い痰が出たら……もはや手遅れらしい……」
そんな深刻な告白に涼子は戸惑った。しかし、それに答える言葉など何も浮かんで来ない。
一瞬にして部屋が静まり返った。涼子はそのあまりにも重い空気に、身動きできないままジッと自分の足下を見つめていた。
すると、書類に会社のゴム印を押していた秘書がぽつりと呟いた。
「ボスは、昨夜寝る前にオレオを食べたのです」
武田は眉を八の字に下げたままコクリと頷いた。そして目を丸めながら、「実際ビビったよ……」と、濃厚なエスプレッソの香りが漂う溜め息をフーッと吐いた。
「とにかくキミはエロい。生きているだけでエロい。掃除後にくつろぐキミの姿、洗濯後にテレビを見ているキミの姿、その何でもないキミの日常風景がエロスとなって私の頭の中でスライドするんだ、しつこいくらいにスライドするんだ、ジョー山中の人間の証明のテーマくらいにリピートするんだ!」
そんな話を蚊帳の外で聞いていた専務は、小さな溜め息をつきながら書類をテーブルに置いた。
専務が気怠そうに老眼を外すなり、すかさず秘書が、「ん? なんか問題あったのかジジイ」と、顔を覗き込んで来た。
「えっ? いえいえ、これといって問題ございません……」
専務は孫ほど年の離れた秘書に慌てて頭を下げた。
「じゃあ、こことここに判を押せ。嫌ならいいんだぞジジイ、ん?」
専務はそんな秘書を無視して、契約書に会社の印を押した。その印一押しで、何千万円という金が事務所に転がり込んで来るのだ。
涼子はそれを横目で見ながら、自分が手渡された書類に慌てて目を通した。
その書類は『同意書』と書かれていた。撮影中の事故や災害で怪我をしても賠償請求はしません、といった、ありきたりな文がずらりと並んでいた。
それらを納得しながら走り読みしていた涼子だったが、しかし、その最後の行だけがどうも気になった。
それは、モデルは武田のプロデュースを全面的に受け入れなければならない、という内容だった。
つまり、いきなり武田がハゲづらのインデアンの衣装にすると言い出せば、涼子はそれを絶対に着なくてはならないのだ。そしてそれによって、その後のモデルのイメージが崩れてしまったとしても、武田側では一切の責任を負わないといった内容が書かれていたのだ。
その行を何度も読み返していた涼子の頭に、ふと、二年前にワイドショーを騒がせていた事件が過った。
それは、撮影中、突然武田がモデルの頭を押さえ、髪の毛をバリカンで刈ってしまったという事件だった。
丸坊主にされたモデルは、ミス・ユニバース東京大会のグランプリに選ばれた事があるほどの実力派美女だった。しかし、彼女は坊主頭にさせられた上に、ダブダブのランニングシャツと半ズボンを履かされ、虫取りアミ片手に栃木の田園地帯を走らされた。
しかも広大な田園を走るモデルは米粒ほどに小さく写っており、それが誰なのか全くわからなかった。
モデルの事務所が激怒し、丸坊主は強制的だったとして武田を刑事告訴までする構えを見せたが、しかし、武田側はその同意書があった為に、結局この事件はワイドショーを騒がせただけとなった。
涼子はそっと武田を見た。
鼻糞をほじる武田と目が合った。
「心配?」と武田が微笑んだ。
「いえ……」と涼子は不安げに首を振る。
「心配するな。私はキミのオレオだ。最初はビビると思うが、後で必ず笑わせてやる」
武田がそう微笑むと、隣りの専務が涼子の腕を肘で押し、早く印を押せと急かせた。
涼子にはチャンスだった。例え丸坊主にされたとしても、つまらないネットモデルから脱出できるのだ。
涼子はバッグから印を取り出すと、一息にそこに印を押した。
これでもう後戻りはできないと思うと、潔い清々しさが胸に溜っていた不安を一掃してくれた。
秘書は、その書類を引ったくるようにして取ると、サカサカと紙の音を鳴らしながらそれらの書類を揃え始めた。
「契約中は、呉々もコレとコレとコレだけは気を付けてね」
武田は、長い指でいくつかのサインを作りながら涼子に言った。
親指と人差し指でOKを作るサインは借金だった。武田の会社と専属モデル契約したとなれば、この業界の者なら誰でも金を貸してくれた。それが麻痺して、撮影が終わる前に借金地獄に堕ちて行くモデルは大勢いた。
親指をグッドと撓らせたサインは男関係だった。無名のモデルが武田と専属モデルを契約したとなれば同業の男達は黙っていなかった。涼子の骨の髄までしゃぶりつくそうと、そこらじゅうから獣共が群がってくるのは至極当然の事だった。そんな男達にチヤホヤされ、泥沼のスキャンダルを起こしてしまうモデルは少なくなかった。
そんな二つのサインはわかったが、しかし三つ目の、人差し指をクイクイと曲げるサインだけはわからなかった。
涼子は不思議そうに顔を傾けながら、「コレってなんの事ですか?」と武田に聞いて見た。
すると、ハーフの秘書が、印の押された契約書を封筒に入れながら「クスリです」と呟いた。
「安物はいけません。顔が変形して鼻水が止まらなくなります。特にシャブはダメ。ウチのボスは、納豆と高田純次と安物のシャブの体臭が大嫌いなのです。だから、どーしても必要なら私のをあげます」
秘書が淡々とそう言いながら封筒をバッグにしまうと、武田は深く頷きながら秘書の太ももをいやらしく撫で、一言ぽつりと「彼女のプッシーはココナッツミルクの香り」と呟いたのだった。
契約を無事に終え、専務と涼子が丁重に礼を言いながら立ち上がると、股を大きく開いた武田が股間をボリボリと掻きながら「腹減った……」と呟いた。そして秘書の太ももの上に頭をごろりと寝転がすと、「今日のお昼はメリースナッキーのチキンサンドが食べたいよぅ」と甘えるように言った。
そんな武田を、見て見ぬ振りをしながら二人がコソコソと部屋を出て行こうとすると、秘書がいきなり呼び止めた。
「後日、リハーサルをする予定です。スケジュールは決まり次第、こちらから御連絡させて頂きますので、呉々も逃げるなよジジイ」
秘書は、営業用のスマイルでニコッと微笑んだのだった。
宇宙ロケットのようなビルを出ると、表参道の朝のラッシュは既に落ち着いていた。
「滅茶苦茶な奴らだな……」
歩道を歩き出した専務が苦い顔でそう吐き捨てた。
しかし、どれだけ屈辱を受けようとも必死に耐えるしか無かった。涼子の事務所と武田の事務所とでは、資金力も知名度も全てが草野球と大リーグほどに差があるのだ。
この業界は大が小を喰うのが当然だった。天地がひっくり返っても小が大に勝てる事はなかった。小が大に逆らったが最後、その瞬間に小は大に飲み込まれ消滅してしまうのだ。
そんな弱肉強食の業界を裏の裏まで知り尽くしている専務は、顔は屈辱で歪みながらも、涼子には「おめでとう」と笑ってくれた。
涼子はそんな専務が気の毒で仕方なかった。
あの秘書の態度は、この業界で四十年も苦労して来た専務に対する侮辱以外の何者でもなかったのだ。
涼子は、横断歩道で足を止めた専務の背中に、「私の為に……ごめんなさい……」と謝った。
専務は「ん?」と言いながら振り向き、優しい表情で涼子を見つめながら「仕事だからしょうがないさ。キミのせいじゃない、気にするな」と言ってくれた。
信号が赤になり、横断歩道で足止めを喰らっていた人々が一斉に動き出した。
専務は歩き出しながら涼子の隣りに並ぶと、「それに……」と言葉を続けた。
「あの秘書の小娘はね、キミも覚えておくといいけど、あれは業界でも有名なガイキチなんだよ。コンドームの中に覚醒剤を入れて、いつもそれをアソコに入れてるって噂だよ……そんな狂った奴だから、何も気にしてないよ」
「……あの子、いくつなんですか?」
専務はニヤニヤと笑いながら「いくつだと思う?」と涼子の顔を見た。
「……まだ、未成年ですよね?……」
専務は「ふふふふ」っと意味ありげに笑った。
秘書の年齢を明かさないまま、専務は「ふふふふ」と笑い続けながら、点滅し始めた歩道信号に慌てて足を速めたのだった。
タクシーを探しながら表参道を歩いていると、巨大なファッションビルの屋上に、武田が撮影した蒔田ゆう子の写真がでかでかと掲げられているのが見えた。
蒔田ゆう子は、清純派女優として長年映画の世界で活躍してきた大女優だった。古くは、石原裕次郎と青春映画で主演をつとめた事もある実力派で、最近では、日本のガンジーと呼ばれた奥原年蔵の自伝映画で妻役を演じ、日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞を受賞されていた。
そんな蒔田ゆう子が、表参道の曇った空でドジョウ掬いをしていた。汚れた日本手拭で頬っ被りし、下唇と鼻の穴に二本の棒を立て、大きな黒目を寄り目にさせながら、中腰で笊を持っていた。
『悪しき既成概念を覆せ!』
巨大看板には、そんなスローガンが掲げられていた。
それは日本国民党の政党看板だった。そこには、永遠の清純スターとして君臨して来た蒔田ゆう子のイメージを逆転させる事で、日本の悪しき既成概念を覆すという狙いが含まれていたのだった。
この看板は話題を呼んだ。誰もが蒔田ゆう子の変身ぶりに驚き、同時に日本国民党の名を広めた。
武田の狙いは的中した。日本国民党にとっても大成功だった。が、しかし、蒔田ゆう子にとっては大きなダメージだった。
その年、クランクインを間近に控えていた日中合作映画『南京豆の木の下で』の主演を演じる事になっていた蒔田ゆう子は、このバカげた看板が原因で中国から激しい抗議を受け、降板させられてしまったのだった。
そんな蒔田ゆう子を見上げながら涼子は激しい不安に駆られていた。
それは、自分も武田にあんな格好をさせられるのではないかといった不安ではなく、世界的に名の売れた武田と契約をした事に対し、嫉妬深い彼がどう反応するかという不安だった。
表参道を黄色いカウンタックが走り去って行った。歩道のベンチに繋がれていたトイプードルが、その地響きするようなエンジン音に驚き、キャンキャンと狂ったように吠えながらクルクルと空回りしていた。
カウンタックとトイプードル。
走り去るカウンタックが武田に見え、吠えまくるトイプードルが彼に見えた。
ふと、ヒルズ前の街路樹の脇で足を止めた専務が、「なぁRinちゃん……」と呟きながら振り向いた。
「武田の野郎は、恐らくヌードを要求してくると思うけど……本当にそれでもいいのか?……」
涼子は黙ったまま足を止めた。
ドルチェ&ガッバーナの店先ではヒスパニック系の外国人が二人の警察官に職務質問されていた。若い警察官が無線で応援を求め、中年の警察官が浅黒い顔をした外国人に向かって「ワッチャーネェーム」と東北訛りで連発していた。外国人は呆れた表情で何度も肩を窄めながら、必死な中年の警察官を見てニヤニヤと笑っていた。
涼子は専務のくたびれた革靴を見ながらコクンっと頷いた。
「彼氏は大丈夫のか? ほら、フリーでカメラマンやってるっていうあの兄ちゃん。怒らないか?」
涼子は大きく深呼吸した。排気ガスと街路樹の緑の香りと、そして雑貨屋の店先から漂って来るソープの香りが鼻孔で混ざり合った。
「彼は関係ありません……それに、彼もカメラマンですから、きっとわかってくれると思います……」
専務はしばらく涼子の目を見たまま黙っていたが、「わかった」と静かに頷くと急に頬を弛め、「Rinちゃんがそこまで腹を括っているならもう何も言わない」と再び歩き始めた。
赤いランプを回転させたパトカーが歩道の脇に止まった。二人の警察官がパトカーから降りて来た。
それを見て勢いづいた中年警察官が、再び東北訛りで「ワッチャーネェーム!」と怒鳴った。
外国人は、たちまち四人の屈強な警察官に囲まれた。狼狽えた外国人は「ワタシなにシタ? ココにいただけ、なにもシテない」と、警察官達の顔をキョロキョロ見ながら懸命に訴えていた。
涼子はそんな外国人を横目に歩き出した。
疑う人間と、疑われる人間。幼い頃から、自分は常に疑われる立場だったとふと思った。
人に疑われる苦しさ、そしてその疑いを晴らせない辛さ。それを痛いほど知る涼子は、異国で疑われている外国人の悲痛な叫びに耳を塞いだ。
しかしその五分後、ヒスパニック系の外国人のバッグの中から大量の大麻と改造拳銃が発見された。
疑われるということはそれなりの根拠があるから疑われるのであり、その疑いはほとんどの場合、正しいものである。
外国人は散々抵抗した挙げ句、四人の警察官に取り押さえられそのまま逮捕された。
しかし、既にその場を離れていた涼子はそれを知らない。
(つづく)
《←目次へ》《3話へ→》