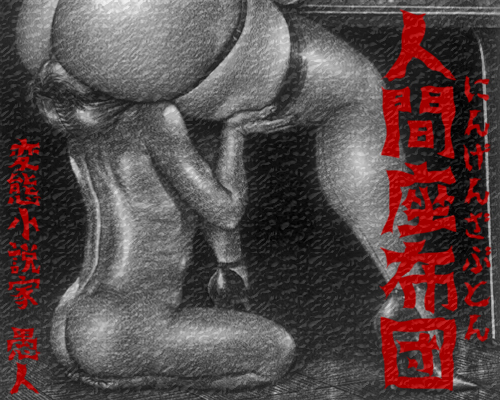人間座布団
2013/05/02 Thu 22:42
「違うんだよ、それじゃだめなんだって、何度言ったらわかるんだよ、もっとさぁ、当たり前な感じで、おもいきり、どすん! と座らなきゃ、ストーリーが成り立たないだろ」
汗臭いステージに団長の声が響いた。劇団員達が見守る客席は水を打ったように静まり返っている。
わかるだろ? と言いながら団長はユカを睨んだ。ユカは今にも泣きそうな顔をしながら「でも……」と呟いた。
「でも、とか、そーいうのいらない。おまえはこいつの顔の上に、どすんっと座ればいいだけなの。でも、とか、だけど、なんてこのシーンに必要ないの」
ユカはステージの床に寝転がる僕をジッと見つめたまま項垂れていた。そんなユカと僕を交互に見つめながら団長が再び荒い声を張り上げた。
「こいつは座布団なんだよ。こいつは純一じゃない、座布団なんだよ。おまえは座布団に座る時、いちいちそうやって恥ずかしがるのか? そうやってモゾモゾと遠慮しながら座るのか? 最近のジョシコーセーは座布団に座る時に、やだぁって恥ずかしがるのか? あん?」
そう言いながら丸めた台本で項垂れたユカの頭をポカポカと叩く団長は、恥ずかしいなら演劇なんかやめちまぇ! と怒鳴り、そのままステージを下りてしまったのだった。
確かに、ユカのその演技は、この脚本が社会に訴えようとしている部分を根本的に覆すものだった。
この物語は、ある大金持ちの娘が、不当解雇された派遣社員達を『物』として雇うというストーリーだった。時給二百円で雇われた者達は、毎日娘の家で扉や机や自転車として使われるという実に悲しい左翼的なお芝居で、僕は客間の座布団として使われていた。
そんな、不況の世の中を揶揄したような物語だったため、金持ちの娘を演じるユカの演技は、もっと横柄で傲慢で威丈高な態度でなければならず、娘が時給二百円で雇った『物』たちに遠慮していては、このストーリーは成り立たなくなってしまうのだった。
しかし、そうは言っても、さすがにこのシーンだけは皆がユカに同情していた。
そのシーンというのは、娘が新しく雇った下駄箱人間と面接するシーンだった。
設定は客間で、優雅な生活に堕落した娘が、アイスクリームを舐めながら下駄箱人間を面接するというものだった。
そのシーンのどこに皆は同情したのか。
それは、そのシーンでのユカの衣装だった。その堕落さを強調するために、金持ち娘の衣装はキャミソールに短パンという格好でなければならず、そうなると、ユカは尻肉がはみ出るほどの短パン姿で、座布団として雇われている僕の顔の上に座らなければならなかったのである。
これには、女の劇団員達から激しいクレームが起きた。
彼女達は団長を取り囲み、あまりにも卑猥過ぎる、と直談判に及んだが、しかし団長は一歩も引かなかった。
平気で人の顔の上に座るというブルジョア娘の馬鹿さ加減を表現するには、どうしてもその格好でなければならないんだ、と団長は、そのシーンでのそれがいかにこの物語で重要であるかを主張し、挙げ句には、ユカに向かって「嫌なら主役を降りろ!」と怒鳴る始末だった。
結局、女劇団員達のクレームはいとも簡単に却下され、ユカもせっかく掴んだ主役を逃したくないという一心で短パンを履く決心をした。
しかし、いざ練習の段階になるとユカは怖じ気づいた。練習中はトレパンを履いていたが、それでも、男の顔の上に座るというのは、十七才の少女にとっては凄まじい羞恥なのである。
ユカは、ステージに寝転がる僕を申し訳なさそうに見つめながら、恐る恐る僕の顔に尻を乗せた。小さいわりにはぷるんっと突き出した丸い尻肉が僕の鼻を押し潰した。
ユカは尻を斜めに傾けていた為、右の尻肉が僕の顔面を圧迫し、僕はものの一分も立たないうちに窒息しそうになり、両手両脚をバタバタとさせた。
その度に団長の怒声が練習場に響き渡った。
ユカには「恥ずかしいなら劇団やめろ!」と怒鳴り、僕には「窒息死するまで耐えろ!」と怒鳴った。そして最後は必ず「てめぇら東北に帰って百姓でもしてろ!」と台本をステージに投げつけ、ドカドカと練習場を出て行った。
因みに、僕は東京生まれの東京育ちで、ユカの実家は横浜だった。
そんな散々な練習が三日続いた頃、練習を終えて予備校へ向かおうとしていた僕を、いきなりユカが呼び止めた。
「純一君、これから暇?」
ユカは小動物を思わせる仕草で僕の顔を覗き込んだ。
さすが主役に抜擢されるだけあってユカは可愛かった。
リカちゃん人形のような小さな顔に、ほんのりと茶髪に染めたショートボブがよく似合っていた。小柄ながらもスラリと伸びた手足はモデルのように均等が取れており、その顔とスタイルは、まるでオタク系の同人誌に描かれている清純女子高生のようだった。
そんなユカが、大きな目にくりくりの黒目を輝かせながら僕をジッと見ていた。
僕はおもわず「暇だけど、どうして?」と嘘をついた。
「うん……これから、私のマンションで面接シーンの練習をしたいんだけど、純一君も一緒にして貰えないかなぁって思って……ダメ?」
ユカがそう首を傾げると、僕は一呼吸置いた後に、「別にいいけど……」と素っ気なく答えた。
本当は飛び上がりたいほどに嬉しかった。ユカのマンションで二人きり、しかも練習するシーンは、例の卑猥なシーンなのだ。
「よかったぁ」と、パッと花が咲いたように微笑んだユカは、「じゃあ、すぐに着替えて来るから待ってて」と、サンダルをペタペタと鳴らしながら僕の横をすり抜けていった。
ユカが走り去った後の廊下には、若い女のシャンプーの香りがほんのりと漂い、そんな香りに包まれた僕は、思わずガッツポーズを取っていたのだった。
ユカと二人で電車に乗った。ユカは高校の制服を着ていた。
いつもジャージ姿のユカしか見た事がなかった僕は、チェック柄のミニスカートから伸びる黒いニーソックスに目眩を感じていた。
聞いた事のない名前の小さな駅で降りると、駅前にあるローソンに立ち寄った。
ぼんやりと雑誌を立ち読みしていると、背後からスっと顔を出したユカが「エッチなの読んでんでしょ」と雑誌を覗き込んだ。
違うよ、求人情報だよ、と笑いながら振り向くと、ユカは、ふ〜ん……バイト探してんだぁ……予備校生って大変だね、と深刻そうに頷いた。
そんなユカが持っているカゴの中にはポッキーとダイエットコーラが転がっていた。
ユカは「ねぇねぇ」と言いながら僕の手を引っぱり、僕を奥のカップラーメンのコーナーまで連れて行った。
「私、料理は何もできないから、好きなの選んで」
ラックに並ぶカップラーメンを指差したユカは、「お腹空いたね」と呟きがら、淡いピンクでネイルされた綺麗な爪で『どん平』の蓋のビニールをカリカリした。
現役の女子高生にチキンラーメンを買って貰った。
ユカは、お腹空いたねと言っておきながら、自分は何も買わなかった。ダイエットをしているらしく、今夜の夕食はポッキーとダイエットコーラなの、っと淋しそうに笑った。
黄色い看板のコインパーキングを右折しながら、「全然ダイエットなんかしなくていいじゃん」、と、ユカの細い腰を横目で見ながら言うと、ユカはコンビニの袋を指でクルクルさせながら、「ダメよ。だって太っちゃったら純一君が窒息死しちゃうもん」と恥ずかしそうに笑った。
そんなユカの笑顔に慌てて目を反らした僕は、初めて来た町の薄暗い路地を歩きながら、この役を与えてくれた団長に心から感謝したのだった。
ユカのマンションは八畳一間のワンルームだった。
現役女子高生の部屋に入るのは初めてだった僕は、竹下通りにあるような派手なショップをイメージしていたが、ユカの部屋はすっきりと白く、点きっぱなしの高そうな空気清浄機が爽やかさを更に強調していた。
そんな、イタリアのデザイナーズホテルのような部屋で、僕はチキンラーメンをずるずると啜った。
ユカはダイエットコーラをちびちびと飲みながらポッキーをカリカリと齧り、私、来年の東宝のオーディションを受けようと思ってんだ、と呟いた。
大学へは行かないの? と聞くと、行かない、と小さく答えた。
今の劇団で名前を売って東宝のオーディションに乗込むんだと力強く頷き、だから、どうしても今回の役は成功させたいの、と、真剣な目で僕を見た。
ユカのその目に熱意を感じた僕は、残っていたスープを一気に飲み干し、「それじゃあ練習は徹底的に頑張らなきゃな」、と、ひと昔前の織田裕二っぽく笑うと、ユカは「うん」と跳ねるように頷きながら、「じゃあさっそく着替えて来るね」と、嬉しそうに浴室に消えて行ったのだった。
時刻は九時を過ぎていた。
今から可愛い女子高生が僕の顔に座ると思うと、あらゆる妄想が僕の頭で渦巻き、激しく呼吸が乱れた。
場合によっては、これがきっかけで恋が芽生え、もしかしたら僕はこの真っ白な部屋の住人になるかも知れないとまで考え、改めて部屋の中を見回したりした。
本番用の短パンを履いたユカが浴室から出て来た。プルンっと丸みを帯びた尻からスラリとした脚が伸び、キュッと脚を締めた黒いニーソックスが異様に可愛かった。
短パンを隠そうと必死にTシャツを伸しているユカに、僕は激しく動揺しながらも、敢えて「じゃあ、始めよっか」と自然体で言った。
フローリングの床に仰向けに寝転がった。
天井も真っ白だった。ふと、天井の電気の丸いカバーを雪見大福のようだと思った時、そんな僕の視界に、恐る恐る僕の顔を覗き込むユカの顔が現れた。
「いい?」とユカは恥ずかしそうに聞いた。
「いいよ」と僕は興奮を押し殺しながら答えた。
ユカがクルッと背中を向けると、短パンに包まれた丸い尻が頭上に浮かんだ。短パンの隙間から微かに下着が見えたような気がした。。
「いくね」と言いながらユカが膝を曲げた。
あっという間に尻は顔面に迫り、右の尻肉が僕の鼻を潰した。
女子高生の尻の感触を満喫するどころではなかった。鼻は痛いし、フローリングに押し付けられた後頭部は痛いし、おまけに息はできないしで、たちまち僕はもがき苦しんだ。
「あっ、ごめん」
慌てて立ち上がったユカは、心配そうに僕の顔を覗き込んだ。
あたたたたたっ……と、鼻と後頭部を押さえながら身体を横に向けると、しゃがんでいるユカの股間がすぐ目の前にあった。
「痛い? 大丈夫?」
ユカはそう心配しながら僕の後頭部を細い指で擦り始めた。僕はいててててっとわざとらしく鼻を押さえながら、ユカのしゃがんだ股間をソッと覗いた。
真っ白な太ももに左右から押し付けられた股間がぷっくりと膨らんでいた。その膨らみの中に薄らと一本の縦線がシワを作っていた。
僕はその縦線をしっかりと目に焼き付けながら、「あのさぁ」とユカに言った。
「いつも座る時、お尻を斜めにしてるよね」
ユカは、少し戸惑いながら「うん……」と返事をした。
「あれが痛いんだよ。お尻の肉で鼻がつぶれちゃうんだよね……」
「……じゃあ、どうすればいいの?」
ユカは僕の後頭部を擦る指を止め、困惑しながら首を斜めに傾けた。
僕は、女子高生の割れ目の食い込みを見つめながら言った。
「真ん中で座ってくれないかなあ……そうすれば中心の隙間に鼻がフィットして、鼻も潰れずに息もできると思うんだ……」
ユカはスッと俯いた。しゃがんだ自分の股間を見つめ、とたんに顔をカッと赤くさせた。
「……このシーンは結構長いから、あれじゃ息が続かないよ……恥ずかしいとは思うけど、成功させるにはそれしかないと思うんだよね……」
僕のそんな言葉に、ユカは黙ったまま考えていた。
しばらくすると、いきなりユカがパッと顔を上げた。
ユカは、腹を括ったような力強い目で僕を見ながら「ごめんね」と謝ると、「位置がわかんないから、教えて」と僕の顔を覗き込みながら恥ずかしそうに微笑んだのだった。
腰をゆっくりと下ろすユカは、戸惑いながらも、尻の谷間に僕の鼻を押し付けた。
ユカの股間の柔らかい膨らみに、僕の鼻がムニュッと食い込んだ。
「ねぇ、大丈夫?」
頭上からユカの恥ずかしそうな声が聞こえて来た。
僕は押し潰された鼻と、塞がれた口をもごもごさせながら、尖らせた唇でユカの股間に微かな空気の隙間を作ると、そこからフーフーと呼吸をしながら「ばいぼうぶ」と返事をした。
「じゃあ、このまま練習始めるね……」
ユカは、恥ずかしそうに声を震わせながらそう言うと、下駄箱人間を面接するセリフを話し始めた。
頭上から聞こえてくるセリフを微かに耳にしながら、二つの丸い尻肉に顔を挟まれる僕は恍惚としていた。
僕の鼻は、丁度ユカの性器に挟まっていた。性器のぐにょぐにょとした感触を鼻の頭に感じると共に、スースーと息を吸う度に汗のような饐えた匂いを感じた。
現役女子高生の尻。可愛い女子高生のアソコ。そんな事を思いながら、軽い肉厚に酔いしれていると、みるみる僕の股間が大きくなって来た。
幸い、ユカは背を向けていたため、勃起した事を気付かれなかった。
そう考えると、これはチャンスだと思い、僕は硬くなった股間にそろりそろりと指を伸ばした。
「あなたの仕事は、玄関で靴を持ってて貰うだけでいいの。動かず、喋らず、ただただ一日中じっと靴を持ってるだけでいいのよ。それだけで時給二百円貰えるんだから、うふふふふ、あなた達みたいなクズ人間達にはもってこいの仕事でしょ」
そんなユカのセリフを聞きながら、ジーンズの上から硬い肉棒を撫でた。指で亀頭をぎゅっぎゅっと押し、密かな快楽に身悶えた。
少し顔をズラしてみた。とたんに、ユカの尻が浮き上がり、「苦しい?」と心配そうな声が聞こえた。
「苦しいけど大丈夫。我慢する。だから練習を続けて」
そう言いながら、わざとらしくハァハァと大きく息をしていると、ユカは申し訳なさそうに「本当にごめんね」と言いながら、再び僕の顔に尻を押し付けた。
今度は少し角度が変わっていた。
股間の中心が鼻からずれ、短パンと太ももの隙間に鼻が押し付けられた。
そこは股関節と呼ばれる部分だった。性器からは少しずれていたが、しかし、このほうがより性器を堪能できた。なぜなら、僕の鼻は太ももと股間の隙間に埋もれていたからだ。
短パンの股間部分に微かな隙間があるのを発見した。
鼻頭をじわりじわりと動かしながら、その隙間に鼻の穴を向けた。
「この家に一歩入った時から、あなたはもう人間じゃないわ。あなたは下駄箱になるの。毎日、右手の平にサンダルを置き、左手の平に父の靴を置いて、一日中、ジッとしているの。それがあなたにできる?」
僕は、(できる)と心の中で答えながら、短パンの隙間から微かに匂って来る性器独特の淫臭に悶えた。ユカの座布団だったら、毎日、いや一生なっててもいいと本気でそう思いながら、ジーンズの上から肉棒をぎゅっぎゅっと握った。
「見てみなさい。彼は座布団よ。座布団として、時給二百円で私に雇われてるの」
ユカは身体を曲げながら振り向き、座布団の僕を指差した。
身体を曲げた事によって、またしても鼻の位置がずれた。
再び、僕の鼻は柔らかい割れ目に挟まれた。
「彼はプロよ。こうして何も考えずに一日中ずっと寝転んでいる彼は座布団のプロなの。あなたも一日も早く下駄箱のプロになる事ね」
ふふふふふふっ、と怪しく笑い始めたユカの腹筋が揺れた。
鼻がぐいぐいと割れ目に食い込んだ。
その瞬間、僕は凄まじい衝撃に襲われた。
なんと、僕の鼻の頭がじっとりと湿っているのである。
(濡れてる……ユカの性器が濡れている……)
そう興奮しながら、おもいきり肉棒を握り締めると、ふいにトランクスの中でヌッと精液が飛び出した。
生温い感触をトランクスの中に感じながら、僕はおもいきり息を吸い込んだ。短パンの股間が湿っているせいか、ほんのりとイカ臭い淫臭はさっきよりも生々しく、濃厚に感じられた。
精液がドクドクと溢れる肉棒を更にグイグイと握ると、僕は快楽のド壷にハマった。
僕の両脚は自然にピーンと伸び、半開きでハァハァと息をしていた唇の端からトロリと涎が垂れた。
突然ユカがパッと立ち上がった。
快楽の底からいきなり引きずり上げられた僕は、慌てて股間から手を離すと、半開きになっていた唇をギュッと閉じた。
「ど、どうしたの」
慌ててユカの背中に聞くと、ユカは「ごめん、ちょっとおトイレに行って来る」と、言ったまま、後も振り向かないでトイレに走っていった。
明らかに様子が変だった。
僕は焦った。密かに射精していたのがバレたのだろうかと慌ててジーンズの股間を見ると、そこにはじっとりとしたシミが広がっていたのだった。
五分経ってもユカはトイレから出て来なかった。
十分経った頃、そっとトイレの扉の前へ行き、「ねぇ」と声を掛けてみた。もし、射精していた事がバレていたなら、恥ずかしいが素直に謝るしかないと思っていた。
僕の呼びかけに、ユカは沈んだ声で「うん」と返事をした。
「どうしたの?……僕、何か悪い事したかなぁ……」
射精がバレたかどうか、カマを掛けてみた。
「うぅぅん、違うの。自分の問題なの。ごめんね……」
ユカはそう答えながら、グスンっと小さく鼻を鳴らした。どうやらユカは泣いているようだった。
ユカの言葉を聞いて、僕の射精が原因ではない事を知るとひとまず安心した。
「どうしたの?……セリフ、すごく上手く言えてたじゃないか……それに、ちゃんと僕の顔の上に座れてたし……」
「うん……だけど……本当にごめんなさい……今夜はもう無理そうなの……勝手な事言って悪いんだけど……今日はこのまま帰って……」
ユカの声はどっぷりと落ち込んでいた。
ユカが落ち込んだ原因は、恐らく、自分のアソコが濡れた事に気付いたからだろうと思った。
僕は、そんな純粋なユカが愛おしくて堪らなくなった。
マンションを出ると、一瞬、方向音痴になった。
駅はどっちだったっけ、と思いながら、取りあえず身体が向いていた方向へ進んだ。
歩く度にドロドロの精液が太ももに粘着した。トランクスに染み込んだ精液は既にパリパリに乾き始めていたが、陰毛に絡み付く精液の塊は、こんにゃくゼリーのようにぷるぷるしたままだった。
気持ち悪いと思いながら中腰になると、ふと、ジーンズの後ポケットに違和感を感じた。
はっ、と右手を尻のポケットにあてた。案の定、いつもそこに入っている携帯が消えていた。そう言えば、床に寝転ぶ前に携帯をポケットから出したんだと気付いた僕は、中腰になりながら今来た道を引き返したのだった。
マンションの階段を上がると、廊下の奥にユカの部屋のドアが見えた。
つい、五分ほど前に見た光景だったが、なぜか異様に切なく感じた。
ドアノブを回すと、鍵は開いたままだった。まだトイレに閉じ篭っているのかと心配になりながら、扉の隙間からそっと中を覗いてみると、部屋の奥で真っ白な脚がくねくねと蠢いているのが見えた。
いきなり後頭部を金槌で殴られたような衝撃が走った。
明らかに、ユカはオナニーをしているのである。
僕は乾いた喉にゴクリと唾を飲み込みながら、ソッと玄関に忍び込んだ。
息を止めながら静にドアを閉めると、廊下に響いていたボイラーの音が消え、急に静まり返った。
「あぁぁん……」
奥の部屋から切ない声が聞こえた。
白い脚がスリスリと擦れ合い、可愛い爪先がピーンと伸びたりしている。
僕はジーンズのボタンをソッと外した。
精液にまみれたペニスは、さっきよりも獰猛に反り起っていた。
このペニスが、ユカの小さな性器にヌポッと滑り込む感触を頭に描きながら、スルスルとジーンズを脱いだ。
これから始める練習は、ノーパンのまま顔に跨がらせよう。
そう思いながら、僕は部屋の奥へと進んでいったのだった。
(人間座布団・完)
《←フェチ特集の目次に戻る》