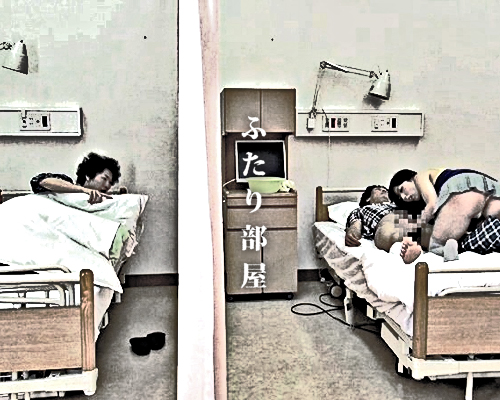ふたり部屋
2012/11/17 Sat 04:25
大きな扉がスルスルスルッと開く気配がすると、ベッドの真ん中を仕切っている薄いピンクのカーテンがふわりと揺れた。
カーテンの向こうから、こんにちは、っと微笑む柔らかい声が聞こえ、同時に、「どうも……」と無愛想に答える嶋田さんの野太い声が聞こえた。
床にカツコツと響くヒールの音が私のベッドに近付いて来た。
「具合はどう?」
カーテンから顔を覗かせたのは妻の由梨江だった。
私は、うん、と小さく頷きながら妻から目を反らした。
「これママからのお見舞い」
妻はそう言いながら丸い缶に入ったクッキーセットをベッドサイドにコツンっと置いた。恐らくコンビニで買って来たのだろう、妙に安っぽく古臭い缶だった。
入院してかれこれ三ヶ月が過ぎようとしていた。
今まで集団部屋だったが、今日、やっと個室に入る事が出来た。
しかし、個室といってもそこは二人部屋だった。
病名は糖尿病だった。若い頃から糖尿の気はあった私だったが、まさか三十代で糖尿病を悪化させ入院するとは夢にも思っていなかった。
いつ退院できるかわからなかった。
会社はそんな私をいとも簡単に見捨て、収入が途切れた。
たちまち家計は火の車となり、仕方なく妻は先月からスナックで働き始めた。
妻に水商売などさせたくはなかったが、しかし貯金も収入も無く、こう入院費ばかり掛かっていては、背に腹は変えられなかった。
妻はベッドサイドに散らばるDVDや週刊誌などを整頓し始めた。
私はそんな妻の派手な化粧と短いスカートを横目で見ながら布団に潜り込んだ。
妻に背を向けながら布団に包まっていた私は嫉妬していた。
何に対して誰に対して嫉妬しているのか自分でもわからなかったが、それは明らかに嫉妬という感情だった。
恐らく、長期入院によるストレスと、先の見えない不安、そして夜な夜なスナックで働きながら客に媚を売っている妻への疑念といったものが全て重なり合い、それが嫉妬という幼稚な感情となって心の中で渦を巻いているのだろう。
そんな今の私は、糖尿病だけでなく心も病んでしまっていたのだった。
背後に妻の気配を感じながら、ラブホのベッドで見知らぬ男と乱れる妻の姿を想像した。
きっと昨夜もまた別の客とラブホに行ったに違いないと私はそう思い込んでいた。何一つ証拠も根拠も無いのだが、そう思い込めば思い込むほど、絶対に間違いないと確信した。
胸を掻きむしられながら、妻が大勢の客達に陵辱されるシーンを思い描いた。スナックのボックスの奥に追い込まれた妻が、スーツ姿の酔ったサラリーマン達に身体中を弄られた挙げ句、「ほら、チップをあげるから、ね、いいだろ」と、醜く太った係長に一万円を無理矢理に握らされてはパンティーを毟り取られる。
そんな妄想を次々に思い浮かべながらベッドの中で悶え苦しんでいると、不意に妻が布団の隙間から覗き込んでは「ねぇ」と言った。
「あなた、なにしてるの?」
妻はそう言いながらソッと掛け布団を剥ぐった。
掛け布団を毟り取られた私はベッドの上で団子虫のように丸まりながら妻を睨んだ。
「おまえ、昨日は何時に帰って来たんだ」
「何時って……お店が終わったら直ぐに帰って来たけど」
「嘘をつくな。全部知ってるんだぞ」
「……知ってるって、何を?」
「もういい……」
私はそう吐き捨てながら仰向けになると、そのままスルスルとパジャマのズボンを下ろした。
「しゃぶってくれ……」
トランクスを膝まで下げながらそう言うと、妻は困惑した表情で薄ピンクのカーテンを見た。
「大丈夫さ……」
私は妻の体を引き寄せながらカーテンの向こうの嶋田さんを差し、「派手にやらなけりゃバレないよ」と妻の耳元に囁いた。
ベッドの端に腰掛けた妻がブヨブヨのペニスを摘んだ。妻の細く長い指はひんやりと冷たく、感覚を忘れかけている亀頭をその気にさせた。
が、しかし、どれだけシゴいても私のペニスは反応しなかった。
心は妻の甘い匂いに激しく興奮しているのに、私の体はそれに乗じようとはしなかった。
「若くして糖尿になると、何が一番怖いかって女房の浮気さ」
同じ糖尿病で入院している中畑さんのそんな言葉が頭に浮かんだ。
妻はまだ若かった。スタイルも良くなかなかの美人だ。
そんな二十七才の綺麗な若妻が、かれこれ一年以上もセックスをしていなかった。一年以上も勃起したペニスに触れていないのだ。
しかも妻は性欲が人一倍旺盛な女だった。
結婚前に付き合っていた男は私が知るだけでも六人おり、そのうちの三人は不倫関係だった。
年の離れた不倫相手に肉玩具にされていた妻は、経験豊かな親父たちからマニアックな快楽を教え込まれ、まさに変態として調教されていた。
まして、今の妻はスナックで働いており、夜な夜な酔った客と下品な猥談で盛り上がっては、執拗に誘われ口説かれ、そして時には体を触られたりしているのだ。
そんな妻が一年以上もセックスをしていないのである。今のこの状況に立たされた妻が、浮気をしないわけがなかったのだった。
妻は隣の嶋田さんを気にしながらも、萎びたペニスにソッと顔を近づけた。
「本当に大丈夫?」
不安そうに見上げた瞳は、既に変態女の色を浮かべていた。
きっとこのシチュエーションに感じてしまっているのだ。
「大丈夫だから早くしろ……」
そう言いながら私は妻のミニスカートの中に手を入れた。
案の定、妻の陰部は驚くほどに濡れていた。
陰部を弄られて興奮した妻が、尻をモゾモゾと動かし始めた。
私の腹の上で「あぁぁん……あなた……」と小さく呻くと、陰毛をザラザラ鳴らしながら舌を移動させ、その丸く開いた唇の中にペニスをチュルっと吸い込んだのだった。
結局、私のペニスは立たなかったが、妻は萎んだペニスを銜えながら、私の指で二回も絶頂に達した。
しかし、例え二回イッたとしても私の不安は拭いきれなかった。
このまま体の火照った妻を返せば、きっと妻は今夜もまた客の肉棒を求めるに決まっているのだ。
そう思った私は、今度は舌でイカせてやると、妻の股間に顔を埋めたが、しかしクリトリスに舌を這わせた瞬間、壁のスピーカーから夕食のメロディーが流れ出し、仕方なく私は妻の陰部をヌルヌルに濡らしたままで、妻を帰らせてしまったのだった。
妻が帰ると、さっそく夕食が運ばれて来た。
ここの病院食は、患者の病状に合わせたメニューだった。
糖尿病の私のメニューは最悪だった。まるで小学校の校庭で飼われているウサギの餌のように質素だ。
その点、肺を患って入院している嶋田さんのメニューは豪勢だった。
栄養を取らなければならないという嶋田さんのプレートには、キツネ色したアジのフライがキラキラと輝いていた。
そんな嶋田さんのベッドを横目で見ながら、蕎麦湯のようなお粥をズルズルと啜った。
すると、嶋田さんがフーッと深い溜息をつきながら私を見た。
「さっきの人、奥さんですか?」
嶋田さんは箸の先でアジのフライをツンツンと突きながら聞いた。
「ええ……」
戸惑いながら頷くと、嶋田さんは「若くて綺麗な奥さんですね……羨ましい限りです」と言いながら、私の質素なプレートの上にソッとアジのフライを乗せた。
「えっ? いいんですか?」
カサカサと鳴る衣にゴクリと唾を飲み込みながら聞くと、嶋田さんはニヤリと意味ありげに笑った。
「同室になったのも何かの縁です。お互い、助け合いながら病魔と闘っていきましょうよ」
嶋田さんはそう笑うと、夕食には箸を付けないままベッドにゴロリと横になった。
そんな嶋田さんを横目に、それじゃあ遠慮なく、と言いながらキツネ色の衣にカシュッと齧り付いた。たちまち油が口内に広がり、久々の旨味に身震いした。
「私の女房なんてね、かれこれ一年以上も顔を出さないでいるんですよ……酷い話でしょ……」
嶋田さんは布団に包まりながらそう呟き、開き直るようにふふふふふっと笑った。
「嶋田さんは入院してどれだけになるんですか?」
私はサクサクのフライを咀嚼しながら嶋田さんの貪よりと濁った目を見た。
「五十才の時に入院しましたから、もう四年になりますかね……」
「四年ですか……長いですね……」
「ええ。途方もなく長かったですね……おかげで仕事も家族も全て失いましたよ……でもね、先日の検査で、やっといい結果が出ましから……」
「いよいよ退院なんですね」
「いえ、余命半年だと宣告されました……あと半年でやっとこの地獄から解放されます……」
そう微笑んだ嶋田さんは静かに寝返りを打った。
嶋田さんのパジャマの襟元から骨と皮だけの肩が惨めに顔を出していた。
返す言葉も無い私は、窓から見える銭湯の煙突を見つめながら、咀嚼していたアジのフライを静かに飲み込んだのだった。
翌日も出勤前に妻がやって来た。
太ももを丸出しにしたミニスカートを履いてやって来た。
「そんなに短いスカートだと客にパンツが見えてしまうじゃないか」
私は嫌悪を露骨に剥き出しながら妻を睨んだ。
「見えるわけないじゃない。ずっとカウンターの中にいるんだから」
妻はそう笑いながら、いつものようにベッドサイドの整頓を始めた。
「じゃあどうしてわざわざそんなスカートを履くんだよ……客以外の誰かに見せるつもりなのか……」
そう嫌味を言いながら、背中を向けている妻のスカートの中をソッと覗くと、なんと下着はTバックだった。
とたんにカッと頭に血が上った。
Tバックが食い込むムニムニの尻肉を覗き込みながら、このTバックはいったい誰の為に履いているんだという怒りが込み上げて来た。
私は妻の手を取り、そのままベッドに引っ張った。
きゃッと小さく驚きながら、妻はベッドの上に尻餅を付いた。
すかさずミニスカートの中に手を入れ、もう片方の手でタプタプの乳房を鷲掴みにした。
「お前が浮気している事くらいお見通しなんだよ……」
そう妻の耳元に囁きながら、薄いキャミソールの上から乳首をおもいきり摘んでやった。
「浮気してる暇なんかあるわけないじゃない、お店と病院を行ったり来たりで手一杯よ」
妻はクスッと微笑みながら私の腕に凭れ掛かり、その熟れた身を好きにしてとばかりに委ねて来た。
「じゃあ、どうしてこんなパンツを履いてるんだ……」
私はスカートの中でTバックの紐を引っ張った。恐らく、スカートの中では引っ張られた紐がワレメに激しく食い込んでいる事だろう。
「それは……あなたの為に履いて来たのよ……その証拠に、もう濡れてるでしょ?……」
確かに妻のワレメは練り過ぎた納豆を垂らしたかのようにヌルヌルに濡れていた。
Tバックの紐をズラし、指を二本入れた。
んふっ……と息を吐きながら、妻が私の胸に顔を埋めた。
私は妻の細い肩を抱き、妻の顔を覗き込みながら指を激しく動かした。
静まり返った病室に、タクタクタクっと小気味良い音が響き、とたんに妻は顔をポッと赤らめた。
「ヤダ……聞こえちゃうよ……」
囁く妻の息が私の頬に触れた。
艶かしい息の生温かさに即発された私は妻の唇にむしゃぶりつき、ベプベプと卑猥な音を立てながら妻の口内を舐めまくった。
互いに「はふっ」と息を吐きながら唇を離すと、すかさず妻が囁いた。
「隣に聞こえちゃうから激しいのはやめて」
「聞こえたっていいじゃないか……」
そう答えながら大きな乳を揉みしだく私の脳裏に、ふと「聞かせてやればいいじゃないか」という考えが浮かんだ。
そうだ聞かせてやるんだ。そして見せてやるんだ。
四年間も入院生活を余儀なくされ、妻や子供にも見捨てられ、何の愉しみも無くただただ余命半年を寝て暮らす哀れな病人に、桃色な刺激を与えてやろう。
突然そう思った私は、妻の腕を強引に引っ張り、妻の体をカーテン側に移動させた。
えっ? と不思議そうにしている妻をベッドから降ろし、並んだ二つのベッドの間に立たせると、私はそのままパジャマのズボンを下ろして萎んだペニスを剥き出しにした。
「しゃぶってくれ……」
わざと隣に聞こえるようにはっきりそう言った。
焦った妻がカーテンに振り返り、困惑した表情で私を見つめた。
私はそんな妻の顔をゆっくりと引き寄せた。
そして妻の耳元に、「そのままお尻を突き出して、お隣りさんにもおまえのそのいやらしい尻を見てもらうんだ……」と、囁いた。
その瞬間、妻の目の色が変わった。
その言葉だけで変態のスイッチが入ってしまったのか、妻のその目は、過去に不倫相手からマニアックな調教を散々受けてきたマゾヒストの輝きを帯びていた。
私はそんな変身した妻の唇を再び吸った。
先程とは違い、妻は攻撃的に熱い舌を私の口内に押し入れて来た。
レロレロと互いに舌を絡ませていると、鼻息を荒くさせる妻は、まるで陸上短距離のクラウチングスタートのように尻を高く突き上げた。
スカートは捲れ、丸い尻が不自然に飛び出していた。
酔っぱらったバカ客達に見られるくらいなら、余命わずかな嶋田さんに見てもらった方がどれだけましか。
そう思いながら私は、キスをしたままカーテンの端を少しだけ開けた。
カーテンの隙間をソッと覗くと、いきなり嶋田さんと目が合った。
嶋田さんは気配を察していたのか、体をカーテンに向けたながらひっそりとベッドに腰掛けていた。
私は嶋田さんの目を優しく見つめたまま、わざと嶋田さんに聞こえるような声で妻に言った。
「昨日の夕食の時、隣りの嶋田さんにアジのフライを頂いたんだ……久しぶりに食ったフライは旨かったなぁ……あとでおまえからもよく礼を言っておいてくれよ」
そう呟く私の気持ちが伝わったのか、嶋田さんは恐る恐るカーテンの隙間に顔を近づけた。
そしてそこに剥き出しになった妻の生尻を見つけ、一瞬、ギョッと目を大きく見開くと、鶏ガラのように痩せた喉をゴクリと上下に動かしたのだった。
「見られてるぞ……食い込んだアソコを見られてるぞ……」
妻の耳元にそう囁きかけると、妻は「やだ……恥ずかしい……」と生温かく呟き、そのままハァハァと荒い息を吐きながら私の乳首をレロレロと舐めた。
ゆっくりと首を起こしながらカーテンの隙間を覗くと、妻の尻に顔を近づけている嶋田さんが見えた。真っ赤に充血した目を大きく見開きながら、まるで散歩後の老犬のようにバウバウと荒い息を吐いていた。
私の乳首を唾液でネトネトに濡らした妻は、そのまま舌をゆっくりと下げて行った。
妻の顔が移動すると同時に尻の向きも変わった。当然、妻の尻を覗き込んでいる嶋田さんの体勢も変わった。
カーテンの隙間から嶋田さんの顔がはっきりと見えた。
嶋田さんは妻の尻の谷間に鼻を近づけ、目を半開きにさせながらクンクンと匂いを嗅いでいた。
萎んだペニスを口の中に吸い込んだ妻は、まるでウドンを啜るかのようにジュルジュルと音を立てながら、その萎えたペニスを口から出したり入れたりと繰り返した。
その度に妻の唾液が大量に溢れ、睾丸に溜った唾液はタラタラと肛門に垂れて行った。
勃起していなくともその快感は亀頭に広がっていた。
射精したくとも射精できないという悶絶地獄を彷徨いながら、ふとカーテンの隙間に目をやると、いつの間にかそこに嶋田さんの姿はなかった。
ソッと首を起こし、カーテンの隙間から隣のベッドを覗き込んだ。
ベッドに潜り込んだ嶋田さんの痩せこけた肩が見えた。
刺激が強すぎたのだろうか。
そう思いながら淋しそうな嶋田さんの背中を見つめていると、この余命半年の男に、逆に気の毒な事をしたような気がしてならず、私はその残酷な行為に激しく後悔したのだった。
私の指と舌で三回絶頂に達した妻は、満足げにヒールを鳴らしながら病室を出て行った。
妻が出て行ったと同時に、いつもの夕食のメロディーがスピーカーから流れ出した。
今夜の私の夕食もまたウサギの餌のようだった。
カーテンの隙間からチラッと隣を見ると、嶋田さんのおかずは丸々とした鳥の唐揚げだった。
いつもなら、食事中はカーテンを開放し、雑談をしていたが、しかし今日は互いに気まずく、どちらもカーテンを開けようとはしなかった。
病室には重たい空気が漂い、箸をカサカサと鳴らす音だけが淋しく響いていた。
すると突然嶋田さんがカーテンを開けた。
嶋田さんは目を伏せたまま、「あのぅ……」と呟いた。
私は甘酒のようなお粥が入った椀を静かにプレートに置きながら、気まずそうに「はい……」と返事をした。
「明日も……奥さんはお見えになるのでしょうか……」
嶋田さんは不審に目をキョロキョロさせ、唇をペロペロと舐めながら聞いて来た。その仕草は、ひと昔前に流行った『ものまね大座決定戦』で、コロッケが野口五郎のモノマネをする仕草によく似ていた。
私はそんな嶋田さんを見つめながら、「来ると思いますけど……迷惑でしょうか」と恐る恐る聞いて見た。
嶋田さんは無言で首を左右に振った。
そして私と目を合わせないまま、黙って私のプレートの上に鳥の唐揚げを置くと、そそくさとカーテンを閉めながら、「奥さんに宜しくお伝え下さい……」と意味深に呟いたのだった。
翌日、またいつもの時間に妻が病室にやって来た。
淡いピンクのキャミソールに巨大な胸を突き出しながら、強烈なミニスカートを履いていた。
きっと、見知らぬ患者に股間を露出したという、昨日のスリリングなプレイがまだ体を火照らしているのだろう、私はそんな妻のいやらしい格好を見て、一目で妻の期待を読み取ったのだった。
いつものようにベッドサイドの整頓をしようとした妻を、さっそくベッドに引きずり込んだ。
「昨夜、誰かとヤったのか?」
私は妻の耳元に熱い息を吹き掛けながらいやらしく囁いた。
「ヤるわけないでしょ……」
妻は意地悪そうにせせら笑いながら私の胸に顔を押し付け呟いた。
「今まで変態親父達に散々調教されてきたおまえだ……昨日の露出であの時の変態欲が甦ったりして、また田辺の爺さん辺りと逢っていたんじゃないだろうな……」
ほんのりと茶髪に染まった髪を優しく撫でながら聞くと、妻は頬をプクッと膨らませては、「また、ってなによ、田辺とはあれから一度も連絡してないわよ……」と拗ねたフリをした。
そんな妻が妙に愛おしく感じた。
きっと今の妻は肉棒が欲しくて欲しくて堪らないはずだ。
それをやれない自分の不甲斐なさに腹が立つと共に、指と舌だけで我慢している妻が愛おしくて堪らなかった。
私は妻の肩を抱きながら、ソッとカーテンを開けた。
カーテンの隙間から、ベッドに座ったままジッと床の一点を見つめている嶋田さんの姿が見えた。それはまるで試合を待つボクサーのようだった。
私はそのままベッドに仰向けに寝転がった。
妻はそんな私を柔らかく微笑みながら見下ろし、ゆっくりと体を移動させた。
私のベッドと嶋田さんのベッドの間の通路で、妻のヒールがコツンっと鳴った。
何の指示もされないのに、妻は自らの意思でその位置に立った。
やはり妻は、昨日の続きを求めていたのだった。
一方の嶋田さんも妻と同じ気持ちだったらしく、妻の細い足首がカーテンの裾から見えるなり、待ってましたとばかりに大きく深呼吸しながらカーテンに顔を近づけていた。
妻は私のパジャマのズボンをゆっくりと下ろしながら、昨日と同じようにカーテンに向けて尻を突き上げた。
私は妻と嶋田さんを交互に眺めながら、二人の変態性に激しく興奮していた。
「もう、濡れてるの……」
妻は悲しそうな表情でそう囁きながら、私の萎れたペニスをクニャクニャと弄り始めた。
「やっぱり、見られたかったんだな……」
妻の大きな胸を優しく擦りながらそう呟くと、妻は怪しい目で私の目をジッと見つめたまま「いじわる……」とポツリと呟き、そして後手でカーテンを手繰りながら、カーテンの向こう側に尻を突き出したのだった。
そこまで大胆な事をするとは思ってもいなかった私は、カーテンの向こう側で怪しく揺れている尻に激しい嫉妬を感じながらも、もう一方で凄まじい興奮に包まれていた。
私はハァハァと荒い息を吐きながら、カーテンの向こうの妻の尻に手を伸ばした。
ムチムチと手の平に吸い付いてくる尻肉を優しく撫でた。不意に嶋田さんの熱い鼻息が私の手の甲に吹き掛かった。
そのまま尻肉の谷間へと指を移動させた。
さてさて今日の妻のパンツはいったいどれだけ濡れているだろうかと、期待に胸を膨らませながらゆっくりと指を下ろしていくと、いきなり指先にヌチャっと熱い感触を感じた。
「えっ?」と妻の顔を見た。
「パンツ、もう脱がされちゃったのか?」と妻に聞きながら、尻一体を手探りしながらパンツを探した。
すると妻は、萎んだペニスをペロペロと舐めながら、「ノーパンで来たの……」と呟き、そのまま萎んだペニスをジュルジュルと口内に吸い込んだ。
こいつはとんでもない変態野郎だ、と憤りを感じた。
こんな短いスカートでノーパンとは、もしここに来るまでに誰かに見られたらどうするんだと、凄まじい焦燥感が私を襲った。
しかし、そんな焦燥感は更に私の性的興奮を激しく煽った。
性器を剥き出しにしたままバスに乗っている妻を想像し、一向に立たないペニスをウズウズさせては悶えた。
そう悶えながらソッとカーテンの隙間を覗いた。
いきなり目の前に剥き出された膣に、嶋田さんは蝋人形のように固まってしまっていた。
そんな嶋田さんを観察しながら、私は妻の膣を開こうとした。
しかし、あまりにもヌルヌルに濡れている為、両サイドの小陰唇が私の指からツルンっと滑り、なかなか思うように開けない。
何度かそれを繰り返していると、不意にペニスを摘んでいた妻の右手が消えた。
妻は私からソッと目を反らすと、両手を後手に回し、なんと、自分で性器を大きく広げてはカーテンの向こう側の嶋田さんにその内部を露出したのだった。
両手で性器を広げながらペニスをしゃぶっていた妻が、いきなり「あうっ!」と唸った。
そんな妻の異変に気付いた私は、何事かとカーテンの隙間を覗いた。
すると、妻の性器にむしゃぶりつく嶋田さんの姿が見えた。気が狂った犬が水を飲むように、大きく突き出した舌を高速でレロレロと動かしている嶋田さんの目は、もはや完全にあっちの世界に逝っていた。
一瞬、勝手な事をする嶋田さんにムカッときた私だったが、しかしよくよく考えれば、この状況で手を出さないようにしろという方がおかしく、長期入院で欲求不満が溜った嶋田さんが妻に手を出すのは当然だろうと納得できた。
一方の妻も、見知らぬ男にいきなり性器を舐められ、狂ったように感じまくっていた。そんな妻の乱れように、やはり妻もかなりの欲求不満が溜っていたんだろうと思った私は、店の客達と乱れるよりは嶋田さんのほうがマシだと自分に言い聞かせ、こちらも素直に納得する事にした。
が、しかし、事態はそれだけでは済まなかった。
私の太ももに爪を立てながら、あんあんと狂ったように悶えまくっていた妻が、なんと、私の睾丸を頬に押し当てながら、「入れて、入れて欲しい」と呟き始めたのだ。
さすがにそれはマズいと思った。
なんといっても今の私はインポである。指や舌でなら嶋田さんに対抗する事も出来るが、しかしペニスでは太刀打ちできないのである。
今ここでペニスを入れられれば、恐らく妻は、久しぶりの肉棒の感触に狂人のように感じまくる事だろう。
そうなれば夫である私の立場はない。完璧なまでに嶋田さんに妻を寝取られてしまうのだ。
私は焦りながらも、「それだけはダメだ。辛抱しなさい」と股間の妻に言い聞かせた。
しかし火のついた妻は聞く耳を持たなかった。
入れて入れて、と放心状態で喚きながら、カーテンの向こうで尻をくねくねと振っているのである。
これでは嶋田さんもその気になってしまうと焦った私は、カーテンの向こうから妻の体を引き戻そうとした。
と、その瞬間、尻を突き出していた妻の腰が弓のように激しく撓り、
まるでジェットコースターで急降下しているような悲鳴をあげた。
私は慌ててカーテンを引いた。
案の定、開かれたカーテンの向こう側で、嶋田さんが妻の尻を両手に抱えながら、丸い尻の谷間にカクカクと腰を振っていたのだった。
一度入れてしまったものは、今更どうしょうもないと私は諦めた。
ガクリと肩を落としながら、私の股間で悶え狂う妻を見下ろした。
見知らぬ男にオマンコされながら夫のペニスをしゃぶる妻。
私はそんな妻の髪を優しく撫でながら、「感じているのか? 見知らぬ男にヤられて感じているのか?」と嫉妬深げに囁き、奥歯を噛み締めた。
狂ったように悶える妻と、そんな妻の尻にパンパンと乾いた音を立てている嶋田さんに凄まじい嫉妬の念を抱きながらも、しかしその一方では、目の前で妻が寝取られているというこの現実に、今までにない強烈な性的興奮を感じているのも事実だった。
私は尻肉が激しくバウンドする結合部分をソッと覗き込んだ。
嶋田さんのペニスは私のペニスよりもひと回り小さかった事がなによりの救いだったが、しかし嶋田さんのペニスは私には無い力強さを持ち、凄まじい早さで妻の性器をズボズボと突きまくっていた。
粘膜が糸を引く結合部分からソッと顔を上げると、勝ち誇ったように私を見下ろす嶋田さんとふと目が合った。
「……どうですか……妻の具合は……」
私は絶望の目で嶋田さんを見上げながら聞いた。
「素晴らしいオマンコです……ギュンギュンとチンポを締め付けて来ますよ……」
ハァハァと荒い息を吐きながらそう答える嶋田さんは、まるで妻の膣穴の細部まで確かめるかのように、時折目を閉じては乾いた唇をペロペロと舐めていた。
ぐちゃぐちゃと響くいやらしい音をBGMに、私はソッと妻の顔を覗き込んだ。
ベッドに顔を押し付けては声を押し殺していた妻は、それでも私のペニスを握ったままだった。
そんな妻の顔をベッドから離し、妻の愛おしい唇にキスをした。
目を半開きにさせながらハァハァと荒い息を吐く妻。そんな妻の頬に唇を押しあてながら、今、愛する妻が他人に寝取られているんだと自分に何度も言い聞かせ、私の感情は、絶望の穴底に落ちたり、興奮の山に登ったりとそれを何度も繰り返していた。
すると突然、妻のハァハァと荒い息がピタリと止まった。
妻はベッドからガバッと顔を上げると、真剣な表情で私を見た。
「ど、どうしたんだ急に……」
驚きながら妻にそう聞くと、妻は眉間にシワをキュッと寄せながら、「立った……」とポツリと呟いた。
「立ったって、何が?……」
そう首を傾げた瞬間、妻は私のペニスをおもいきり引っ張りながら叫んだ。
「なに言ってんのよ! 立ったのよ! ほら、見てよ! あなたのおちんちん、こんなにビンビンになってるじゃない!」
私は「えっ!」と唸りながら慌てて顔を下げた。
股間からニョキッと伸びるそれは、まるでひと昔前のコカコーラの瓶のようだった。
黒くて固くてゴツゴツして、そして嶋田さんのモノとは比べ物にならないくらいに太かった。
「おおぉぉぉ……」
おもわず唸ると、すかさず妻がペニスにしゃぶりついて来た。
ベポベポベポっという懐かしい音が股間から聞こえて来た。
亀頭から伝わる快感は、まるで電気が走ったように強烈で、こんな凄い快楽は生まれて初めてだった。
私は「ごめんなさい」と嶋田さんに呟くと、そのまま妻をベッドの上に引きずり上げた。
ボールペンのようなペニスをピーンっと突き立てたままの嶋田さんは、「あれ?」と首を傾げながら腰をカクカクと動かし、しばらくエアーセックスをしていた。
「後で必ず貸しますから、先にヤらせて下さい」
嶋田さんにそう告げながら、横たわる妻の尻にグイッと腰を突き立てた。
私の肉棒はいとも簡単に妻のオマンコの中に滑り込み、妻の子宮をドン! と突いた。
脳天を貫くような快感が私を包み込んだ。
妻がワッと泣き出し、同時に小便をビュッ! と洩らした。
私と妻は、呆然と立ちすくむ嶋田さんに見つめられながら獣のように交わり合った。
何度も何度も絶頂に達しながら、夫婦互いに快楽の渦の中に飲み込まれて行ったのだった。
窓の外には、学芸会の紙雪のような軽い粉雪がチラホラと舞っていた。
窓際に設置されたスチームヒーターが、窓に無数の水滴を作り、それがダラダラと垂れては窓下の白い壁にシミを作っていた。
完全に設計ミスだろ、とそのシミを見つめながらツッコミを入れると、テレビから聞き慣れたクリスマスソングが聞こえて来た。
入院してかれこれ一年が過ぎようとしていた。
ここで過ごすクリスマスは二度目で、恐らく正月もまたこの息苦しい二人部屋で除夜の鐘を聞く事になるだろう。
そんな私の病状は一向に良くならなかった。いや、反対に悪くなる一方だった。
その原因は、嶋田さんの夕食だった。
食事療法を制限されていた私は、朝昼晩と嶋田さんから栄養のあるおかずを貰っていた。そう、毎日貸し出ししている妻の体の見返りに、私は嶋田さんから栄養を貰っていたのだ。
食事を制限されているにもかかわらず、旨味たっぷりの食肉タンパク質を毎日むしゃむしゃと貪り喰っているのだから糖尿病が良くなるわけが無かった。
私の糖尿が悪くなる一方で、嶋田さんの病状はみるみると回復していた。今ではすっかり顔色も良くなり、もはや余命云々という話しはどこかに消えてしまっていた。
病室のドアがスススッと静かな音を立てて開いた。
廊下の冷気と共にクレゾールの香りが病室に忍び込んで来た。
部屋に入って来たのは嶋田さんだった。
今朝、何の予告も無くいきなり検査に連れ出された嶋田さんが戻って来たのだ。
「検査、どうでしたか?」
ベッドの上でブヨブヨに浮腫んだ足をプニプニと押しながら私は聞いた。
「ええ。おかげさまで、今日、退院が決まりました」
普通にそう笑う嶋田さんに、私はおもわず「はぁ?」と目を見開いた。
「あまりにも突然の事で私自身、信じられないくらいです」
嶋田さんは必死に嬉しさを堪えながらそう呟き、ベッドの下から埃の被ったボストンバッグを引きずり出した。
「それもこれも全て松田さんと、奥さんのおかげです。余命半年だと宣告されて絶望に打ちひしがれていた私に、お二人はパワーを与えてくれたんですからね」
ギギギッとボストンバッグのチャックを開けながら、嶋田さんはそこで初めて嬉しそうに微笑んだ。
私は、ベッドの下の嶋田さんに、よかったですね、と何度も呟きながらも、ソッと声を潜めた。
「嶋田さん……わかってると思いますが……退院後に妻と会うのは……」
すかさず嶋田さんは大きく首を振った。
「当然です。金輪際、奥さんとは会う事はないでしょう。約束します。お二人は私の命の恩人です。そんなお二人を裏切るような事は絶対にしませんから安心して下さい」
嶋田さんはそう固く約束してくれた。
嶋田さんは五年間もこの病院に入院していたのに、退院の準備はわずか五分足らずだった。
荷物をまとめた嶋田さんは、「このまま奥さんとは会わずに消えますので……」と言い残し、病室を去って行った。
この一年間、私と嶋田さんは妻の体を共有していた。
嶋田さんのおかげでインポがすっかり治った私は、月・水・金に妻を抱き、嶋田さんは火・木・土に妻を抱いた。
そして日曜日は3Pをした。
3Pでは色んなプレイを楽しんだ。
SMまがいのプレイや、三人で全裸になって深夜の廊下を徘徊した事もあった。
そんな馬鹿馬鹿しい思い出が、テレビから聞こえるクリスマスソングと共に甦り、私はおもわず一人窓の外を見ながらクスッと笑った。
しかし、本当に嶋田さんを信用していいのだろうか?
粉雪の空にボツンと聳える銭湯の煙突を見つめながら、ふとそんな不安が過った。
妻はかなり嶋田さんの事を気に入っていた。あれだけ変態な妻だから、私に隠れて嶋田さんに連絡する可能性は高い。
その時、嶋田さんは本当に約束を守ってくれるだろうか……
そんな約束が絶対に守られると確信できたのは、嶋田さんが退院して五日目の朝だった。
末期ガンで手の施しようがなくなっていた嶋田さんは、退院して五日後の朝に、妻子のいないひとりぼっちのアパートでひっそりとこの世を去った。
嶋田さんは、私との約束を永遠に守ってくれたのだった。
(ふたり部屋・完)
《←変態病院物語短編集・目次へ》