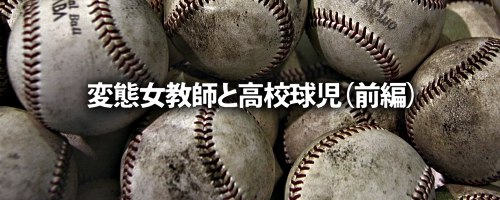変態女教師と高校球児(前編)
2009/08/21 Fri 12:04
1
その先生のお尻は桃のように見事に丸かった。
先生が部室にやってくると、グローブやバットの手入れをする部員達は一応モソモソと手は動かしているものの、しかしその目は桃のように丸くカーブを描く先生のプリップリの尻に釘付けになっていた。
「おはよう」
日帝高校野球部の選手マネージャーという役職を受け持つ京香先生は、いつものように部室に入るなり皆に向かって明るい笑顔を振りまいた。
京香先生が部室にやってくると、それまで汗と水虫とチンカスが入り交じったような悪臭が漂う部室が一瞬にして「オンナの匂い」に変わる。
部員達は皆、京香先生の髪や衣類から匂い立つその女の香りに目眩を感じながら、グローブを拭き拭きしつつ「今夜も先生をネタに・・・」と密かに企むのであった。
日帝高校野球部。
初の甲子園出場高校。
それまで野球部を懲役のように扱っていた校長だったが、この夏、甲子園初出場が決定するや否やチョウチンアンコウのような顔をして喜び狂い、今までいわれなき差別を虐げられて来た野球部はこのチョウチンアンコウの手によって数々の優遇処置を受ける事となった。
そのひとつが「選手マネージャー」の配置だ。
元々野球部にはマネージャーと名のつく雑用係は、スクールウォーズに出て来たようなハリキリ女マネージャーの弘田利江(通称・タッチ)と、妙におっちょこちょいな眼鏡デブ娘の村田杏子(通称・おむすび)の二人がいたが、しかしその二人の熱血スポ根マネージャーと此の度新たに設置された「選手マネージャー」とは方向性が明らかに違った。
選手マネージャーとは、従来のマネージャーのような、洗濯・ボール磨き・ノックの玉渡し・スコアブックへの記録・タイム測定・・・といった雑用ではなく、選手の健康管理を主とした精神的肉体的カウンセラーだ。
ま、いわゆる、野球部の中の「保健室の先生」みたいな感じの癒し系部門。
ただしこれはチョウチンアンコウ校長がアメリカの心理臨床家C・ロジャースとかいうなんだかわかんない人の本を読んだ事だけがきっかけで作られた役職なわけで、そのカウンセリングがいったいどれほど選手に対して効果があるのかは疑問だった。
そんな選手マネージャーに抜擢されたのが京香先生だ。
京香先生は教員歴1年のまだ新米教師で、生徒のカウンセリングはおろか野球についての知識などまったくなかったが、しかし学生時代に「生涯学習のユーキャン」で生活心理学入門の通信講座をほんの少しだけやっていたという実績?をチョウチンアンコウ校長に見初められ、それだけの理由で選手マネージャーに抜擢されたのだった。
2
「ふーっ・・・・」
京香は部室内にある「カウンセリング室」と大袈裟に書かれた小部屋に入るなり深いため息を付きながら診察ベッドの上に横になった。
京香のため息からはまだ昨夜の酒の匂いがほんのりと漂っている。
(それにしても昨夜のあのオトコ。大っきなオチンチンだったな・・・)
そんな事を考えながら眠そうな目で天井を見つめていると、小部屋の外から「京香先生!朝練いってきまーす!」という部員達の野太い声が響いて来た。
「はーい!頑張ってねー!」
京香はベッドに寝っ転がったままの姿勢で彼らを見送ると、部員達が出て行くのを見計らい大きなアクビをしたのだった。
京香は眠そうな目を擦りながら妙に固い診察ベッドの上でゆっくりと携帯電話を手にするとマイピクチャを開いた。
携帯の画面一杯に勃起したペニスの画像がずらりと並ぶ。
京香は昨夜の日付が付いた画像をクリックする。
ラムネの瓶のように太く逞しいペニス。それを虚ろな目をして喰わえている自分の写真がアップされた。
(やっぱりこの人、かなり大っきい・・・)
京香は画像の自分と同じくらい口を大きく開けながら(喉の奥までグイグイと入って来たもんね・・・)と、喉ちんこに受けた固い感触を思い出していた。
三沢京香。24歳。独身。
教師にしておくのはもったいないくらいのその抜群のプロポーションは、女子生徒達からは憧れの的でもあり男子生徒達からはオナニーの的でもあった。
京香は元々教師になる気はまったくなかった。
本当はファッションデザイナーの道を進みたかった京香だったが、しかし、両親が元教師、一番上の兄は教育委員会に勤め、そして二番目の兄もやはり中学校の教員といったそんな教員家庭に育った京香だったため、不幸にもふと気がつくと自分も教師になっていたのだった。
そんな京香にはある特殊な趣味があった。
それは趣味というよりもどちらかといえばフェチと呼んだ方がいいのか、京香はいわゆる「ペニスフェチ」なのである。
躾の厳しい教員家庭に育ち、清く正しく美しくをモットーに歩んで来たはずなのに、どこでどうそうなったのか京香自身にもわからないのだが、とにかく京香は「男性自身」が好きなのである。
それは淫乱性欲的に大きなペニスや形の良いペニスを好むといった感じのノリではなく、若い女の子がキティーちゃんやディズニーのキャラクターを収集するといった感じのノリだ。
そんなペニフェチの京香は今まであらゆる男達のペニスを試してみた。
デカそうな体育教師、固そうな黒人、遊んでそうな芸能人、白そうなアメリカ人、強そうな肉体労働者、臭そうなロシア人、知的な弁護士、インポの老人、痛そうなヤクザ・・・・・
ただしそれは、その男やセックスという行為が好きだから寝たのではなく、その男達の中心にぶら下がっているペニスだけに興味があるから寝たのだった。
快楽が目当てではなくコレクターとしてのペニフェチ京香は、大きさ、形の良さといった、いわゆる世間一般論でいう「立派なペニス」に対してそれほど興味は無い。
むしろそれよりも「異常に小さい・異常に大きい」、「強烈に臭い」、「歪な形をしている」といったレアモノを好む癖があり、偶然にもそんなペニスに出くわした時には、まるで空港で待ち伏せしているヨン様ファンのおばさま達のように「キャーキャー」と騒いではカメラのフラッシュを焚きまくるという変な癖があった。
しかしながら、そんな不気味なペニスをただ写真に撮ったりただ眺めているというわけでもない。
そんなヘンテコリンなペニスとセックスしてみたいという性的願望が強いのも確かである。
その証拠に、京香は男を選ばない。
その男のペニスが「不思議ちゃん」であれば、相手がホームレスであろうと性病持ちであろうとどれだけ不潔で不細工であろうとおかまいなしにセックスをさせた。
公園のベンチであろうと自動販売機の裏であろうと、まるで盛りの付いた犬のようにどこでだってヤらかしたのだ。
セックスそのものの快感よりも、レアなペニスを自分のオマンコに挿入したという貴重な体験に性的興奮を覚える京香は、俗にいう「変態」なのであった。
3
「先生、ちょっといいですか・・・・」
診察ベッドの上でウトウトとしていた京香は、生徒のその声ではっと我に帰り慌ててペニス画像の映る携帯電話をパシン!と閉じた。
「えぇ、いいわよ・・・」
京香はそう言いながらベッドから起き上がると、いかにも今までデスクワークをしていたかのように机の前に腰を下ろした。
ガッチャ・・・と扉が開き、泥だらけの少年が足を引きずりながら入って来た。
「柴田君、どうしたの?」
京香は柴田の引きずる足を見て驚いて立ち上がった。
「ちょっとスライディングで足を捻ってしまって・・・」
柴田は真っ黒に日焼けした顔を歪めながらそう言うと、今まで京香が寝転がっていた診察ベッドを指差し「横になっていい?」と言った。
京香は急いでベッドのカーテンを全開にすると、右足を庇いながら歩いて来る柴田に手を貸した。
「どうしよう・・・私じゃわからないわよ・・・保健室に行った方がいいんじゃない?」
柴田の体を支えながら静かに柴田を寝かせると京香は不安な表情でそう言った。
「いえ、ちょっと横になってればすぐに直ります。僕、膝が弱いからよくあるんですよ、これ・・・」
柴田は寝転んだまま右足を擦りながらそう言った。
京香はタオルを冷たい水で冷やしながら、「そう言えば、柴田君、前にもそこが痛いって言ってたよね・・・」と言い、半分だけ水を絞ると、その水の滴るタオルを持ってベッドに近付いた。
「とりあえず、冷やしとこっか・・・」
京香は柴田の泥だらけの靴下に手をやると、それを優しく脱がした。
「痛っ・・・」と顔を歪ませる柴田の素足からプ~ンとすえたニオイが漂って来た。
(このニオイ・・・竹岡さんのニオイに似てる・・・)
京香は柴田の足を冷たいタオルで拭きながらふとそう思った。
竹岡というのは、毎月一回変態セックスを楽しんでいるセックスフレンドの1人で、43歳の長距離トラックの運転手だ。
竹岡は露出趣味と匂いフェチというレベル5の変態で、毎月一回京香を呼び出す時には「絶対に風呂に入って来るな」と強要した。
洗っていない京香のアソコを美味しそうにネチネチと舐め回しながら、同じく洗っていない恥垢だらけのペニスを京香にしゃぶらせる。
しかもそれは、店内に客がいるコンビニの駐車場やトラック仲間達が沢山いるドライブインなどにトラックを停めての車内行為で、京香のその卑猥な姿を多くの人に見せつけるといった変態露出ぶりだった。
(そろそろ竹岡さんから連絡が来る頃かな・・・・)
京香は竹岡から受ける変態行為をアレコレと思い出しながら竹岡のペニスの匂いのする柴田の足を拭いていると、自然にアソコが濡れて来るのがわかった。
一方の柴田の方も、まさか京香がマンコを濡らしているとは露知らず、そんな京香に足を優しく拭かれながらも今にもムクムクと勃起しそうな感情を懸命に堪えていた。
(ダメだダメだ。起つんじゃないぞ・・・・64-23=・・・・22×15=・・・イイクニツクロウカマクラバクフ・・・・ああ、ダメだ起ちそう・・・)
柴田は半分コリッとなりかけた股間の上に、ベッドの隅に置いてあったタオルケットをそっと掛けた。
そして再び起たない為の念仏をひたすら唱える。
唱えながらも、心とは裏腹に柴田の視線は京香の胸元に注がれる。
(うわぁ・・・柔らかそうなオッパイだ・・・・)
思った瞬間、高校球児のバットはピーンとライトスタンドに向けてそそり立った。
ヤッバ!・・・・と思ったが、しかし大丈夫。柴田の腰にはタオルケットがしっかりとガードしてくれている。
それをイイ事に思春期の丸刈り少年はこっそりと股間に手を伸ばし、コリコリになった亀頭をズボンの上からスリスリと擦った。
「この間も確か同じ場所だったよね・・・やっぱりちゃんとお医者さんに視てもらったほうがいいんじゃない?・・・・甲子園も控えてるんだし・・・」
京香はそう言いながら柴田の足首に湿布をペタペタと貼付けた。
そして「一応、膝にも張っておこうか・・・」とタオルケットを剥いだ瞬間、柴田はガバッ!と起き上がり「大丈夫!もう直りましたから!」と慌てて叫びながら部室を飛び出していったのだった。
4
「バカだな・・・ボッキを抑えるには母ちゃんの屁を思い出してみろよ、一発で萎えちゃうから」
素振りをする中島がケラケラと笑いながら柴田にそう言った。
「でもマジヤバかったよ、あのまんまだったらボッキしてたの京香先生にバレてたぜ」
柴田が大袈裟にそう説明すると、ベンチに座っていた有沢が「でもボッキしてんのがバレたらそのまんま京香先生とバコバコできたかも知れねぇじゃん」と笑った。
野球部員達の中で京香は「オナニーネタ☆ランキング」堂々の第1位だった。
「京香先生って彼氏いないんだろ・・・・俺達みたいな若い肉体を見たら堪んねぇだろ・・・」
ベンチから出て来た有沢が転がっているバットを拾いながら誰と無くそう言った。
「そうそう。あのプリプリの尻を見てみろよ、男が欲しいって誘ってるようなもんじゃねぇか・・・それに変態だし・・・」
ピッチングマシーンの調節をしていた栗田のその言葉に、近くにいた部員達全員がピタリと動きを止めると全員が一斉にリアルにゴクリと唾を飲んだ。
その唾の理由。
数週間前、部員の1人である鹿島がカウンセリング室に忍び込み、京香のロッカーを物色した事があった。
それは、夏の特別練習として野球部員は水泳をさせられるのだが、ある時、なんとそのプールに水着を着た京香先生が来たのだ。
プールで水着を着ているという事は、当然ノーパンである。
という事は、京香先生が今まで履いていたパンティーは・・・・と物凄い勢いで妄想した部員達は、さっそくプールの中でジャンケンをし、ジャンケンに負けた鹿島が京香のロッカーを漁るハメになったというわけだ。
鹿島はプールから上がると素早くコーチの元に走りより「昨夜アルツハイマーの母が夜食にと食べさせてくれたコンビーフはどうやら豆太郎のドックフードだったらしくその為今朝から激しい下痢を伴いこのままではプールの中で逆噴射をしかねないため早急にトイレに行かせてくらさい」と伝え、そそくさと部室に忍び込んだ。
カウンセリング室に入り京香のロッカーに手をやるが、当然鍵が掛かっている。
しかし京香が使っていたそのロッカーは、以前まで部室の隅に転がっていたロッカーで、部員達のエロ本貯蔵庫に使用されていたロッカーだ。
十円玉を扉の隙間に差し込みクイッと捻れば簡単に開くというスグレモノなのである。
鹿島は、以前エロ本を取り出す時にしていたように十円玉でクイッと捻ると、ロッカーの鍵はガッチャン!と簡単に開いた。
ハァハァと興奮しながら鹿島が扉を開けると、モアッ!と女の匂いがロッカーの中から溢れ出した。
京香の香りに目眩を感じながらも、鹿島はロッカーの下に乱雑に脱ぎ捨てられている京香の衣類を目にした。
几帳面な先生だと思っていたのに、こんなに乱暴に服を脱ぎ捨てているなんて・・・・
そんなギャップが鹿島を更に興奮させる。
鹿島はストッキングを手にするとそれを顔に押し付けた。
甘い香りが鹿島の脳を蕩けさせる。
鹿島はその香りに悶え苦しみながら思わずそのストッキングを顔に被ってしまう。
三流映画の銀行強盗のようにストッキングを被った鹿島は、ついでに京香のブラウスに袖を通しピチピチになりながらロッカーの底を探った。
そしてスカートの下でクシャクシャに包まっていたヒョウ柄の布の塊を発見するや否や、清純な女教師とは想像もつかないそのヒョウ柄に「女教師などとお高くとまってはいるが、所詮はサカリの付いた牝猫よのぅ」などと週間エロトピアのような恥ずかしいセリフを平気で呟いた。
鹿島には、一刻も早くこのヒョウ柄を男子トイレの個室に持っていかなければならないという使命があった。
京香がプールを上がる前に、部員全員にこのおかずを与えてやらなければならないのだ。
しかしそこまで鹿島は出来た人間ではない。
お宝を目の前にしてどうしてわざわざそれを他人に分け与えてやらなくてはならないのだ。
鹿島はビンビンに勃起したペニスを水着から取り出すと、それをゴシゴシとシゴきながらパンティーを開いた。
京香のパンティーのクロッチには、まるでカレーうどんをワイシャツに飛ばしてしまったかのような黄色いシミがポツンと付いていた。
ストッキングを被ったままの鹿島がそれをクンクンと嗅ぎ、ひとこと「くせぇ・・・」と呟く。
グロ趣味の無い鹿島には、このクロッチに染み付いた「臭い匂い」の芸術的センスがわからない。
あまりの臭さに瞬間に萎えてしまったペニスを水着に戻した鹿島は、被っていたストッキングをスポッ!と抜くと「がっかりだよ!」と最近まったくテレビで観かけなくなった桜塚やっくんのモノマネをして、数秒後、やっぱりモノマネなんてしなければよかったと凄く恥ずかしくなった。
と、その時だった。
ロッカーの下に置いてあった小さな段ボールの底に、何やら親近感のある色と形を発見した。
「ん?」と首を傾げながらソレを取り出す鹿島。
なんとそれは20センチ級の大型ディルドーだった・・・・
そんな鹿島の発見があってからというもの、部員達の京香を見る目は一気に変わった。
「巨大バイブをロッカーに隠し持つヒョウ柄パンツにウンコ付けた変態女教師がっかりだよ」
しかしそれは部員達にとって、幻滅ではなくむしろ「可能性アリ」と思わせる材料となったのであった。
5
「いっちょう仕掛けてみるか・・・」
ベンチから部員達の話しを聞いていた前原がそう言って立ち上がった。
前原は野球部の中でも戦略を立てるプロとして一目置かれる存在だ。
その戦略は監督も唸るほどで、今回この弱小野球部が甲子園に出られるようになったのも前原の戦略があったからだと言っても過言ではない。
そんな前原のニックネームは武田信玄の軍師・山本勘助だ。
「勘助。なんかいい案でもあるのか?」
素振りの手を止めた部員達が、目をギラギラさせながら勘助の周りに集まって来た。
「そもそも・・・・」
と、勘助の演説が始まった。勘助は戦略を演説する前は必ずこの「そもそも」を付ける癖がある。
「京香先生が俺達野球部のカウンセラーになったのはナゼだ?という事をみんなまず考えて欲しい」
勘助はもったいぶりながらみんなの顔を見回した。
「それは俺達が甲子園出場に決まったからだろ」
何故か体育座りで聞いていた中島が呟いた。
「では、なぜ甲子園に出場が決定したらカウンセリングが必要なんだ?・・・・はい有沢!」
勘助は、同じく体育座りの姿勢で聞いていた有沢に向かって素早く指を差すと、ピタリと止まったまま有沢の答えをジッと待っている。
まるでどこかの羽毛布団セールス会社のインチキ集会のようだ。
「なぜって・・・俺達の精神面を・・・和らげるっつうか・・・」
勘助に当てられた中島はビクビクしながらそう答えた。
答えを間違えると勘助ミーティングがやたらめったら長引くからだ。
「・・・精神面を和らげる。そう、いわゆるこれは甲子園という大きなプレッシャーを背負った俺達の精神はズタズタに不安定だろうと予測した校長の策略なのだ!」
勘助の声はグラウンドにやまびこのになって響いた。
部員達はこの勘助劇場が長くならなければいいが・・・と密かに思う。
「校長は、今、俺達に不祥事を起こされるのが怖いんだよ。特に、性的な不祥事を・・・」
勘助は軽く咳払いをすると空を見上げた。
「俺達は若い。その為、大いに性欲がありあまっている。そのエネルギーをどこで消費させるのか?・・・風俗か、若しくはレイプ、はたまたチカンか・・・そんな事をしでかしたら甲子園は水の泡となる・・・・」
勘助はゆっくりと遠くを見つめた。
「校長の策略。ズバリ言おう。京香先生は、俺達の性処理として我が野球部に配属されたのだ・・・」
いつしか全員が体育座りになっていた。
全国の甲子園出場校でこんな話しを真剣にしているのは恐らくこの学校だけであろう。
「校長は俺達の性的不祥事を怖れている。しかし性欲というものは『止まれ!』といって簡単に止まるものではないそんな事は校長は百も承知さ。そこでヤツは俺達に当て馬を送り込んで来たというワケさ、しかもド変態の女教師をな」
勘助は乾いた喉を癒そうとポケットからペットボトルを取り出しゴクリと飲んだ。
部員達も勘助のそのゴクリに合わせて唾をゴクリと飲む。
「・・・あの女教師もそれなりに問題があるのさ。変態、淫乱、これは教育者にとって致命傷になるからな。きっと校長の野郎はあの女教師がいつ性的不祥事を起こすかとビクビクしてたんだろう、そんな時に俺達の甲子園出場だ、これは熊さん一石二鳥ってなもんだっといった具合で、性欲の溜まりすぎでいつ爆発するかも知れない危険な俺達の所へあの変態女教師を送り込んで来たってわけさ」
「・・・って事はヤっちゃっていいって事か?」
セカンドの野村が鼻づまりの声でそう言った。こいつは慢性の蓄膿症の為に鼻からの呼吸が出来ず、その分皮膚呼吸で酸素を取り入れているという爬虫類のような男だ。
「基本的にはヤっちゃってもかまわないだろう。たとえば今から全員であの変態女教師を姦した所で、それを表沙汰にはできないだろうよ校長は。ただ、そこで問題なのが、果たしてオマエ達に今から先生をレイプする度胸が本当にあるのか?・・・って事だ」
勘助の言葉に、全員がゆっくりと下を向いた。
性欲が爆発寸前な彼らだったが、しかしいざレイプとなると・・・腰が引けた。
「・・・じゃあどうすればいいんだよ・・・」
ヤリたいけどヤル度胸が無い。そんなジレンマの中、誰かがポツリと呟いた。
一瞬にして希望をなくした高校球児達は、すがるような目をして軍師・勘助を見た。
そんな彼らの目をゆっくりと見渡しながら、ゆっくりと勘助が空を見上げる。
「・・・向こうが当て馬を送って来たなら、こっちも当て馬を送るまでさ・・・」
勘助が静かに顔を元に戻し皆を見つめながらニサリと笑った。
「目には目を歯には歯を・・・」
そう言いながら勘助が指を差したその先には、ベンチの奥でボールをセッセと磨く補欠の三助がいたのだった。
6
学校を出た中村三助はいつものように電車に揺られながら、グラウンドで勘助から言われた言葉を思い出していた。
「いよいよお前の出番が来た。明日の練習後、代打で試合に出てもらう」
勘助のその言葉の意味はいったいなんなのか?
補欠の三助に代打などという大役はこれまで一度も回って来た事は無い。いや、それどころかこの三年間一度だって試合のバッターボックスに立った事などないのだ。
(どうして僕が代打に・・・それに明日の試合ってのはいったいどういう事なんだろう・・・)
勘助の言葉を気にしながら電車の吊り革にぶら下がっていた三助は、ふいに股間を誰かにくすぐられビクンと体を強ばらせた。
(また・・・あの人だ・・・・)
三助は恐る恐る股間をくすぐる手の方に振り返った。
後にピッタリと寄り添うように立っていた30歳前後のおばさんが、三助と目が合うなりニッと笑った。
(うわぁ・・・やっぱりあの人だ・・・どうしよう・・・)
三助は吊り革をキュッと強く握る。
おばさんの手は三助の股間を散々揉みまくった挙げ句、今度は三助の筋肉質なプリプリ尻を指で押したり摘んだりとしてきた。
おばさんは三助の耳元に唇を近づけ「少し足を開きなさい」と優しく言った。
しかしその優しい声はどこか命令口調で、気の小さな三助はいつもその命令に逆らう事ができなくなるのだ。
三助は辺りを気にしながらも、おばさんの命令通りにゆっくりと足を開いた。
おばさんの手が開いた三助の股からニョキッと飛び出すと、手慣れた手つきでゆっくりとズボンのジッパーを降ろし始めた。
そして三助のパンツの中に五本の指を忍び込ませると、既にビンビンに勃起している三助のペニスをギュッと握りしめ、電車の音に合わせるかのようにリズミカルにソレをシゴき始めたのだった。
「この駅で降りなさい・・・」
電車のブレーキが車内に響き始めた頃、おばさんは三助の耳元にそう呟いた。
三助はブレーキの音を聞きながらどうしようかと迷っていた。
先日、おばさんから踏みつけられた太ももはまだズキズキと痛むのだ。
またこの間のように蹴られたり叩かれたりするのではないかと三助は脅えながらも、しかし、電車のドアが開いた瞬間、体はおばさんの後ろに付いて歩いていたのだった。
駅を出てしばらくおばさんの後を付いて歩くと、大きなマンモス団地が現れた。
先日は駅の公衆便所だった為、今回も同じ場所かと思っていた三助だったが、今日はどうやらそのマンモス団地にある公園の公衆便所のようだ。
いつものようにおばさんが先に男子トイレの個室に入ると、その後に付いて三助が素早く個室に入り込んだ。
個室に入るなり、いきなり三助はキスをされた。
おばさんの生暖かい舌が三助の口の中にヌッと侵入し、戸惑う三助の舌をコロコロと舐め回した。
三助はまだ童貞だったが、しかしキスはこれで三度目だ。
その三度のキスはいずれもこのおばさんだった。
おばさんがゆっくりと唇を離すと唾液がヌチャッと糸を引いた。
おばさんはその唾液の糸を見つめながらハァハァと息を荒くさせ、そして「服を全部脱ぎなさい」と命令した。
三助はただひたすらおばさんの命令に従うだけだった。
どうして僕が・・・とも思うが、しかし体が勝手におばさんの命令に従ってしまうのだ。
三助がトランクスを脱いで全裸になると、おばさんは三助の包茎の皮を指でおもいきり引っ張りながらケラケラと笑った。
そしていきなり三助の頬に平手打ちをすると「6年前、あなたは私に何をした?」と目を大きく開いた。
頬をヒリヒリとさせながら三助はただ俯くだけだ。
このおばさんはいつも意味不明な事を口走りながら三助の頬を叩くのだ。
「諏訪湖であなた言ったわよね、結婚しようって」
おばさんは三助の頬を指で摘んだ。
おもわず三助が「イテテテっ」と口走ると、再び右頬をおもいきり引っ叩かれた。
「正座しなさい」
目をギラギラと光らせたおばさんはハァハァと息を切らせながら、全裸の三助にトイレの床に正座するように命じた。
三助がタイル張りの床に膝を揃えると、それを見下ろすおばさんはゆっくりとスカートを捲り上げた。
おばさんはノーパンだった。
ブヨブヨの下腹部に剛毛な陰毛。その亀の子たわしのような陰毛の中に赤く爛れた穴が濡れて光っていた。
おばさんは片足を便座の上に置くと、その剛毛の中に指を忍び込ませ、「♪チャラララララ~♪」とポールモーリアの「オリーブの首飾り」を口ずさみながら三助の目の前でゆっくりと穴を開いた。
透明の汁をキラキラと輝かせながら穴はパックリと口を開いている。
三助はおばさんのストリップを見ながらおもわず勃起したペニスを握っていた。
オリーブの首飾りがピタッと止むと、おばさんが鬼のような形相で三助を見下ろしながら「・・・誰がハーレダビットソンを触ってもいいと言ったのだ重吉・・・・」とまた意味不明な事を呟いた。
と、その瞬間、おばさんの靴の踵が三助の太ももにグイッ!と食い込んだ。
「うっ!」と仰け反る三助に、おばさんは穴を三助の顔に近付け「舐めろ。おまえの子供が眠っている穴だ~よ~。綺麗に舐めろ。水子だ水子だ、ほら、ほら」と迫って来た。
三助はおばさんのその穴の匂いに目眩がした。
先日よりも更に臭いはキツく、そのニオイはまるで腐った魚のようなのだ。
おばさんは「ほら、ほら」と股間を顔に押し付けながら、右足の爪先で三助のペニスをグリグリと押した。
初めのうちはペニスに激痛が走るが、しかしその痛みは不思議と快感に変わって来る。
痛さと快感の狭間に立たされた三助は、顔に押し付けられたおばさんの穴に舌を伸ばした。
おばさんはハァハァと言いながら自分でクリトリスをグリグリと刺激している。
ネチャネチャの粘膜が三助の顔中に塗りたくられた。
三助の顔は魚屋の裏に捨てられている発泡スチロールのようなニオイが漂っていた。
「立ちなさい中井重吉42歳・・・」
再びおばさんの命令が下った。
三助がゆっくりと立ち上がると同時に次はおばさんが床にしゃがんだ。
「まぁ、なんて赤いチンポなんだろうねぇ~赤とんぼみたいよ~・・・それに酷く臭いねぇ・・・」
おばさんは三助のペニスの皮をゆっくりと剥き、露出された真っ赤な亀頭を愛おしそうに見つめながら「くっさい!くっさい!」と何度も呟いた。
実際、練習後の三助のペニスはとてもとても見れたものではなかった。
仮性包茎の皮に包まれた亀頭には真っ白な恥垢がびっしりとこびり付き、その恥垢の奥にテカテカと輝く真っ赤な亀頭が猛烈なニオイを発しながら息づいているのだ。
おばさんは三助のペニスをポロンと口の中に頬張ると、ジュブジュブと音を立てながらしゃぶり、そしてしゃがんだ股間の中で激しく指を動かしていた。
時折、おばさんがペニスをしゃぶりながら「あーんぱーんまーん!」と叫び金玉の皮をおもいきり引っ張る。
おもわず声が出そうなくらいの激痛だったが、しかし何度かそれをやられるうちにその痛みは快感に変わって来ていた。
(ちなみにジャムパーンマーンの時は金玉にデコピンする)
いつものようにおばさんの股間からシャッ!シャッ!と小便が飛び散る。
おばさんは手を小便でベトベトに濡らしながらも、穴の中に三本の指を突っ込んでは「あふーっあふぅーっ」と唸りながら指でアソコを掻き回していた。
おばさんの小便が三助の足に引っかかる。
その生暖かさを感じながら、三助はペニスの先から大量の精液を放出した。
おばさんは三助の精液を旨そうにジュルジュルと吸い込みながら、いつのまに持ち出したのか黒いバイブを穴の中に押し込んでいったのだった。
(後編へ続く)
《←目次へ》《後編へ→》